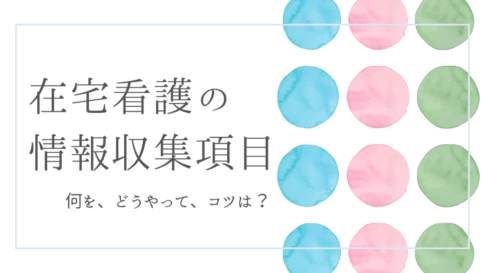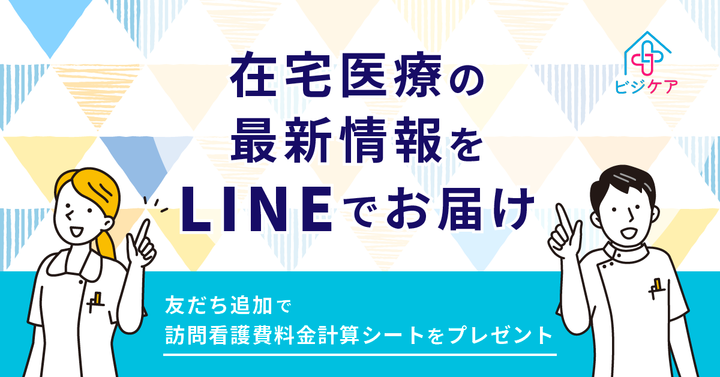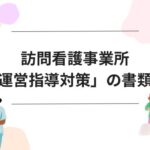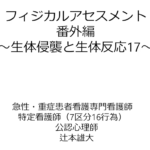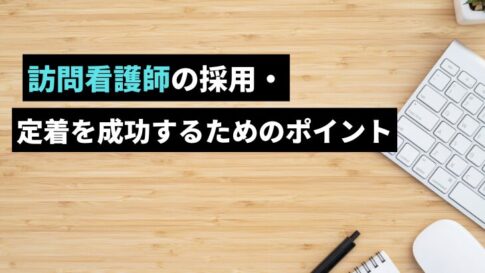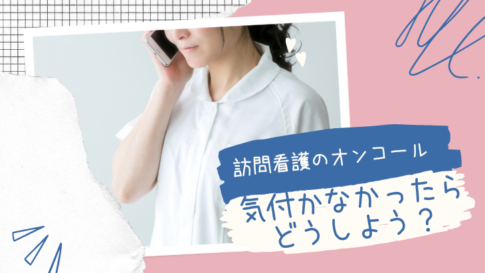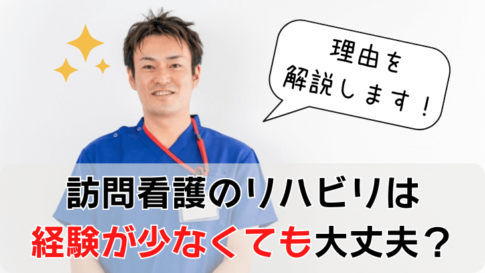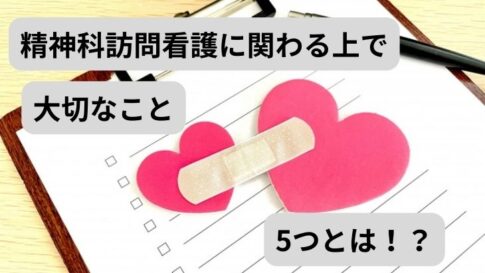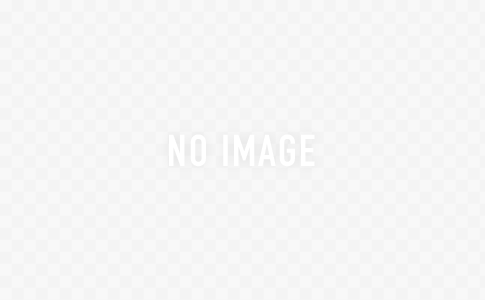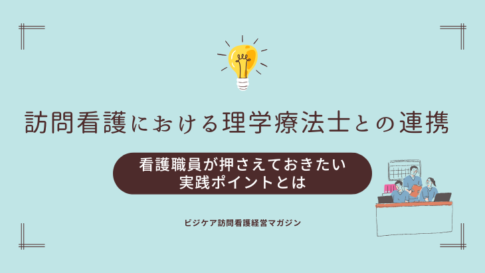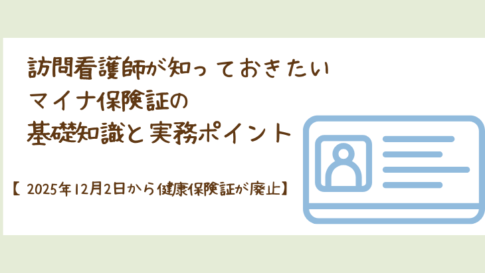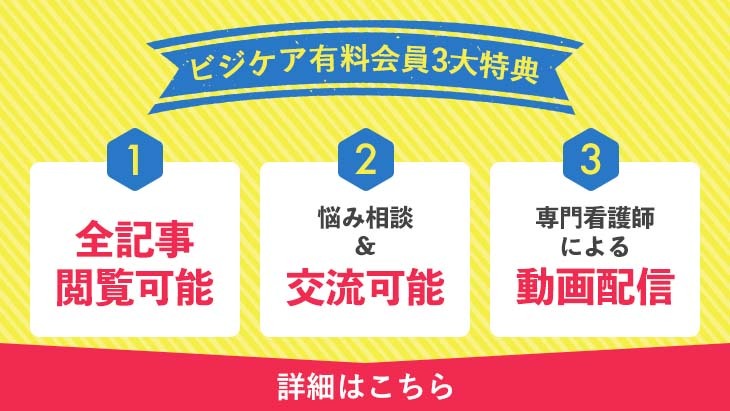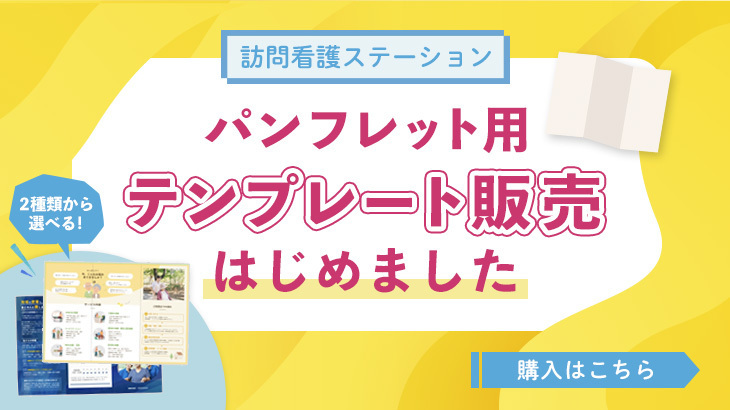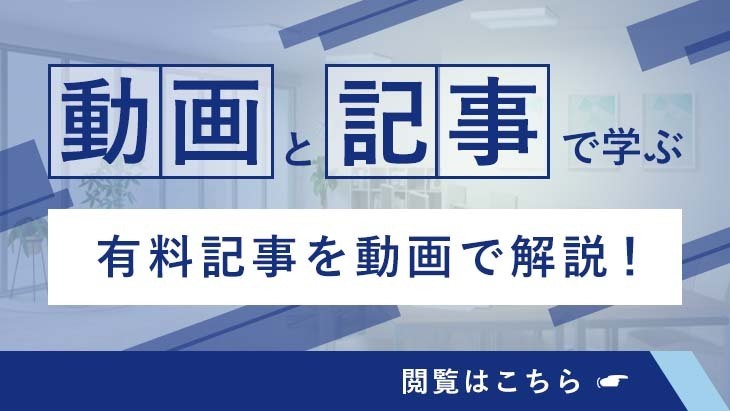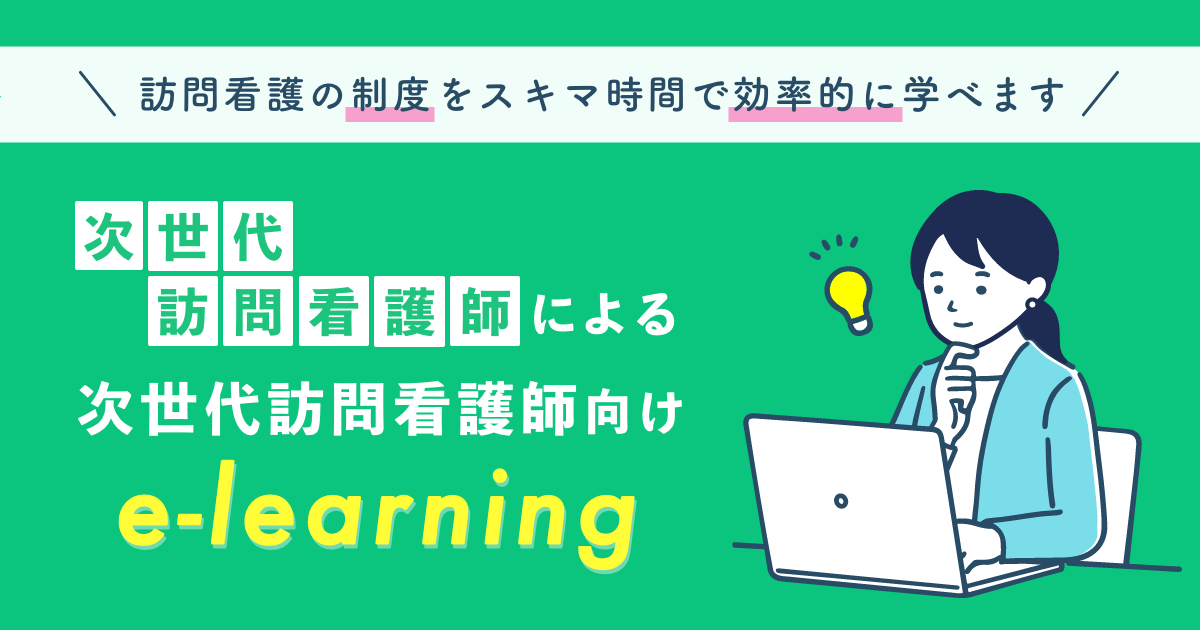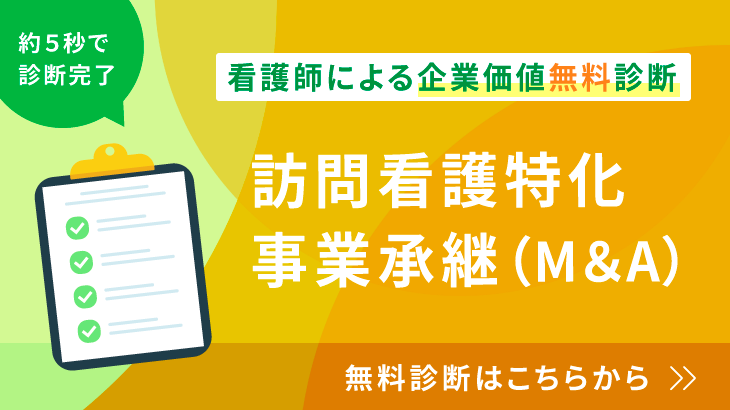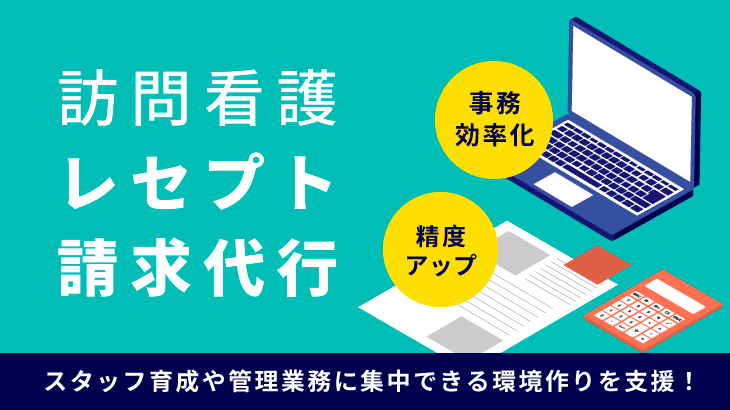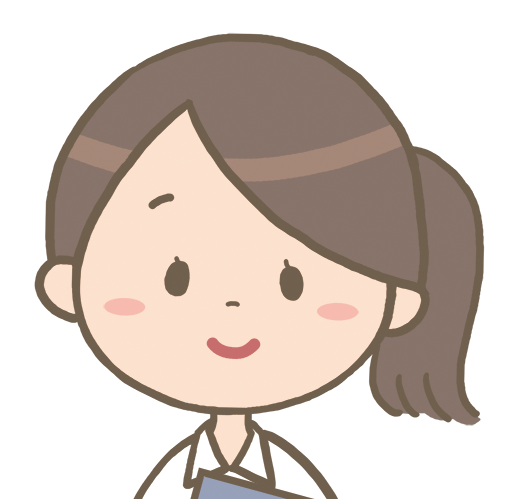
訪問看護の現場で最も重要なスキルのひとつが「アセスメント」です。
なぜなら、利用者さんの状態を正しく見立てて必要なケアを判断し、サービスを提供する必要があるからです。
さらにリスクを防ぎ、生活の質を高めることにつながります。
しかし、現場では「訪問看護師によって見立てが違う」「情報が共有されていない」という課題も少なくありません。
本記事では、訪問看護におけるアセスメントの考え方と実践のポイントを、具体例を交えながら解説します。
目次
アセスメントとは「状況を見立てること」

病院でも訪問看護でも、看護の出発点は「アセスメント」にあります。
アセスメントとは状況を見立てることであり、看護師が利用者の「いま」の状態を多角的にとらえ、必要な支援を考えるためのプロセスです。
単に観察するだけでなく、変化を予測し、生活の中で何が起きているかを整理する思考が求められます。
特に訪問看護では、病院のように常に観察できるわけではありません。
また、「先週どうだったか」「今週はどうか」「今後どうなるか」といった時間の流れを意識したアセスメントが必要になります。
情報共有の重要性
訪問看護では、チームで「見立て」を共有する仕組みをつくる必要があります。
なぜなら、訪問看護の契約は、個人の看護師ではなく「訪問看護ステーション」と利用者さんとの間で結ばれているからです。
担当の看護師だけが利用者さんの状況を把握しているのは望ましくありません。
チーム全体で「情報」と「考え方」を共有することが、質の高い看護の前提になります。
アセスメントツールの作成や、観察項目の標準化など、誰が訪問しても同じ質のケアが提供できる体制づくりが求められます。
誰が評価しても同じ結果が得られるように、評価基準を統一するための標準化ができるようなアセスメントプロトコールを用いることが望ましいと思われます。
標準化は画一化(個々の状況を考慮せず、すべて同じにすること)ではなく、「共通の土台の上で個別性を見出すための手段」です。
フィジカルアセスメントと生活の視点
訪問看護における身体をみることの前提には、「暮らし」を支えることがあります。
そのため身体的な情報(フィジカルアセスメント)と生活環境の両方を結びつけて考える必要があります。
入浴介助の場面で「本人が入浴できるのに、看護師が介助している」という状況は、生活機能を奪ってしまうことにもなります。
できることを見極め、自立を支える視点を持つことです。
フィジカルアセスメントでは、バイタルサインや皮膚の状態などを意図的に収集し、訪問日における「いつもと変わりない」「変化がある」を根拠をもって判断します。
この観察が、異常の早期発見やリスク予測につながります。
他にも情報収集には以下の記事も参考にしてみてください。
S情報とO情報の整理
主観と客観を区別して正確に見立てることが重要です。
アセスメントで収集する情報には、以下の2種類があります。
S情報(Subjective):利用者や家族の訴え・主観的な感覚
O情報(Objective):看護師が観察・測定した客観的データ
客観的な事実であるO情報に、利用者の言葉(S情報)を混在すると事実に基づいた正確な評価ができなくなり、不適切な看護計画につながる可能性があります。
症状を整理する際には、次の7つのポイントを意識すると効果的です。
- 発症の様子
- 進行具合
- 性状(痛みや違和感の特徴)
- 程度(強さ・頻度)
- 部位(どこに出ているか)
- 増悪・改善因子(どうすると良くなる・悪化するか)
- 随伴症状(ほかに出ている変化)
これらのポイントごとにS情報とO情報を収集します。
この整理した情報をチームで共有することで、誰が見ても同じ判断ができる体制につながります。
リスク判断とウエルネス判断

訪問看護の場面では、「悪化を防ぐ」と「より良く生きる」を両立することが大切になります。
なので、リスク(危険)を察知する力、ウエルネス(健康・幸福)を高める提案力の両方が必要です。
そのためには、以下の手順例を踏まえているかを確認します。
- 今、何が起きているかを明確化する
- すぐに介入すべきかを判断する
- 状況が悪化する危険性を予測する
- より望ましい生活への可能性を探る
また、在宅では医療者がいない「空白の時間」が存在します。
この時間を見通して、「手遅れになる前に動けるか」「異常がない状態をどう維持するか」を考えることが、訪問看護師の腕の見せどころです。
生活を支えるアセスメント
訪問看護の目的は、生命を守ることだけでなく「その人らしい生活を支えること」です。
生活機能の階層モデル(山内豊明 生命・生活の両面から捉える訪問看護アセスメント・プロトコル)では、「身体の営み」と「生活行動」は連続しているとされています。
- 「排尿をつくる」は身体の営み
- 「トイレで排泄する」は生活行動
このように、身体機能の維持と生活動作の実現は切り離せません。
生活を支えるためのアセスメントでは、次のようなニーズを意識します。
- 食事がしたい
- トイレに行きたい
- 入浴したい
- 外出したい
- よく眠りたい
- 痛みのない生活を送りたい
これらを叶えるために、身体機能だけでなく、生活環境・経済状況・意志の力を見立てることが求められます。
もっと、くわしく学びたい方はこちらの本をぜひおすすめします。
標準化と質の保証
アセスメントの質を高めるには、思考過程を可視化することが欠かせません。
看護師の経験的判断を言語化し、チーム全体で共有することで、再現性のあるケアが可能になります。
標準化なきところに個別性は生まれません。
共通の枠組みがあるからこそ、利用者一人ひとりの特性を活かしたケアが実現します。
カンファレンス時間を設けたり、経験値をチームの知に変えることにつなげていくことが、事業所の質の保証となります。
まとめ
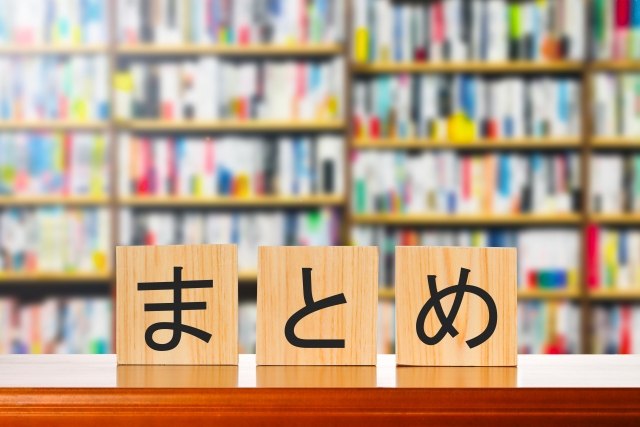
- チームで「見立て」を共有する仕組みをつくる
- 身体をみることの前提には、「暮らし」を支えることがある
- 主観と客観を区別して正確に見立てることが重要
- 「悪化を防ぐ」と「より良く生きる」を両立することが大切
- 生命を守ることだけでなく「その人らしい生活を支えること」
- 身体機能だけでなく、生活環境・経済状況・意志の力を見立てること
- アセスメントの質を高めるには、思考過程を可視化すること
訪問看護におけるアセスメントは、「生きること」を支えるための看護の原点です。
身体的変化(フィジカルアセスメント)を正確にとらえ、生活全体を見立て、チームで情報を共有すること。
それが、利用者さんの「よりよく生きる」を実現する第一歩です。
命を守りながら、生活を支える。
訪問看護師に求められるアセスメント力は、まさにその両輪を動かすエンジンです。
日々の実践に、ぜひ「見立ての視点」を取り入れてみてください。
訪問看護をおこなう中で誰もが不安や疑問に思ったりすることを解決できるような記事の作成を心がけています。
この記事がみなさんの日々の業務に役立ってもらえると幸いです。