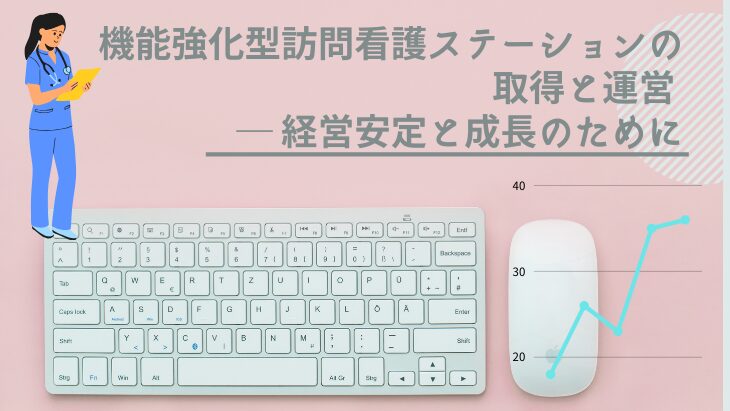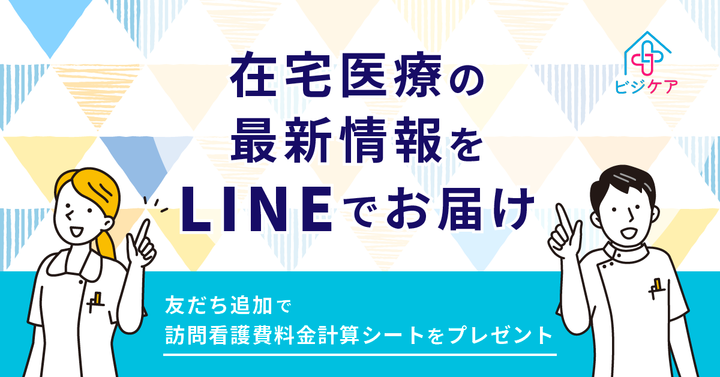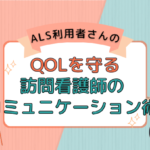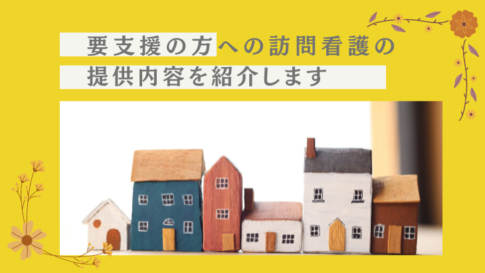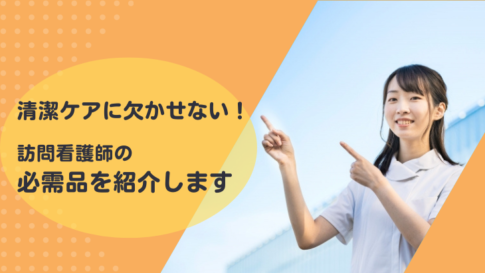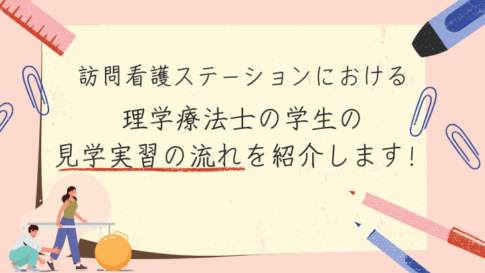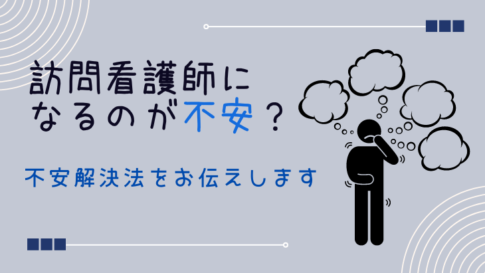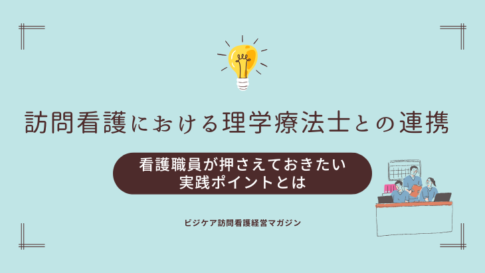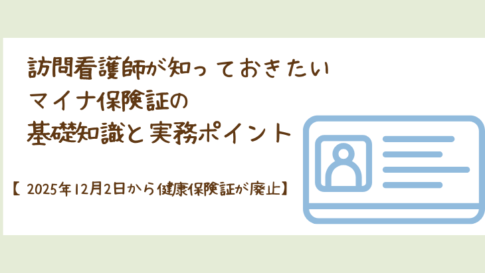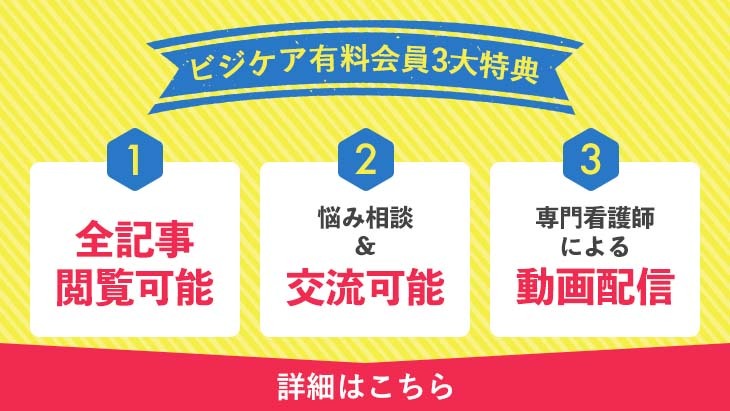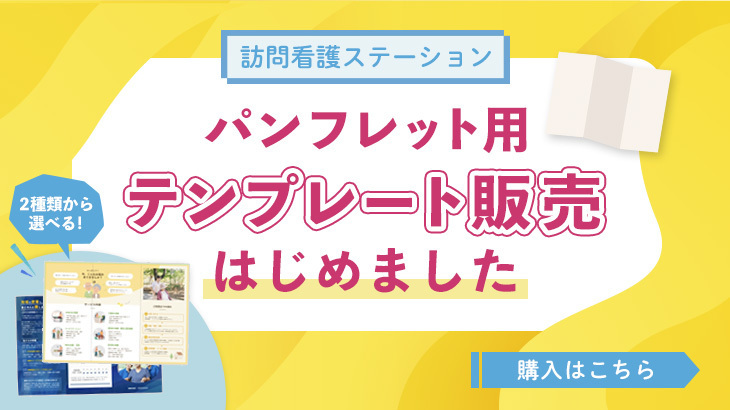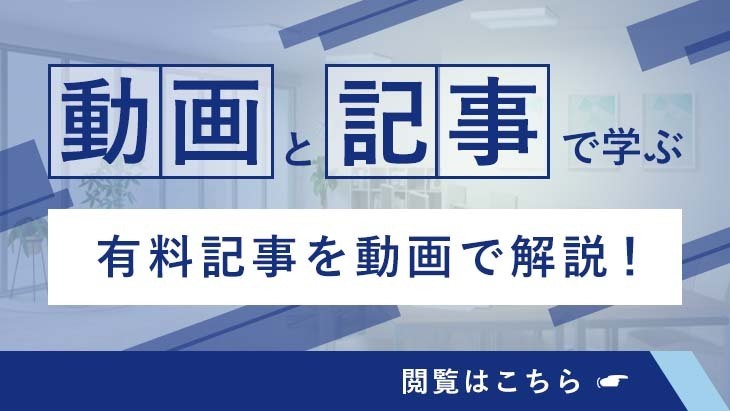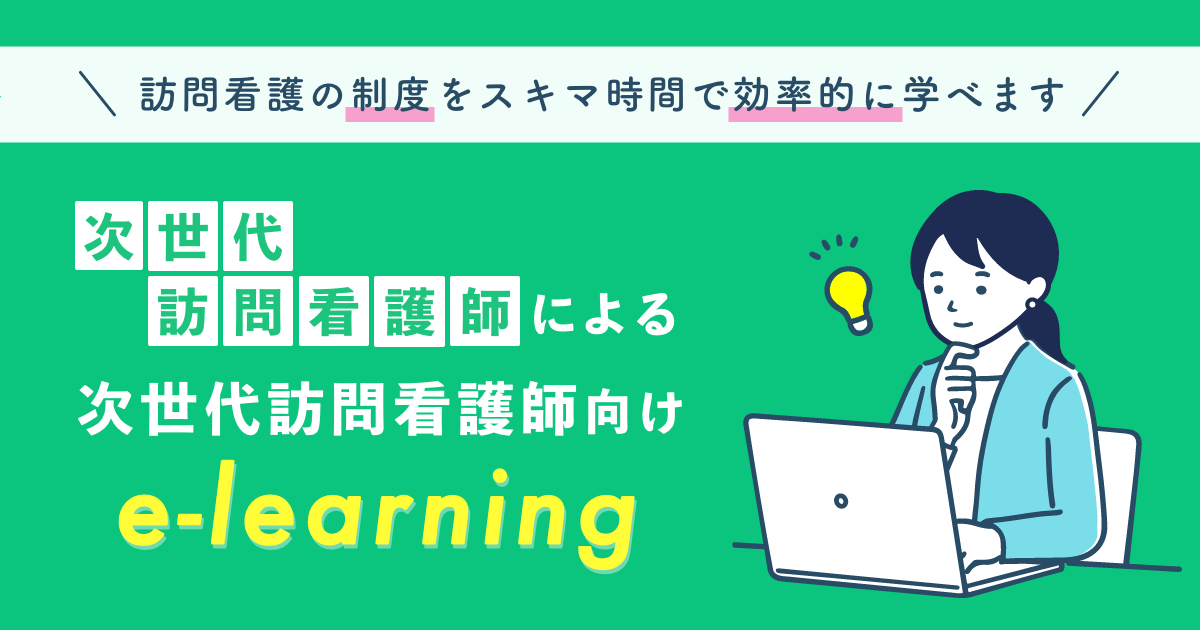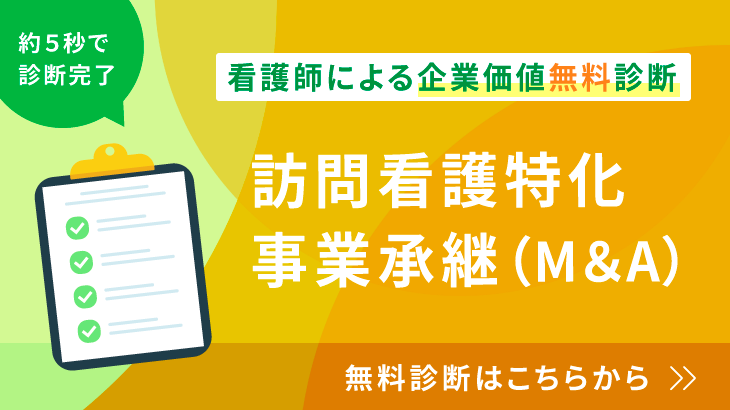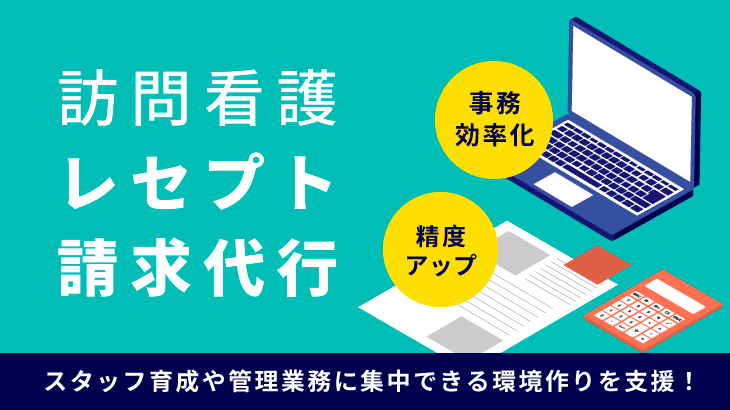訪問看護ステーションの経営者や管理者なら誰もが一度考えたことのある悩みではないでしょうか。
人件費の高騰や事業者間の競争激化により、訪問看護ステーションの経営環境は厳しさを増しています。
今後もこの流れは加速することが予測され、収益の安定と持続的な成長には「他のステーションと差別化できる強み」が不可欠です。
その一つの選択肢が「機能強化型訪問看護ステーション」への移行です。
本記事では、機能強化型訪問看護ステーションの概要、取得要件、運営上の課題とメリットについて整理し、経営者・管理者が検討すべきポイントを解説します。
目次
機能強化型訪問看護ステーションとは?

「機能強化型訪問看護ステーション」とは、重症度の高い利用者や急変リスクを抱える方に対し、より専門的で質の高い在宅医療を提供するために機能を強化した事業所です。
常勤看護師の配置数や24時間対応体制など、国が定めた要件を満たすことで機能強化型訪問看護療養費(1・2・3)を算定でき、通常より高い診療報酬を得ることができます。
以下の記事も参照してください。
なぜ機能強化型を目指すのか?
- 訪問単価を上げて経営を安定化
- 地域における信頼の向上
訪問単価を上げて経営を安定化
訪問看護ステーションの収益改善には「訪問単価の引き上げ」が最も有効です。
訪問件数の無理な増加や過度なコスト削減は、スタッフの負担を増やし、サービスの質を下げるリスクがあります。
その点、機能強化型を取得すれば加算を算定できるため、訪問単価が上がり少ない件数でも安定した売上を確保できます。
地域における信頼の向上
機能強化型訪問看護ステーションは、病院やケアマネジャーから「安心して任せられる事業所」として認知されやすく、紹介件数の増加につながります。
さらに算定要件である「地域の勉強会や研修の開催」を通じて、地域医療全体の質向上にも寄与できます。
機能強化型訪問看護ステーションの取得要件
- 常勤看護師の一定数以上の配置
- 24時間対応体制(夜間・休日含む)
- 重症者・ターミナル・小児の受け入れ実績
- 主治医との連携(計画書・報告書の提出)
- 安全にサービスを提供できる管理体制
- 地域への研修や情報提供などの貢献
これらの要件を満たせば、機能強化型訪問看護療養費を算定でき、経営の安定に直結します。
以下の記事でもさらに詳しく解説しています。
導入における課題と解決策
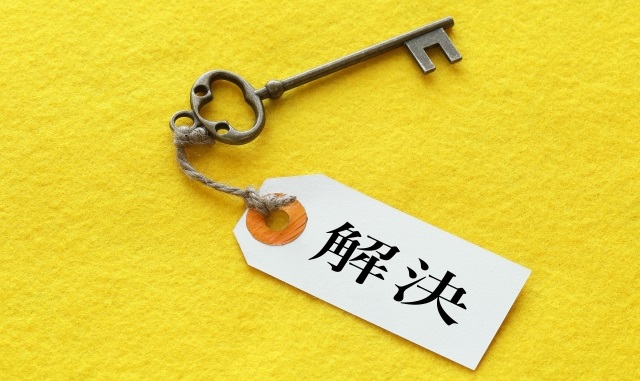
一方で、機能強化型取得にはいくつかの課題があります。
- 複雑で厳しい要件:特に中小規模の事業所にとっては人員配置や体制整備の負担が大きい
- 人材確保の難しさ:専門性の高い人材は慢性的に不足しており、採用・育成・定着が課題
- 夜間・休日対応の負担:オンコール負担やシフト管理の工夫が不可欠
- 地域連携の構築:病院・施設・行政との関係づくりには時間と労力がかかる
こうした課題にどう対応するかが、成功の鍵となります。
人材確保の難しさ
機能強化型の要件を満たすためには、看護職員の常勤配置や割合、専門性の確保が前提となっていますので、採用の段階から明確な選考基準と人材要件を定めておく必要があります。
中でも専門性の高い人材は慢性的に不足しています。
機能強化型1の算定には専門の研修を受けた看護師の配置は要件となっています。
採用と同時に、育成の考え方としてスキル向上と定着率を両立させる工夫が重要です。
専門の研修を受けやすい外部研修参加支援や働きやすい職場環境の整備が必要です。
夜間・休日対応の負担
24時間対応体制の確保は、機能強化型の届出要件の中でも中心的な項目です。
オンコール体制はスタッフへの負担が大きいため、ICTを活用した情報共有や看護師のシフト計画(無理のないローテーションを設計する)やオンコール業務の負担分散の工夫が求められます。
緊急対応マニュアル・研修の徹底をおこない、スタッフが安心して対応できる仕組みづくりが必要です。
また、オンコール対応中の看護師がタブレット端末から利用者情報を即時に確認できれば、判断や報告の精度が向上します。
これらの仕組みは、運営全体の見える化にも貢献できます。
地域連携の構築
地域の認知と信頼獲得は、経営を継続するためにも重要です。
地域医療機関や行政との連携強化を行う必要があります。
勉強会や情報交換の場を設け、信頼関係を築くためには、時間と関係構築が欠かせません。
また、居宅支援事業所を同一法人で運営することで紹介ルートが安定し、連携強化につながります。
これらを段階的に進めることで、要件を満たしつつ持続可能な運営を実現できます。
届出・運営における実務ポイント
実際に届出を行う際には、次の点を押さえておくとスムーズです。
- 内部チェックリストの活用:要件の充足状況、必要書類の有無を整理
- スケジュール管理:提出期限から逆算し、法人内の部署へリマインド
- 記録・証拠の明文化:研修実績、地域連携の記録、利用者の要件該当状況を数値化
- 継続的な進捗管理:月次で重症者・ターミナル件数や情報提供実績を確認
- リスク対応計画:要件から外れないように代替策を事前に対策していく
さらに、地方厚生局による実地確認や資料提出に備えて、帳票・記録類を電子化して保管しておくことも重要です。
毎年8月1日現在の加算等の届出状況について地方厚生局への報告することになっています。
加算取得後もこれらの運営における実務のポイントを参考に管理し、要件を満たせなくなって取り下げすることにならないようにしましよう。
機能強化型取得によるメリット
課題を乗り越えて機能強化型を取得した場合、得られるメリットは多岐にわたります。
- 診療報酬の増加による経営安定
- 地域での認知・信頼の向上
- 紹介件数の増加(病院・ケアマネからの依頼が増える)
- 職員のモチベーション・定着率向上(専門性を高める研修制度や待遇改善につながる)
- 人材採用力の強化(働きやすく、やりがいのある職場として魅力が増す)
このように、機能強化型への移行は「経営」と「サービス品質」の両面でプラスに作用します。
中でも機能強化型3は「1」や「2」への通過点としてではなく、地域に根ざした訪問看護の質を高めるという目的をもった戦略的な選択肢として位置づけることです。
「1」と「2」とは違い、精神科重症患者(GAF尺度による判定が40以下など)と別表8の利用者、複数の訪問看護ステーションで共同して提供する利用者の受け入れも重症度の高い利用者としてカウントできるのが特徴です。
小規模ステーションが、機能強化型を目指す際の重要な選択肢と考えてみることをおすすめします。
まとめ

機能強化型訪問看護ステーションへの移行は、単なる加算取得ではなく、経営の安定と地域での信頼を両立させる戦略的な選択です。
届出要件を満たすための準備は大変ですが、その先には収益基盤の強化・紹介ルートの確立・人材定着といった大きなメリットが待っています。
管理者にとって「機能強化型を目指すべきかどうか」は避けて通れないテーマです。
単なる加算のためではなく、地域に根ざした訪問看護の質を高め、在宅療養の選択肢を増やすための戦略的選択肢として位置づけることが重要です。
ステーションの安定した運営が、最終的には利用者へのより良いケアの提供につながります。
機能強化型の取得に向けて、現場と管理者が一体となり、地域に信頼される訪問看護ステーションを目指していきましょう。
ビジケアには、機能強化型算定など「訪問看護経営の課題解決の支援」を行う訪問看護経営サポートというサービスがあります。
興味のある方はぜひチェックしてみてください。
\詳細はコチラ!/
訪問看護をおこなう中で誰もが不安や疑問に思ったりすることを解決できるような記事の作成を心がけています。
この記事がみなさんの日々の業務に役立ってもらえると幸いです。