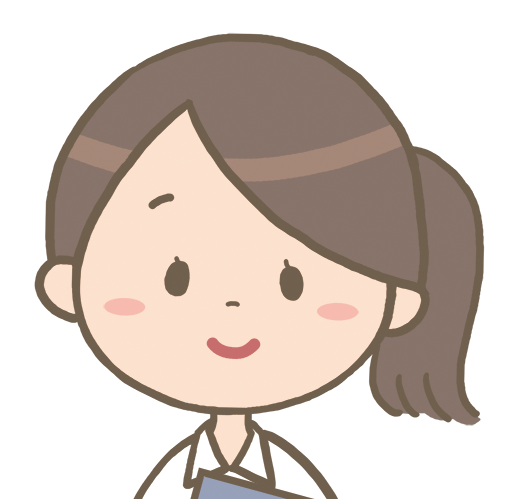
このような悩みにお答えします。
訪問看護を始めたばかりで緊急対応の経験がほとんどなく、「自分が対応する場合どうしたらいいのだろう……」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、筆者が実際に対応した事例をもとに訪問看護の緊急対応について解説します。
- 緊急対応の事例には何があるか知りたい
- 先輩看護師の経験を参考に、適切な対応がとれるようになりたい
このような訪問看護師にとって役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
訪問看護の緊急対応を事例別に紹介

私が実際に経験した訪問看護の緊急対応の事例は、次の通りです。
- 転倒
- 点滴・カテーテル類のトラブル
- 疼痛
- 脳卒中
- ターミナルケアやエンゼルケア
- 発熱
- 精神科訪問看護
- 医療機器のトラブル
それぞれについて解説していきます。
転倒

緊急対応として、転倒に関する相談がもっとも多いと感じています。
実際に私が経験した事例では、転倒を繰り返す老々介護のご家庭に夜間帯に訪問し、状態を確認したことがあります。
また、朝方に家族から「腰を強く打って動けない」との電話が入ったこともありました。
このときは骨折の可能性が高いと判断し、訪問せずに電話越しで救急搬送を依頼したこともありました。
一方で、以下の条件がすべて揃っている場合には、緊急訪問が不要となるケースもあります。
- 本人に意識がある
- 頭を強く打っていない
- 疼痛がない
- 家族と同居している
このような場合には家族に協力を依頼し、ベッドまで運んでもらい経過を観察するように伝えることが一般的ですね。
しかしここ数年は、独居や老々介護のケースが増え、これらの条件が揃わないことがほとんどです。
そのため、看護師が訪問して状態確認をおこなう必要性が高まっていると感じます。
事業所によっては電話で無事を確認し、翌日に対応を回す場合もありますが、条件が揃わない場合は看護師が訪問することが重要だと考えています。
点滴・カテーテル類のトラブル
医療依存度の高い利用者さんを多く受け入れている事業所では、点滴やカテーテルに関するトラブルの相談が多くあります。
実際に私自身も、これまで以下のトラブルに対応してきました。
- 点滴(静脈・皮下、CVポート、ポンプ等)
- カテーテル(膀胱留置カテーテル、経管栄養等)
これらの閉塞や漏れ、事故(または自己)抜去といった問題への緊急対応です。
また、イレウスチューブを挿入したまま在宅に戻られた方の管理をおこなった経験もあります。
こうしたケースでは、利用者さんだけでなくご家族も強い不安を抱えることがあり、日々のケアの大切さを実感しました。
点滴・カテーテルに関するトラブルは、電話越しでの解決が難しい場合も多いため、看護師による緊急対応が不可欠です。
自分が慌てないためにも、トラブル発生時の対応方法や手順を事前に確認し、医療機関との連携を密にしておきましょう。
疼痛

疼痛に関する相談も非常に多いです。
私がこれまでに経験した事例のひとつに、腹痛を訴える方への対応がありました。
電話で「胃のあたりが痛い」と訴えがあったため、自宅にある胃薬を内服して経過を観察してもらいました。
しかし痛みがまったくおさまらず、さらに強くなったため緊急訪問したのです。
訪問時、バイタルサインに異常はなく、腹痛を訴えるような既往歴もありませんでした。
痛みは臥位よりも座位の方が楽とのこと。
この方は脳出血の後遺症で言語障害があり、具体的な痛みの度合いを説明することが難しい方でした。
触診にて単なる胃痛ではないと判断し、独居であることも考慮して救急搬送を手配。
その後、胆石が原因の膵炎との診断を受けました。
このように、痛みの訴えは程度や表現が人によって大きく異なります。
特に高齢者や認知機能が低下している方の場合、訴えに一貫性がないこともしばしばです。
疼痛は頭痛、腹痛、腰痛、四肢の痛み、がん性疼痛など多岐にわたるため、緊急性の有無の判断が重要です。
慢性的な痛みや、原因が明らかである痛みの場合は、緊急性が低いと考えられます。
また多くの場合、鎮痛剤が処方されているため、内服し経過を観察してもらうことが一般的です。
しかし上記以外の緊急性が高い可能性のある場合は、以下を電話で確認しておきましょう。
- 痛みの種類
- 程度
- 発生時期
緊急性の有無を判断するためには、疼痛の原因に関する知識をもっておくことが重要です。
必要なときに、確実に知識を引き出せる準備をしておきましょう。
脳卒中

脳卒中に関する緊急対応も多いですね。
家族から「いつもと反応が違う」「おかしい」「手が動かない」といった内容で緊急訪問を依頼されることがあります。
訪問すると明らかに顔面の麻痺が確認され、その後すぐに救急搬送を要請しました。
また、いつものように訪問したところ、倒れていたり麻痺が出ていたりといったケースも少なくありません。
私自身も、いつも訪問すると声が聞こえるのに、その日は反応がなく床に倒れていた事例がありました。
幸い意識はあったため、すぐに救急搬送となりました。
脳卒中のなかでも特に脳梗塞の場合は、発症から早ければ早いほど後遺症のリスクを減らせます。
緊急時にはすぐ対応できるように、普段と異なる変化を見落とさないように心がけましょう。
ターミナルケアやエンゼルケア
訪問看護におけるターミナルケア、特にがん末期の対応は、必須の業務といっても過言ではありません。
終末期には死への恐怖やがん性疼痛など、心身ともに細やかなケアが必要となり、オンコールの回数も多くなります。
疼痛が強い方、肺がんで呼吸苦がある方、最期が近い方など、すべての事例で電話があれば緊急対応をおこないました。
自分の無力さを痛感しましたが、ただ訪問するだけでも利用者さんやご家族はとても安心してくれます。
内服薬だけでは解決できない苦痛も多く、少しでも軽減するために私たち看護師がいると感じています。
ある利用者さんの家族から「反応が薄くなり呼吸の間隔が長くなった」という連絡を受け、その日の夜は1時間おきに電話がありました。
呼吸が停止したとの連絡を受け、すぐに医師へ連絡し、私も訪問してエンゼルケアをおこないました。
在宅でのエンゼルケアは病棟でおこなう場合とは異なり、家族にも参加してもらい、最後のお別れの時間を大切にできる貴重な機会です。
全員がしっかり対応できるように準備しておくことをおすすめします。
経験が浅い訪問看護師にとっては不安も多いかもしれませんが、ご本人やご家族の不安はその何倍、何十倍も大きいです。
冷静さを保ち、適切に対応できるように訓練しておきましょう。
発熱
緊急対応時は、まず解熱剤を内服してもらいます。
薬がない場合はクーリング対応にて経過観察をすることが一般的です。
そのほかに気になる症状がない場合、フォローの電話を入れ、医師へ繋ぎます。
発熱の場合は看護師が訪問するよりも、早めに医師の往診に繋げるのが望ましいです。
精神科訪問看護
利用者さんの依存が強くなることを懸念し、緊急対応の判断を慎重におこなっています。
精神科の訪問看護の場合、24時間契約をとっている事業所は少ないと思われるため、利用者さんには自身で考えて行動できることを重点目標としてケアすることが大切です。
不安になった際の対処法を一緒に考えていきましょう。
ただし、精神的な問題ではなく身体的に緊急性が高い場合もありますので、見極めも重要です。
医療機器のトラブル

医療機器のトラブルに関する緊急対応の経験はありませんが、一般的に起こり得る話としてお伝えします。
人工呼吸器や在宅酸素を使用している場合、アラームなどで電話がかかってくることがあります。
しかし、こういった医療機器のトラブルは生命に直結するため、緊急対応は極力避けるべきです。
事前にチェックリストや緊急時の対応マニュアルを作成し、災害用電源の確保や家族への指導をしておきましょう。
医療機器メーカーとの連携を密にし、万が一のトラブル時にはすぐに対応してもらえる体制を整えておくことも大切です。
以前在宅で、高濃度の酸素投与をおこなっていた方がネーザルハイフローを使用していました。
私はこの機器の取り扱いに不安を感じていたため、メーカーに何度か電話で問い合わせをしたり、機器の勉強会を依頼したりして対応しました。
あせらずに緊急対応をとれるようになろう!
今回は筆者が実際に対応した事例をもとに、訪問看護における緊急対応について解説しました。
在宅での緊急対応では、看護師自身が判断し、解決しなくてはならないことが多くあります。
そのため日頃からしっかりと準備をし、連携機関との連絡を密にとっておきましょう。
最初は誰でも不安を感じるものですが、実際に経験しなければ得られないこともあります。
本記事を参考に、あせらずに緊急時の対応をとれるようになってもらえれば幸いです。
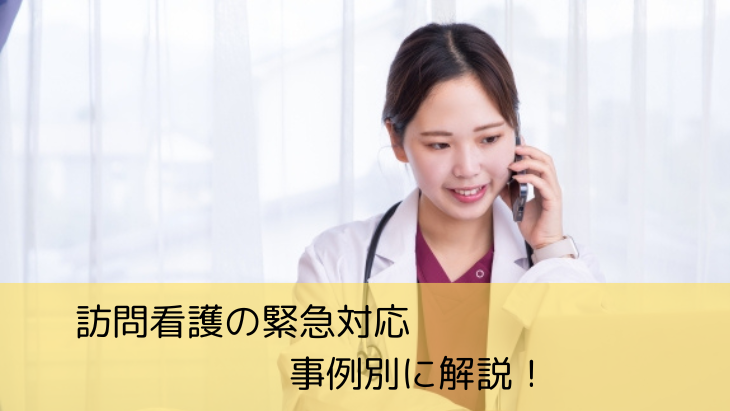

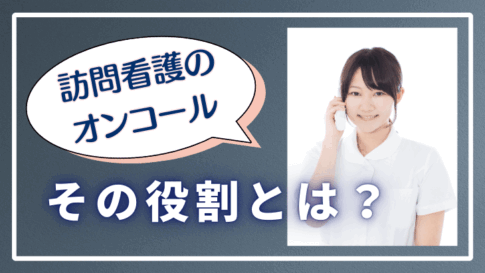
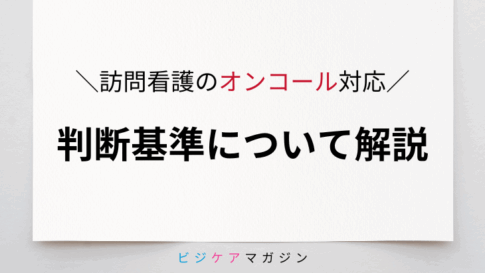

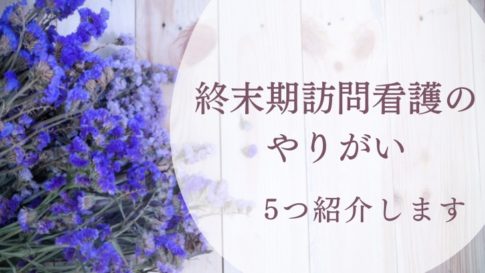
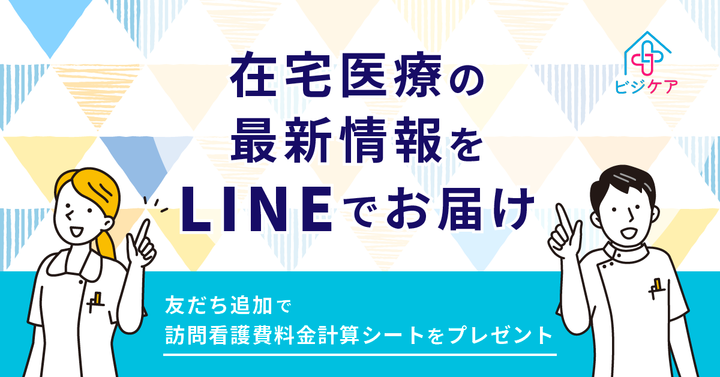
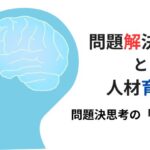
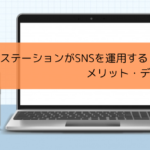
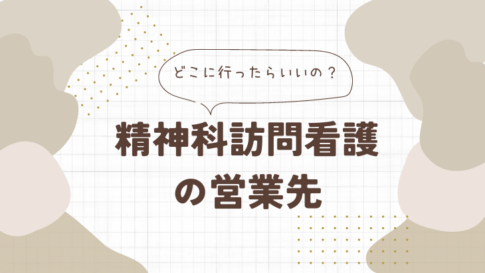

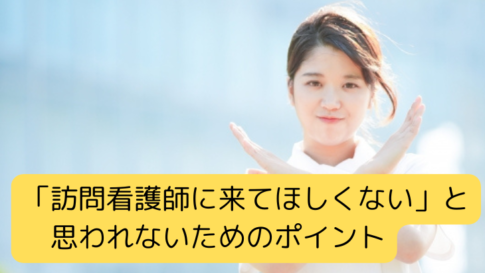
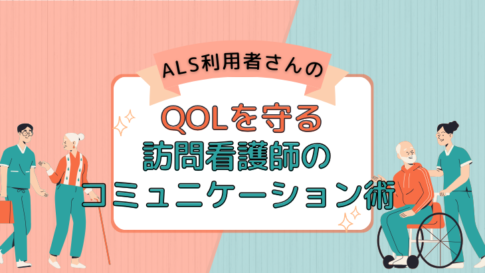




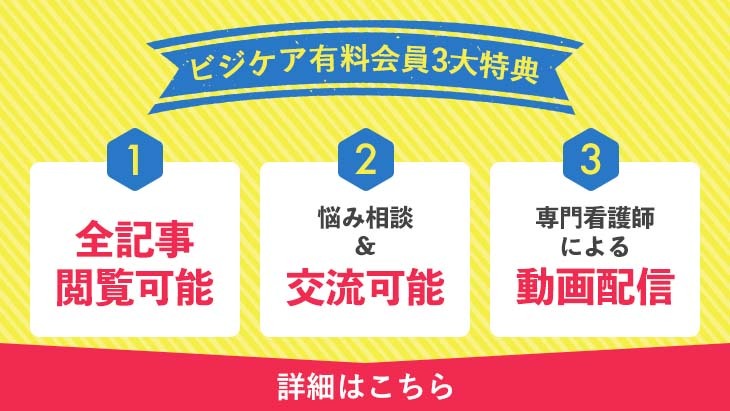

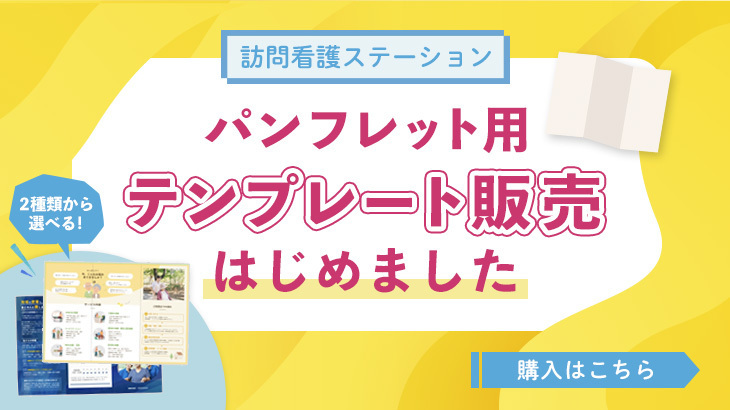
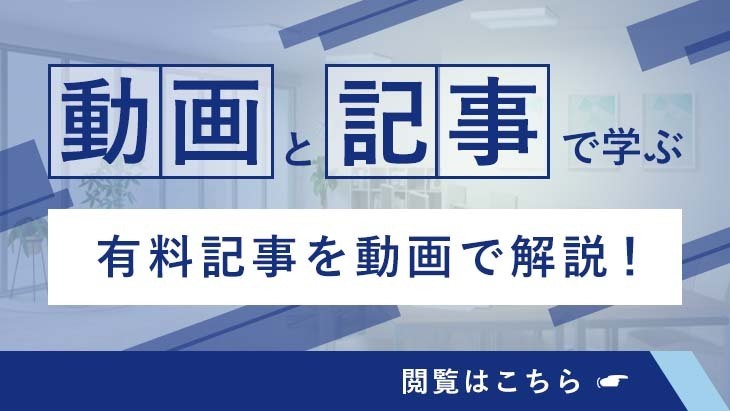
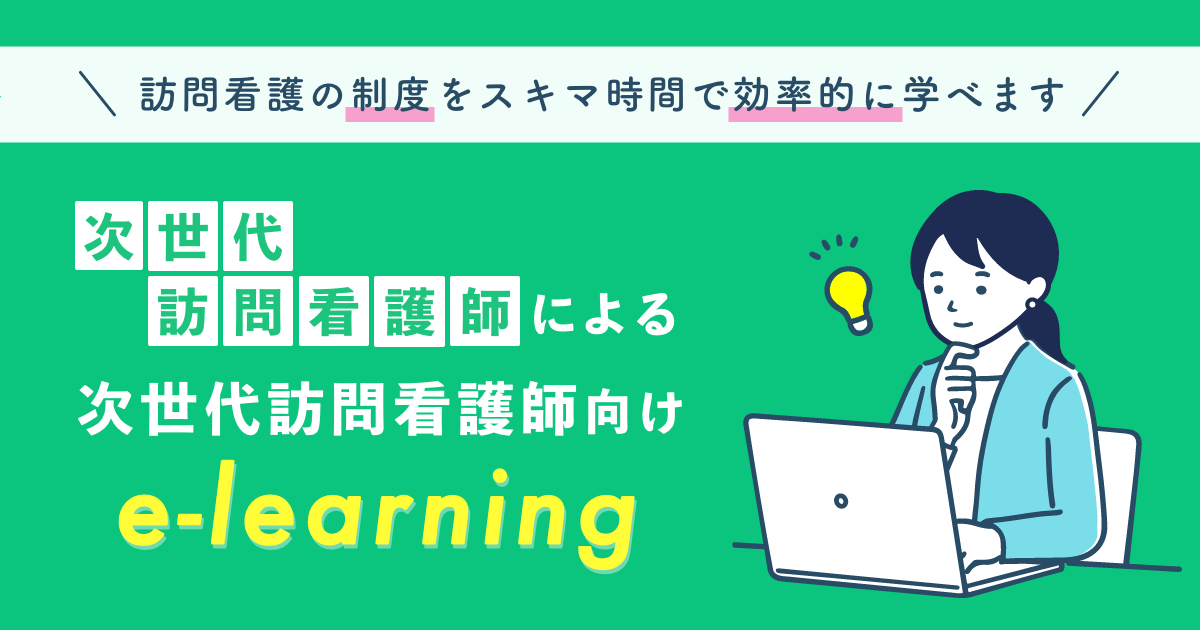
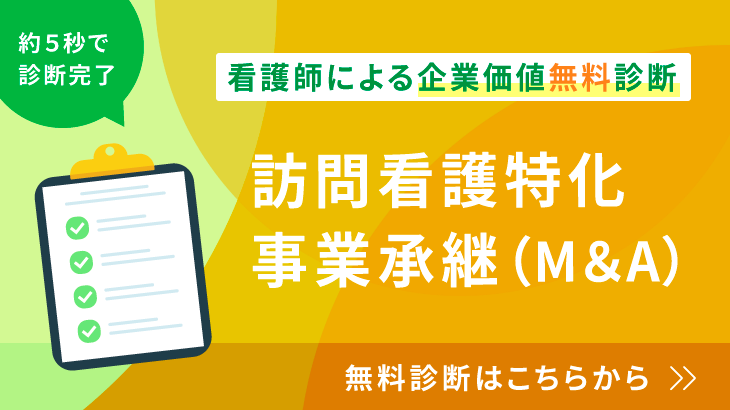
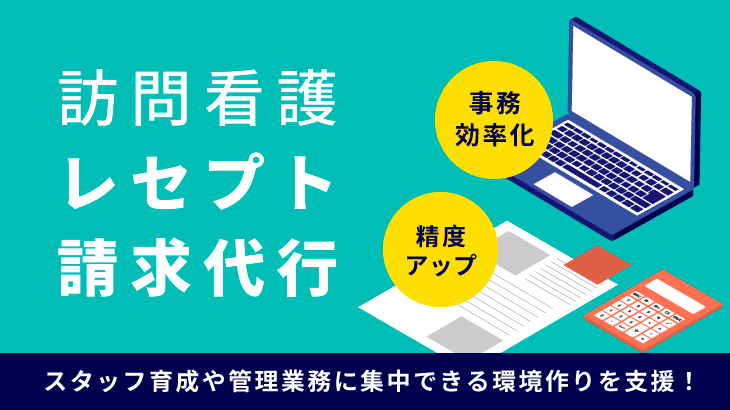

訪問看護の緊急対応にはどのようなものがありますか?事例別に教えてもらい、自分にもできる対策をとりたいです。