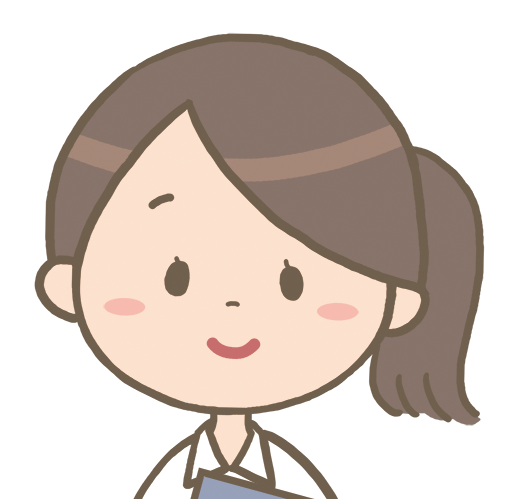
このように思ったことはありませんか?
精神科訪問看護では、病院とは違い自分一人で利用者さん宅へ伺うことが多いです。
そのような中で、支援者として信頼され、受け入れていただけるよう、より良いコミュニケーションをとっていく必要があります。
今回は実際働いている経験から、精神科訪問看護におけるコミュニケーションのコツ5選を紹介させていただきます。
精神科訪問看護のコミュニケーションに悩んだり不安を抱えている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ではさっそく解説します。
目次
精神科訪問看護におけるコミュニケーションのコツ5選

精神科訪問看護におけるコミュニケーションの主なコツは以下の5つです。
- 妄想は否定しない
- 向かい合っては座らない
- 支援者自ら心を開く
- 言葉遣いや接遇マナーを守る
- 精神症状が悪化する兆候(サイン)を見つける
順番に解説します。
1.妄想は否定しない
精神科訪問看護の利用者さんの疾患は、統合失調症、鬱や双極性障害、パニック障害、覚醒剤やアルコール依存症など様々あります。
症状として妄想が表れて日常生活に支障をきたしてしまう事もあります。
ある利用者さんは、「自分の隣にいつも綾瀬はるかがいる。話しかけると返事が返ってくるんや」とおっしゃっていました。
とても真剣な表情で、真面目におっしゃります。
ご本人の中には本当に存在しているのです。
それを支援者が「綾瀬はるかなんて隣にいないですよ」などと言ってしまうと、利用者さんとしては「自分の言っていることを否定された!」と感じ、不信感を抱いてしまう可能性があります。
本人の言っていることは否定せず、なぜそのような妄想が出現しているのかを考えることが大切です。
2.向かい合っては座らない
訪問中、向かい合っては座らないことも精神科訪問看護におけるコミュニケーションのコツのひとつです。
向かい合って座ると、お互い妙な緊張感が生まれることが多いためです。
以前、向かい合って座っていたこともありましたが、利用者さんが緊張して話しずらそうにされていると感じました。
精神科訪問看護では、利用者さんが在宅で生活する中で抱える不安や問題などをサポートするのも重要な役割なので、相手が身構えてしまうとうまく援助ができなくなります。
部屋が狭い等、どうしても向き合って座らないといけない状況でなければ、正面には座らないようにするとよいです。
3.支援者自ら心を開く
精神科訪問看護のコミュニケーションにおいて、支援者自ら心を開くことは非常に大切です。
支援者の緊張や警戒心は、利用者さんに伝わってしまうからです。
毎日いろいろな方のもとへ訪問させていただいていると、支援者に全く心を開かず、警戒し、受け入れていただけない利用者さんも中にはいらっしゃいます。
そのような利用者さんの訪問は、どうしてもこちらも身構えて緊張感が出てしまいます。
しかし、こちらが身構えていることに利用者さんは気づきます。
余計に受け入れていただけないという悪循環が生まれます。
ノンバーバルコミュニケーション(非言語的コミュニケーション)は非常に重要です。
言語以外で行うコミュニケーションのこと。
- 表情
- 声の調子
- 香り
- 身だしなみ
- 姿勢 など
まずは「オープンマインド」。
自分から心を開くことがとても大切です。
そのように意識したところ、 利用者さんの方も徐々に警戒を解き、色々と話してくれるようになりました。
4.言葉遣いや接遇マナーは守る
精神科訪問看護において、言葉遣いやマナーはとても重要です。
「病院の患者さんに対しても言葉遣いは大切では?」
そのように感じる方もいらっしゃると思いますが、訪問看護は病院と違い、看護師の方がご自宅で生活している利用者さん宅に伺うため、相手のテリトリーに足を踏み入れることになります。
自分のテリトリーに他人が上がってくるわけなので、非常に警戒する方もおられます。
また、精神科訪問看護では年配の利用者さんも多いです。
そのような理由から、病院で働いている時以上に言葉遣いや接遇マナーには留意する必要があります。
自宅に置いてある物などを移動するときも、不用意に移動させるのは避けたほうがよいです。
ご本人のこだわりがある可能性があるからです。
さまざまな事に対し、まずは利用者さんに確認をとってから行動します。
そうする事で相手も支援者を不快に感じる事なく受け入れてくださり、コミュニケーションも取りやすくなります。
5.精神症状が悪化する兆候(サイン)を見つける
これは慣れていなければ少し難しいかもしれません。
精神科訪問看護の訪問時間は30分〜90分と決められており、限られた時間の中で、利用者さんの現在の精神症状を把握する必要があります。
利用者さん宅に訪問した際、夜間寝れず、早口で落ち着きがない方がいらっしゃいました。
その時は「原因はなんだろう?」と考えました 。
関わりを続ける中で、精神症状が不安定であるときはいつも実母と会っている次の日だと気づきました。
話を聞き、実母との関係性が非常に悪かったと知りました。
精神症状が悪化する兆候を知ることができれば、どのようにすれば、その状況を抜け出すことができるのかを考えやすくなります。
精神科訪問看護のコミュニケーションのコツを踏まえて訪問に臨もう!

今回は、精神科訪問看護のコミュニケーションのコツ5選を紹介させていただきました。
精神疾患は本当に人それぞれあり、その人その人に合った対応が大切です。
一概にその対応が正しいというのは大変難しいと思います。
正解がない分、利用者さんにとって何がよい援助となるのか、試行錯誤しながら関わっていけるやりがいもあります。
今回紹介した内容が少しでも参考になれば幸いです。
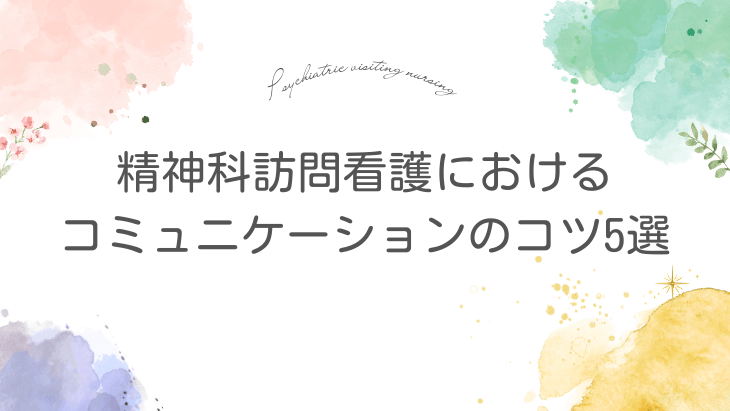

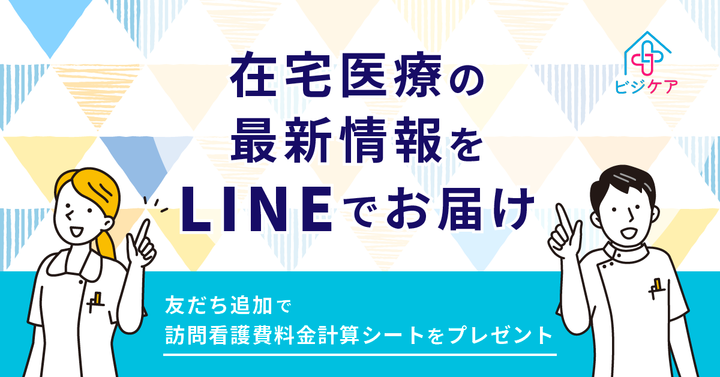
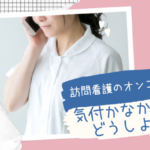


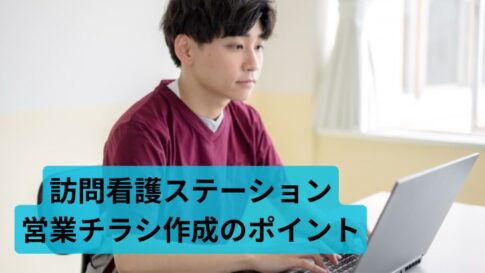


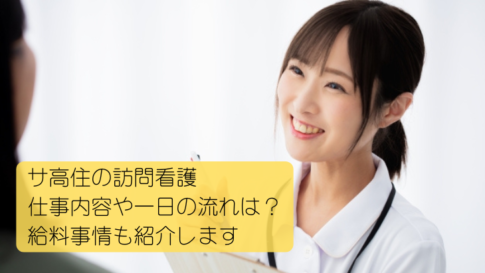
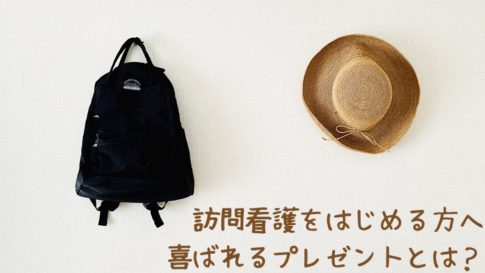


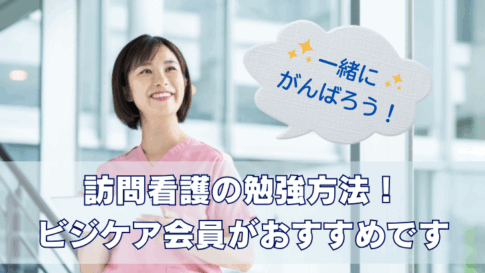



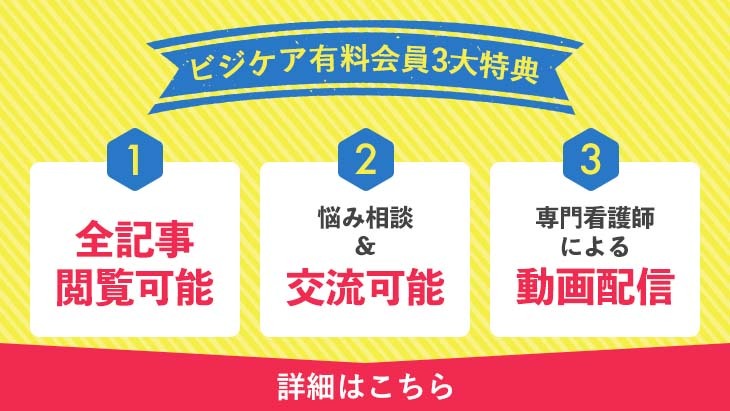

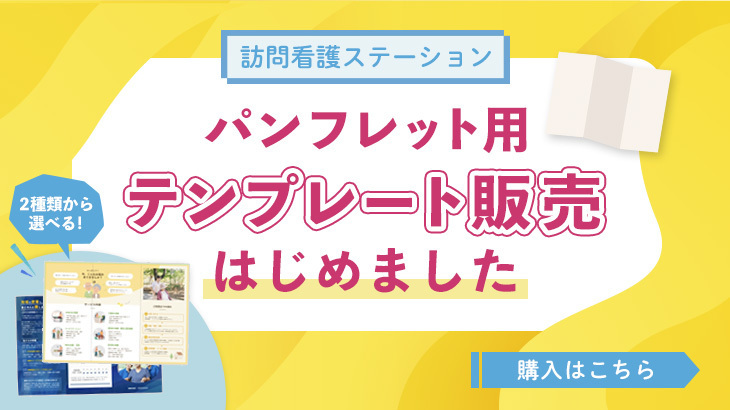
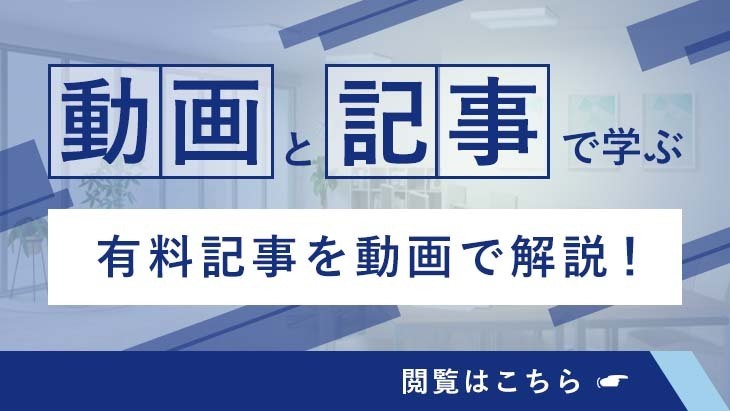
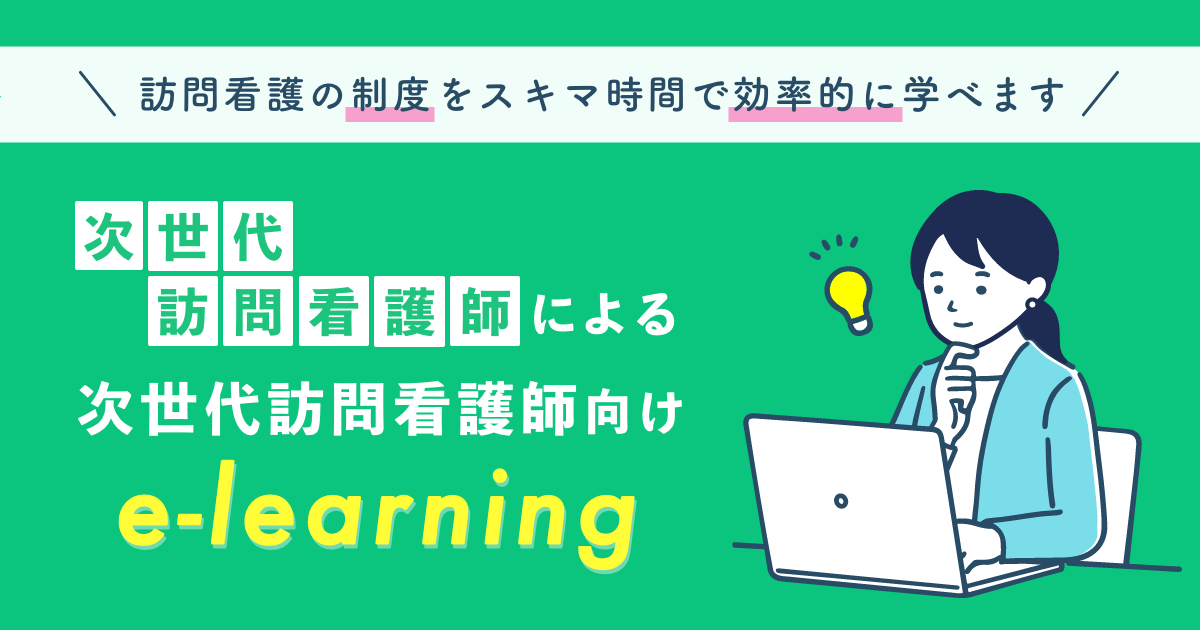
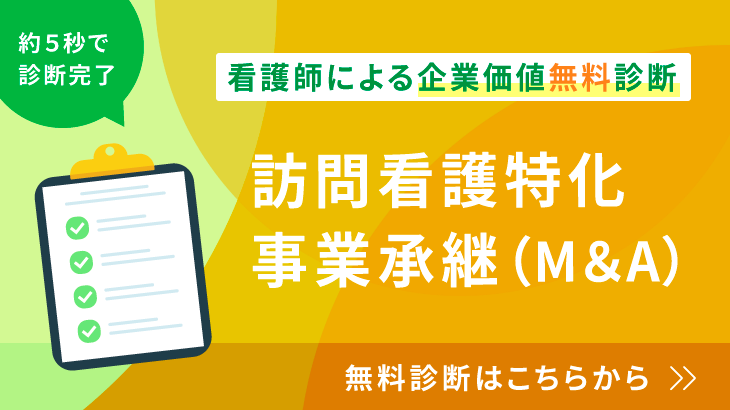
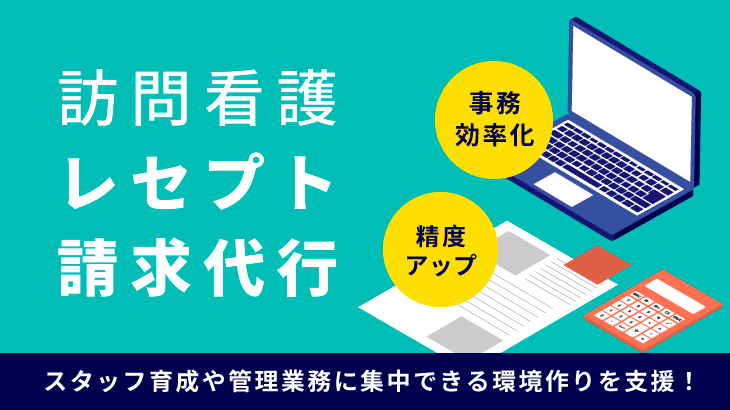

精神科訪問看護に興味があるけど、コミュニケーションの取り方ってなんか難しそうだなぁ。