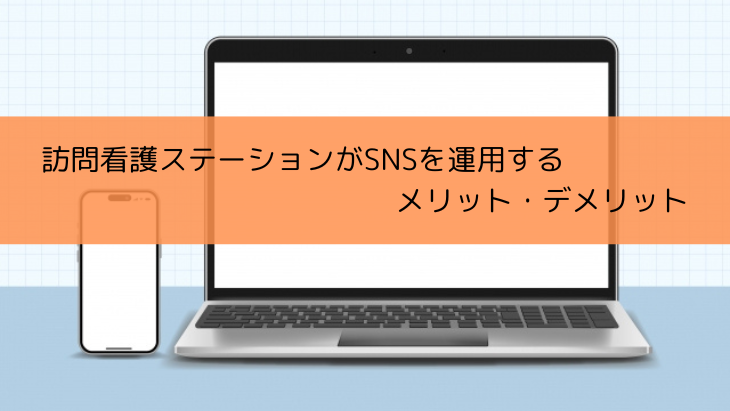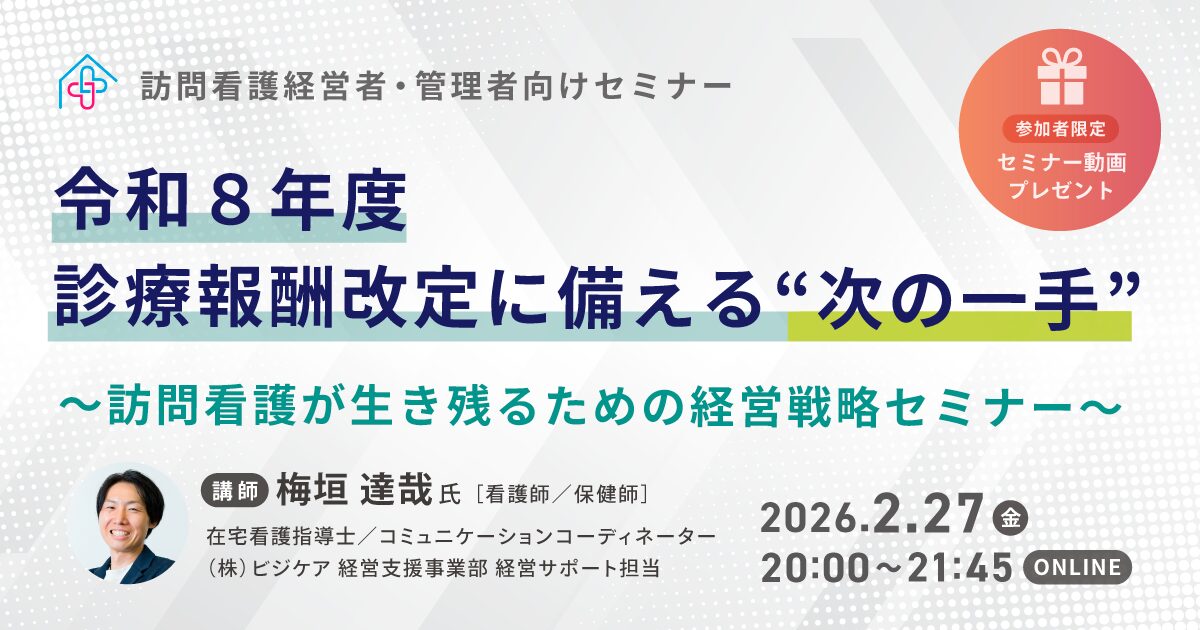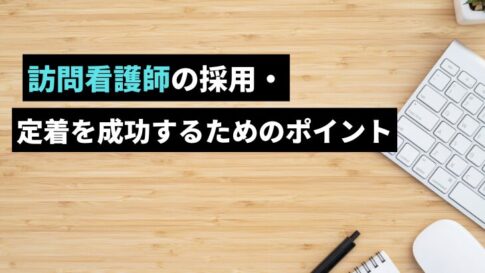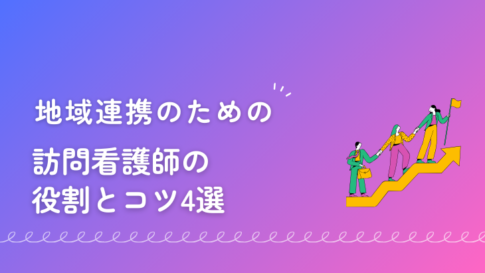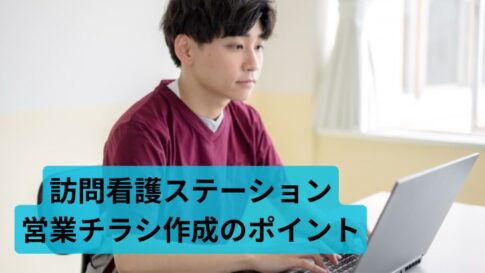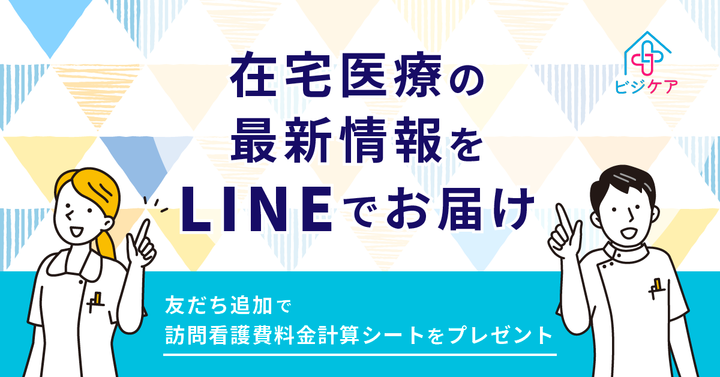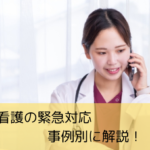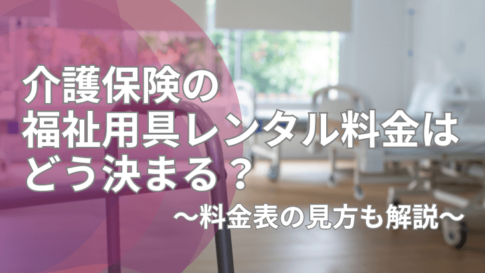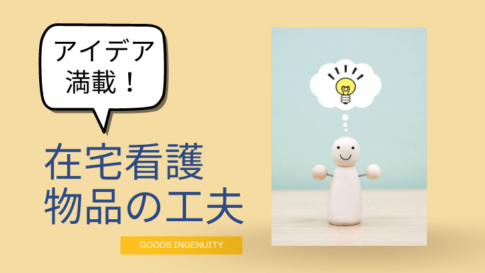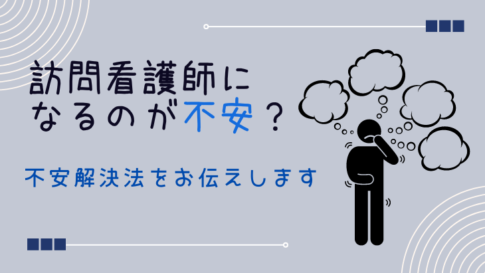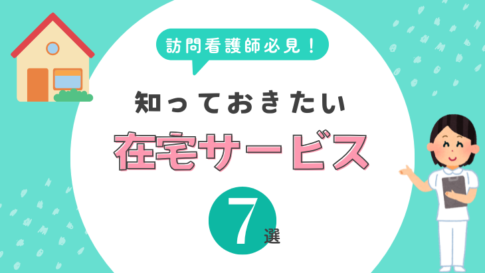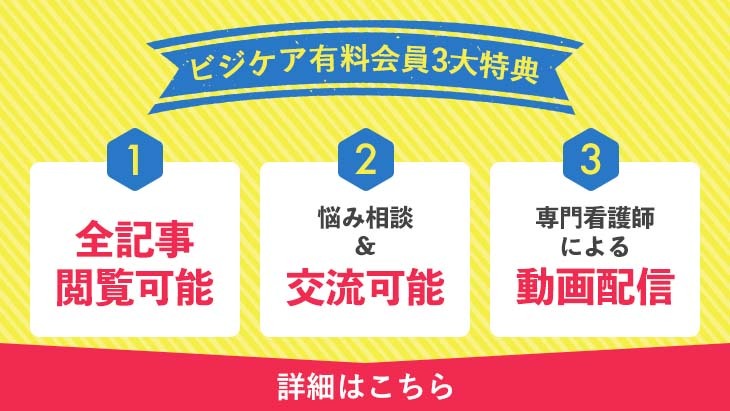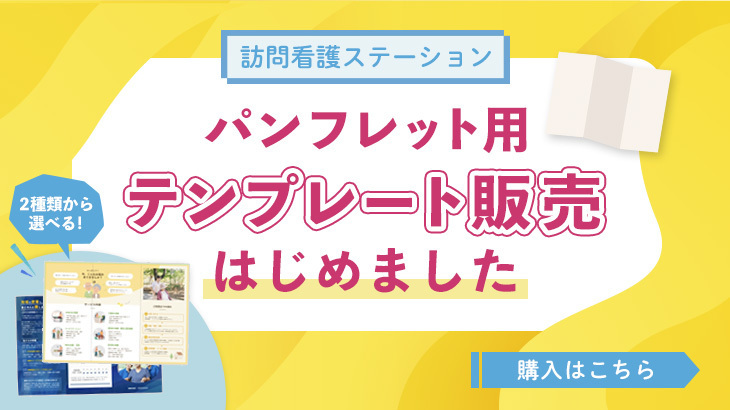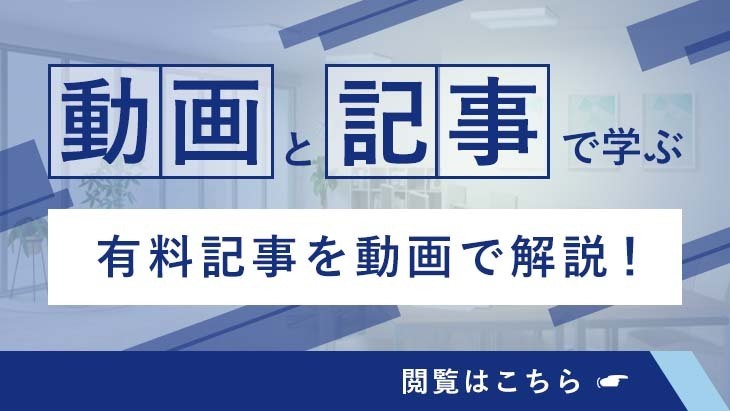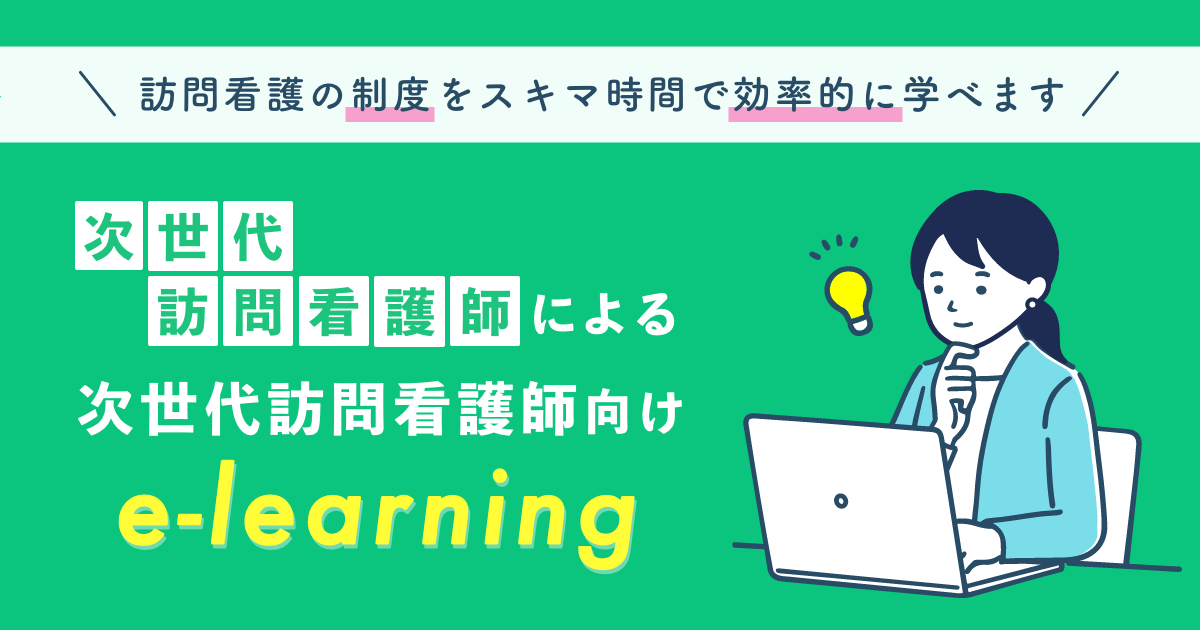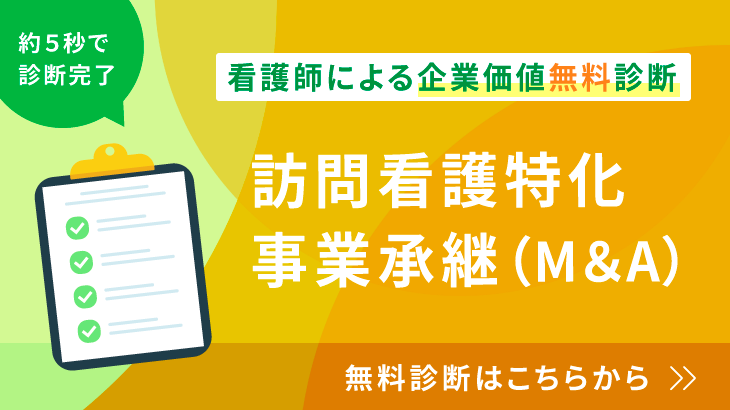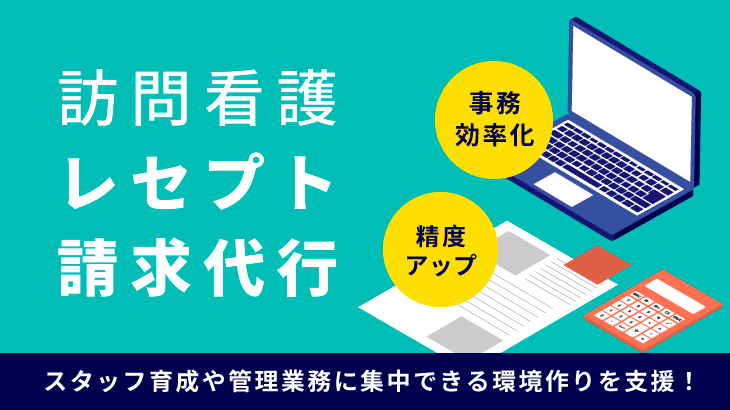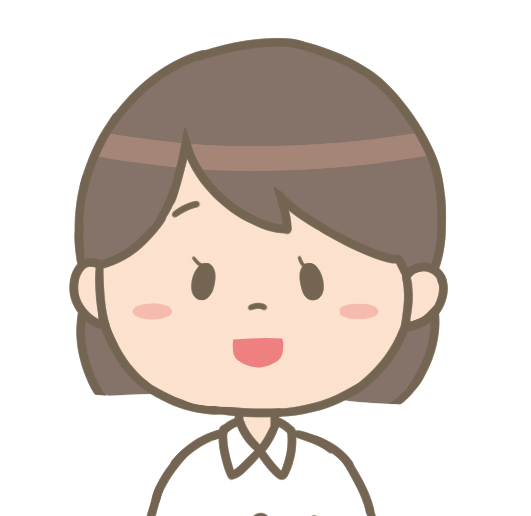
このような悩みにお答えします。
SNSとは「Social Networking Service」の略称で、ユーザーが情報を発信し、つながりをもてるコミュニティサイトのことです。
個人だけでなく企業も活用しており、マーケティングや販売促進などさまざまな目的で広く利用されています。
最近ではSNSを運用している訪問看護ステーションも増えてきていますが、どのように活用されているのか知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、訪問看護ステーションがSNSを運用するメリット・デメリットについて、活用例を交えて解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
訪問看護ステーションがSNSを運用するメリット
訪問看護ステーションがSNSを運用するメリットは、次の通りです。
- コストを抑えて情報発信できる
- 利用者さんが自ら訪問看護ステーションを選択できる
- 多職種での連携に役立つ
ひとつずつ解説していきます。
コストを抑えて情報発信できる

SNSを活用すれば、訪問看護ステーションの魅力を低コストで発信できます。
SNSは幅広い年代層に利用されており、InstagramやFacebook、X(旧Twitter)などの無料プラットフォームの活用により、宣伝費を抑えつつ多くの人にアプローチできます。
また、写真や動画を投稿できるため、テキストだけでは伝えきれない魅力や職場の雰囲気を直感的に伝えられるでしょう。
特に採用活動にSNSを利用すると、人材紹介会社を介さずに求職者と直接つながれるため、採用コストを大きく削減できます。
DM(ダイレクトメッセージ)での応募受付や、自社採用サイトへの誘導なども簡単におこなえ、コストを抑えながら採用の間口を広げられます。
また求職者も、SNSを通じて会社の情報や雰囲気を事前に把握でき、応募の判断材料にできるでしょう。
浮いた採用コストは、内定者へのお祝い金にあてられる場合もあり、会社側・求職者双方にメリットのある施策が打てます。
利用者さんが自ら訪問看護ステーションを選択できる
訪問看護を利用する際、多くの場合はケアマネジャーやクリニックが候補となる事業所を選定し、利用者さんに提案する形で依頼が進みます。
しかし、訪問看護ステーションは利用者さんやご家族が選ぶこともできます。
その際の判断材料として、SNSが大変役に立つのです。
訪問看護の実際の様子や会社の特徴を発信することで、利用者さんやご家族にとって魅力的な情報を提供できるため、納得したうえで事業所を選んでもらえるでしょう。
多職種での連携に役立つ

訪問看護ステーションだけでなく、居宅介護支援事業所や通所介護事業所などもSNSを活用するようになり、以下のような多職種連携がしやすくなりました。
- 他の事業所スタッフとの交流
- 勉強会の開催
- 利用者さんの紹介
- 利用者さんの情報共有
特に利用者さんに関する情報共有がしやすくなった点は、大きなメリットです。
これまで、情報共有の手段はFAXや電話が主流でしたが、最近ではSNSを活用して情報を共有する訪問看護ステーションが増えています。
なかでもおすすめなのは、「MCS(Medical Care Station)」というツールです。
MCSはLINEのようにスマートフォン1台で手軽に情報共有ができ、訪問看護ステーションだけでなく、以下のような機関でも導入できます。
- 医療機関
- 薬局
- 居宅介護支援事業所など
これまでは事業所ごとに個別でしか提供できなかった情報も、MCSのようなツールの活用により、スムーズに共有できるようになりました。
利用者さんごとにグループを作れるため、大変便利だと感じています。
訪問看護ステーションがSNSを運用するデメリットと注意点
SNSを使うメリットはたくさんあるものの、使い方を誤ると大きなデメリットを招くこともあります。
SNSを運用する際は以下のデメリットを把握し、注意点も押さえておきましょう。
- 個人情報が漏洩するリスクがある
- 炎上するリスクがある
- SNSのみではアプローチに限界がある
ひとつずつ解説していきます。
個人情報が漏洩するリスクがある
スタッフや利用者さんの写真のほか、個人が特定できる場所などの情報を掲載してしまうと、個人情報の漏洩につながるリスクがあります。
写真をSNSに投稿する際には事前に許可をとり、必要に応じて個人が特定できないようにモザイク処理をしたり、位置情報をオフにしたりするなどの対策をとっておきましょう。
炎上するリスクがある

スタッフや利用者さんなど、特定の個人へあてた誹謗中傷や、プライバシーをないがしろにした投稿などをしてしまうと、炎上するリスクがあります。
そのため、自社でSNSを運用する場合は「誰が見ても不快と思わないか」「プライバシーは侵害していないか」といった点を確認してから投稿しましょう。
また、必要に応じてSNS運用に関するマニュアルも作成し、全スタッフに目を通してもらってください。
SNSのみではアプローチに限界がある
SNSは情報発信や多職種連携に役立ちますが、利用していない方や事業所ももちろんあります。
そのためSNSのみに頼るのではなく、ほかの手段と組み合わせることも大切です。
たとえばパンフレットやチラシなどの紙媒体を好む方もたくさんいるでしょう。
また他事業所との関係構築のためには、直接の訪問や対面での交流も欠かせません。
SNSは便利なツールですが、万能ではないためアプローチには限界があることを押さえておきましょう。
訪問看護のSNSはメリットとデメリットを把握したうえで運用しよう
本記事では、訪問看護ステーションがSNSを運用するメリットとデメリットについて解説しました。
無料で情報の発信や共有ができる便利なツールである一方で、使い方を誤ると取り返しのつかない事態を招いてしまうデメリットもあります。
訪問看護ステーションでSNSを運用する際は、メリットとデメリットをしっかりと押さえたうえで、正しく使いましょう。