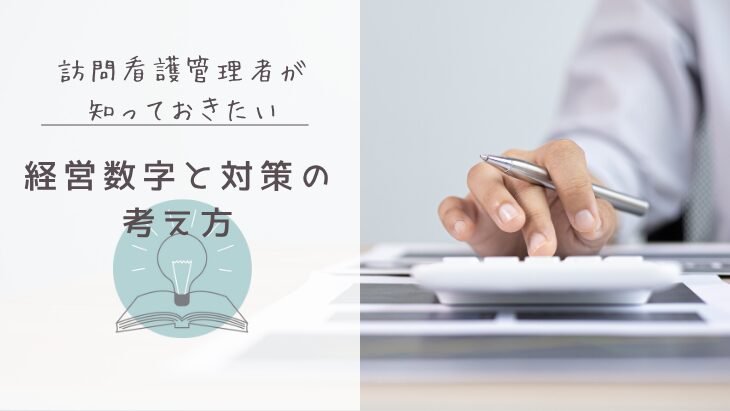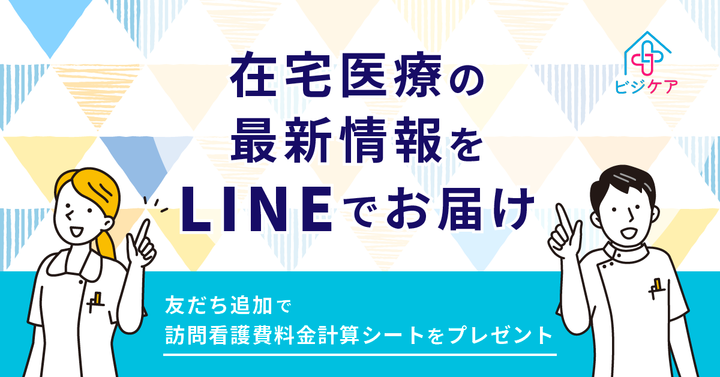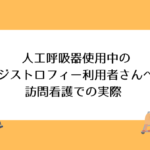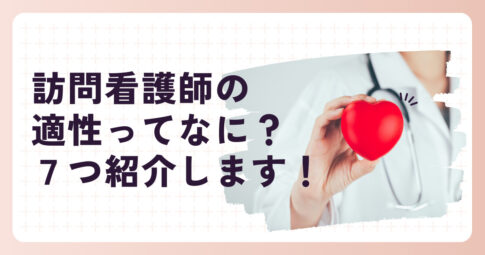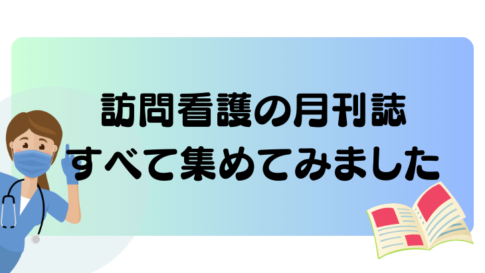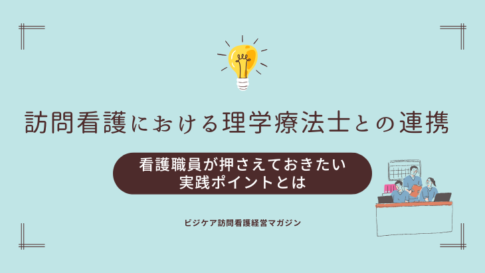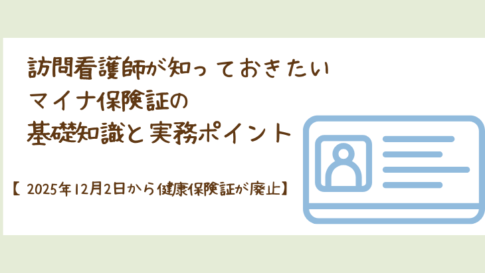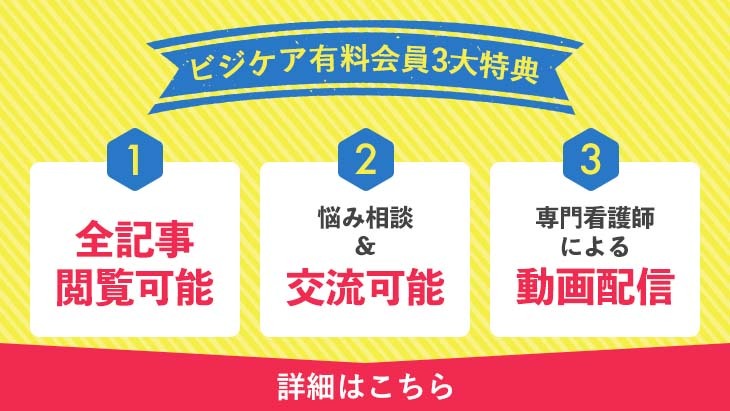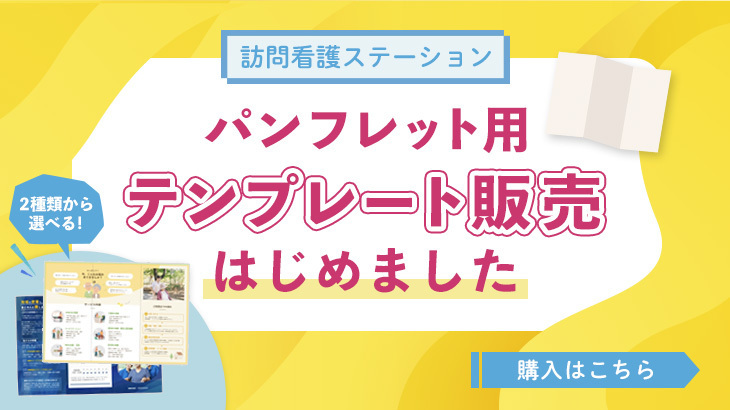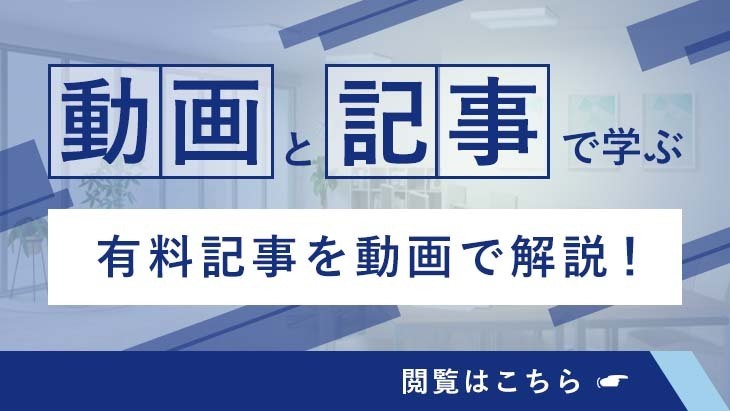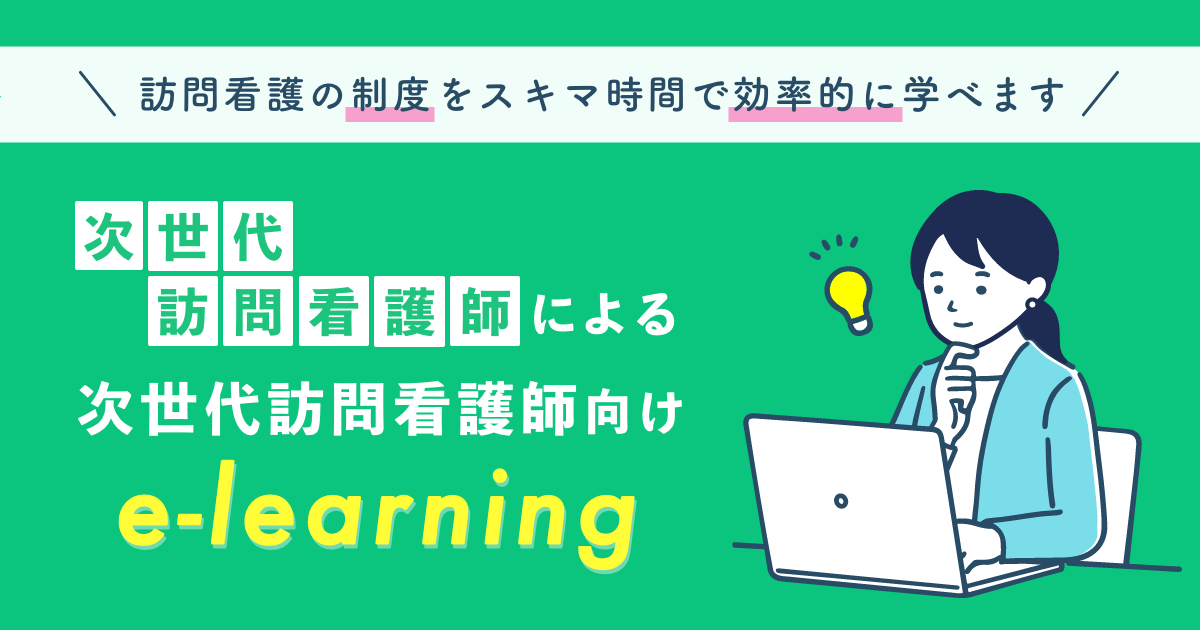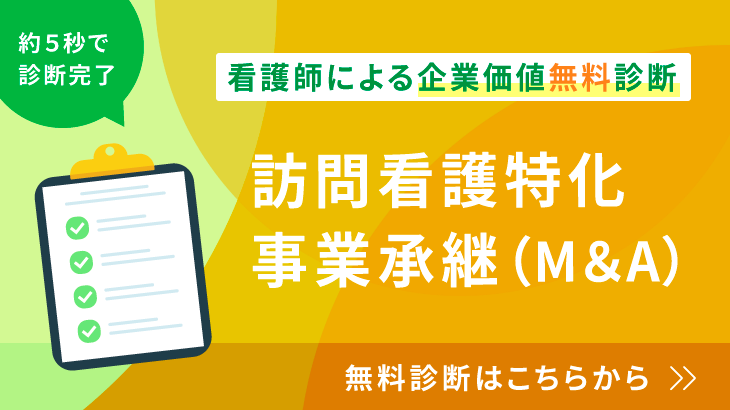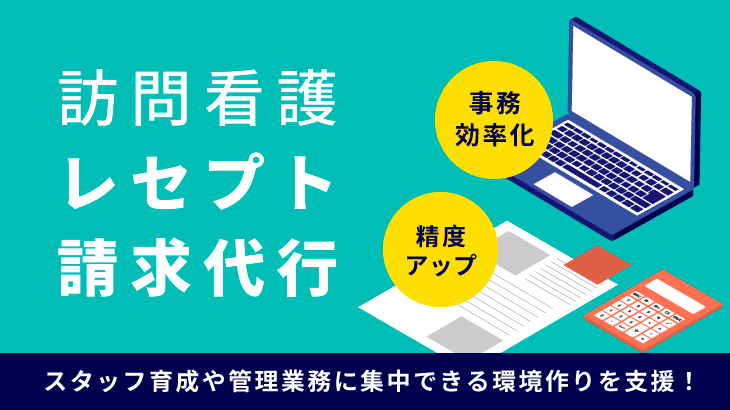訪問看護ステーションの管理者として新たな一歩を踏み出すにあたり、多くの方が「どんな数字を見ればよいのか?」「経営の観点で何を意識すべきか?」と不安になると思います。
私も経験年数が長いという理由だけで雇われ管理者となりました。
その時も「数字は苦手で…」「数字は専門家にまかせればいい」と思っていました。
しかし、それでは必要なときに正しい判断ができません。
実務だけでなく経営的な視点も持ち合わせることで、より強いチーム作りと質の高いサービス提供が可能になります。
たとえ訪問看護ステーションのスタッフであっても、数字を理解しておくことはチームメンバーの一員として非常に重要だと感じています。
この記事では、訪問看護管理者として把握すべき「経営数字」と、具体的な対策について詳しく解説します。
目次
売上の仕組みを理解する

売上は単なる「金額」ではなく、いくつかの要素が組み合わさって形成されています。
- 売上 = 訪問単価 × 訪問数
- 訪問単価 = 介護報酬、診療報酬 + 加算÷訪問数
- 訪問件数 = 利用者数 × 1人あたりの訪問回数
この式を分解すると、売上を向上させるために以下の点が重要であることが分かります。
売上を上げるためのポイント

- 訪問単価・診療報酬をあげる
- 加算を確実に取得する
- 利用者1人あたりの訪問回数の適正化
- 新規利用者の獲得
- 既存利用者の維持と訪問回数の維持
- チームメンバーの協力を得る
順番に説明していきます。
1. 訪問単価・診療報酬を上げる
60分訪問を増やす
長時間の訪問には高い訪問単価が設定されており、根拠をもって必要性を説明できることが大切です。
利用者さんに必要なケアを時間内に終わることができているかをチェックし、場合によっては、ケアマネジャーさんにサービス調整をしてもらう必要があります。
また、リハビリはセラピストではなく訪問看護師の訪問が適切な場合もあります。
医療依存度の高い利用者を受け入れる
特別指示書、難病、ターミナルのケースを積極的に受けます。
ステーション内の教育を充実させて難病利用者さんの受け入れやターミナルケアが提供できる体制にします。
介護保険から医療保険への移行の検討
重度の褥瘡処置や急性増悪等、必要に応じて適切な保険制度への変更を提案します。
2. 加算を確実に取得する
算定漏れのチェック
毎月、制度やルールに基づいて加算の取扱いや請求方法を実施します。
退院前カンファレンスへの参加
加算が得られるだけでなく、利用者理解も深めることができます。
地域連携活動にもつながり、退院後の状況も報告することで、入院先の病院との信頼関係が構築できます。
退院当日の加算
指示書に退院当日の訪問必要と記載してもらい、タイミングを逃さない体制づくりを行います。
退院当日に訪問することは早めの対処で再入院を回避できたり、利用者さんの不安の軽減につながります。
3.利用者1人あたりの訪問回数の適正化
サービスの必要性を明確に
利用者さんの要望やケアマネジャーの依頼は、場合によっては必要な訪問回数とサービス回数が一致していないこともあり得ます。
専門職として必要なケアを提案できるようにします。
複数回訪問の意義を伝える
特に医療依存度が高い利用者さんには、ケアに対する負担感を軽減できたり、安心感にもつながり効果的といえます。
たとえば医療保険の場合、90分訪問が可能ではありますが、利用者の体力も考慮して清潔援助とリハビリの提供など、複数回訪問にしたほうがよい場合もあります。
4. 新規利用者の獲得
地域連携活動の強化
医師やケアマネジャーには、適切なタイミングで情報提供ができると信頼関係が構築できます。
医師への病状変化時の報告はもちろん、退院のタイミングなど利用者さんに関する情報を事前にお伝えすることも必須です。
またケアマネジャーには、モニタリング前の情報提供を意識することや、ケアやリハビリの効果などを具体的に報告することで、担当の利用者さんを大切にしてくれていると感じ、喜ばれます。
ケアマネジャーの困りごとの把握
ケアマネジャーの中には、困難事例を抱えている方も多く、ニーズにマッチした提案ができれば信頼につながります。
あいさつだけでなく、困り事がないかを聞いてみましょう。
5. 既存利用者の維持と訪問回数の維持
キャンセル時の別日提案
できるだけ売上の減少を防ぐ工夫は必ずします。
キャンセルが思わぬ訪問回数を減少していることがあります。
利用者が必要とするケアの再確認
ニーズの変化に応じた対応が大切です。
状況の変化や介護者の体調変化なども影響があります。
状況に応じて必要とするケアが提案ができるようにしましょう。
6.チームメンバーの協力を得る
経営的視点をスタッフ全体で共有することも重要
管理者だけが経営的数字を把握していても、実際はスタッフに動いてもらうことが必要になります。
定期的なミーティングで数字を共有し、目標達成に向けた意識を高めましょう。
毎月確認しておきたい主な経営指標
| 指標 | 意味・確認ポイント |
| 平均単価(件数・時間) | 平均件数単価は、30分訪問や複数回訪問の割合が高いと単価は低くなる/平均時間単価はサービス訪問や加算の取得状況に注意が必要 |
| 利用者1人あたりの訪問回数 | 訪問回数の適正化/ケア内容と回数の検討 |
| 人件費率 | 高すぎる場合は業務の効率化を検討(60~65%) |
| 利益率 | 経営の健全性を表す指標(20~25%以上) |
| ケアの比率 | 実際にケアに充てた訪問時間と就業時間のバランス/件数とケア時間の差が大きいとスタッフが疲弊している可能性がある |
| 訪問看護師1人あたりの月売上 | 人員配置と収益のバランス/スタッフを増やした分の売上が増収したかわかる |
| 訪問看護師1人あたりの1日売上 | 実働ベースでの生産性評価/売上は稼働日が多いか少ないかの影響だけなのか、増収したのかわかる |
まとめ
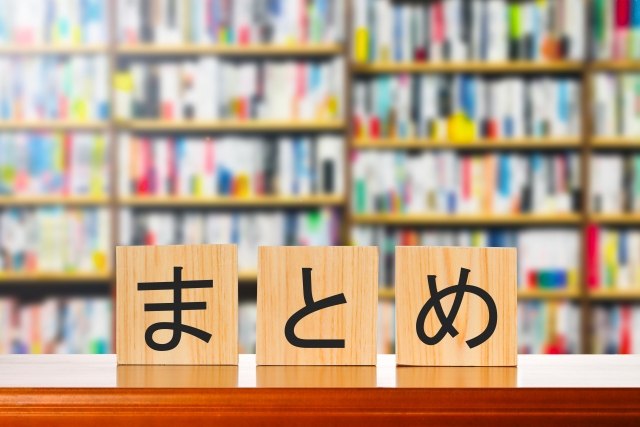
訪問看護ステーションの管理者として、経営数字を「読む力」「活かす力」は非常に重要です。
昨今ホスピス型有料老人ホームの不正請求が話題となっています。
訪問看護師として大切なのは「制度とルールを正しく理解して利益をだすこと」です。
数字をもとにスタッフと共に課題を明確にし、改善を積み重ねていくことで、より質の高い訪問看護サービスを提供することができます。
ビジケアでは、経営数字をはじめ、よりくわしく学ぶために訪問看護経営スクールを受講することができます。
無料オンライン相談会もありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
\詳細はコチラ!/
訪問看護をおこなう中で誰もが不安や疑問に思ったりすることを解決できるような記事の作成を心がけています。
この記事がみなさんの日々の業務に役立ってもらえると幸いです。