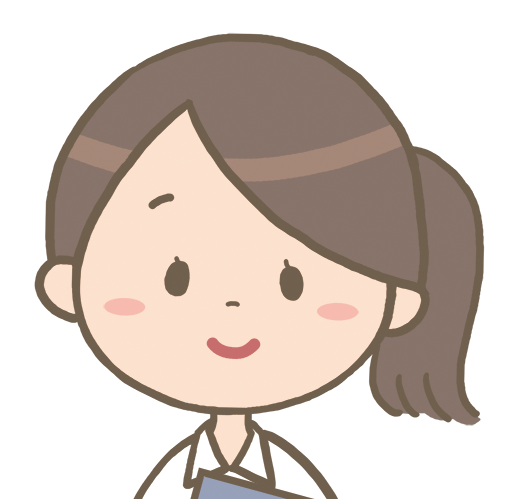
このような不安を解決する記事です。
訪問看護の業務のひとつに「オンコール当番」があります。
訪問看護ステーション営業終了時間から翌朝の営業開始時間までにかかってきた、利用者さんやご家族からの電話に対応する業務です。
いつ電話がくるかはわからず、夜中に電話がくることもあります。
オンコール当番に関する不安はいくつかあると思いますが、その中のひとつに「起きれなかったらどうしよう」という不安があるでしょう。
この記事では「オンコールで起きれなかったら?」という不安に焦点を当て、対策を解説していきます!
現役訪問看護師が実践する対策なので、参考になることが多いと思います。
- これからオンコール当番をする予定の方
- オンコール当番をしているけど夜起きれるか不安な方
上記のような方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ではさっそく解説します。
目次
「オンコールで起きれない」への対策7選

「オンコールで起きれない」への対策として以下の7つを紹介します。
- 充電・電源確認
- 着信音・バイブレーションの設定
- スマートウォッチの使用
- 寝る場所を変える
- 2名体制を取る
- 無理のない勤務
- 体調管理
順番に解説します。
充電・電源確認
当番の電話の充電・電源を確認しておくことは、基本的なことですがとても重要です。
充電がなくなってしまったり、電源がOFFになってしまっていては、そもそも電話が鳴りません。
オンコール対応前に充電は十分かしっかり確認し、必要があれば充電しましょう。
電源がOFFになっていないかも要確認です。
着信音・バイブレーションの設定
着信音の設定を適切なものにすることも、オンコールで起きれないことを避けるために重要です。
音が小さすぎたり、優しい音色の着信音だと、寝ている時は気づかない可能性があります。
- 着信音は大きめに設定
- 優しいメロディ音よりは電話のベル音
- 念のためバイブレーションもonにする
上記のことを踏まえて着信音・バイブレーションを設定しましょう。
普段自分で使用しているスマートフォンのアラーム音とも違う音に設定することをおすすめします。
スマートウォッチの使用
スマートウォッチの使用も、オンコールで起きれないことを避けるための一案です。
スマートウォッチには、スマートフォンの着信をバイブレーションで教えてくれる機能が備わっているものがあります。
万が一電話の着信音に気が付かなかったとしても、手首に装着しているスマートウォッチが振るえれば、電話に気づく可能性が高いです。
寝るときに腕時計をすることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、慣れるとあまり気にならないものです。
安価でも着信通知機能が付いたモデルは増えてるので、心配な方は試してみるのも良いと思います。
寝る場所を変える
普段と寝る場所を変えてみるのも、オンコールで起きれないことを避ける対策となります。
オンコールの日だけ違う場所で寝ることで「今日はオンコールだ」という意識が働き、着信に気づきやすくなるためです。
普段は家族と一緒に寝ている場合も、オンコールの日だけ別の場所でひとりで寝ることで、着信音量を大きくしやすかったり、電話対応時も家族に気を使わずできるメリットもあります。
ぜひ試してみてほしいです。
2名体制を取る
オンコール当番の体制として、「ファースト」と「セカンド」を設け、2名体制としている訪問看護ステーションも多くあります。
2名体制は、そもそもはファーストの訪問看護師が電話対応・臨時訪問している間に、さらに他の利用者さんから電話があったときに対応するための体制です。
しかし、万が一ファーストの訪問看護師が着信に気づかないという事態が起きた時、セカンドの訪問看護師がフォローできるのは、心強い体制と言えます。
利用者さんに必要なサービスを確実に提供するという点においても有益で重要です。
訪問看護ステーションによっては2名体制を取っていない場合もありますが、2名体制が取られている場合は、オンコールに気づかないことを避ける対策になるでしょう。
無理のない勤務
日々の勤務に無理がないことも、オンコールで起きれないことを避けるために重要です。
きつすぎる勤務では疲労が蓄積し、オンコールで夜間起きられないことにつながるからです。
- 日中の訪問件数が多すぎる
- しっかり昼休憩が取れない
- オンコールで夜間出動しても、翌日普通に勤務がある
このような勤務状況が続くと、どんどん疲労が蓄積する可能性があります。
逆に、無理のない勤務で働けると、うまく疲労を回復することができ、オンコールで起きれない事態を避けやすいでしょう。
現在の勤務がきつすぎると感じる場合は、一度上司に相談してみても良いと思います。
体調管理
最後は体調管理です。
疲れを残さないための体調管理を自身で日々実践することは、非常に重要です。
- 寝れるときにしっかり寝て、十分な睡眠を確保する
- 食事でしっかり栄養を摂る
- 適度な運動を心がけ体力維持に務める
体調管理は自身でできる一番効果的な対策だと思います。
自身の健康を守るためにも、ぜひ意識して継続する努力をしていきましょう。
訪問看護のオンコールはきつい?

訪問看護のオンコールに関する不安は、「起きれない不安」以外にもあるかと思います。
- 実際やっぱりオンコールってきついのかな?
- 自分にちゃんと務まるかな?
- ちゃんと対応できるかな?
慣れないうちは苦労や失敗もあるかもしれませんが、訪問看護のオンコールは必ず務まります。
詳しくはぜひこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
「オンコールなのに起きれない」を避けよう!しっかり準備して臨むべし

「オンコールなのに起きれなかったらどうしよう」という不安は、誰しもが感じる不安です。
今回ご紹介した対策を参考に、ぜひしっかり準備してオンコールに臨んでみてくださいね。
利用者さんが安心して過ごせるよう、安全で質の高い訪問看護を提供していきましょう!
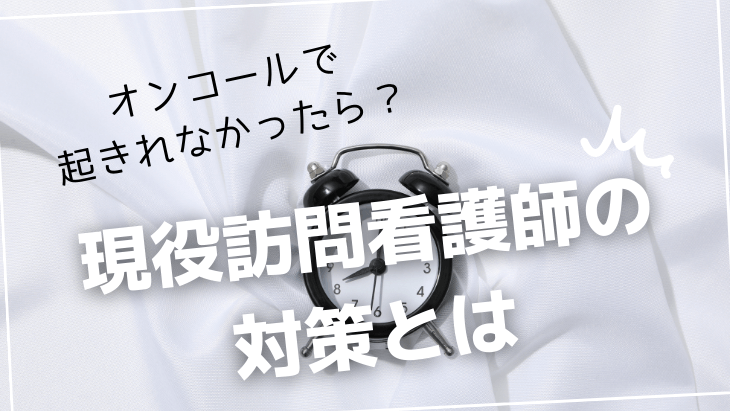
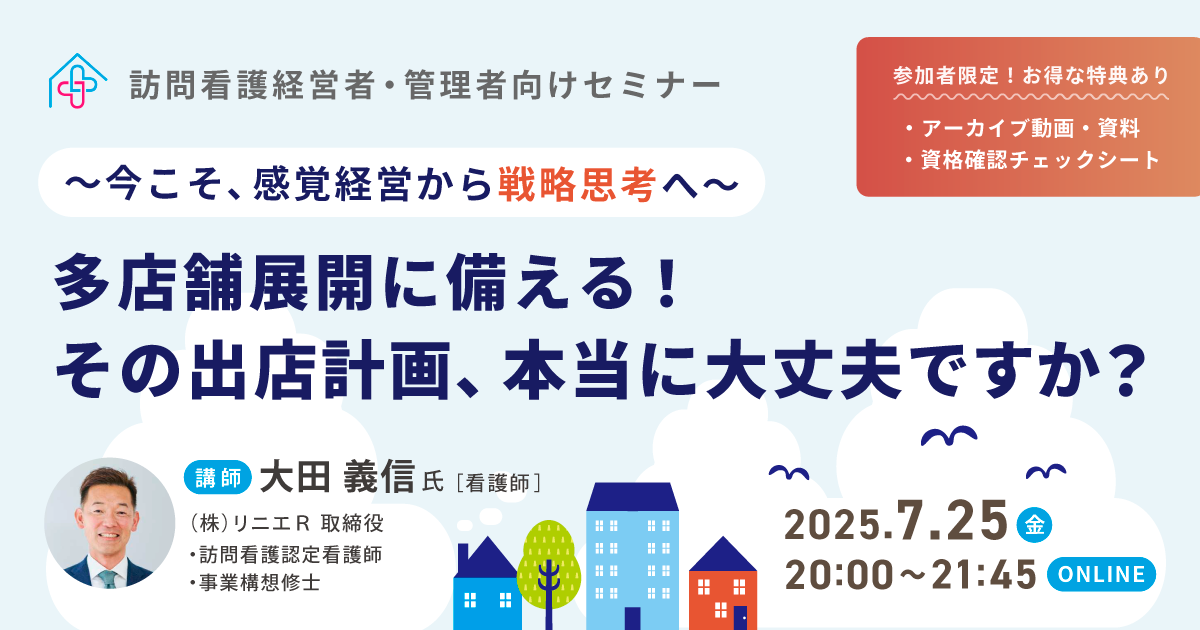



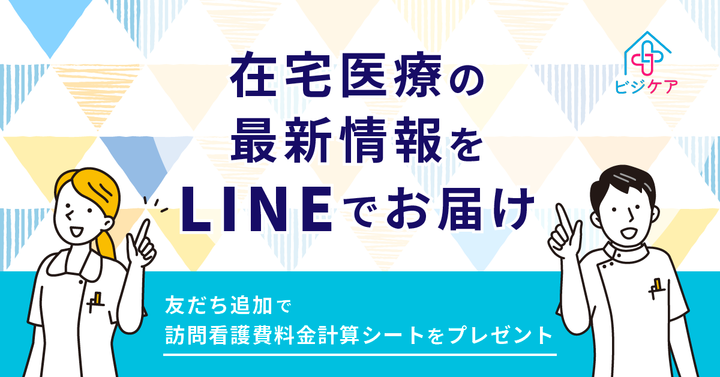










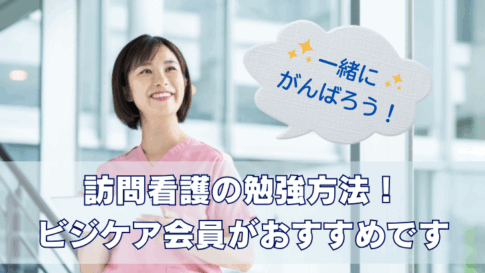



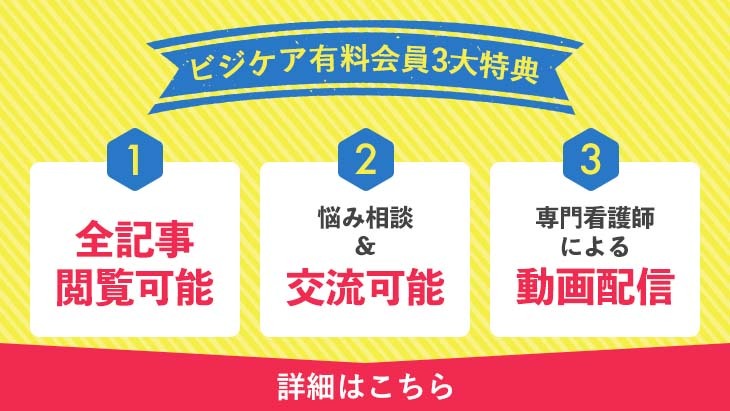

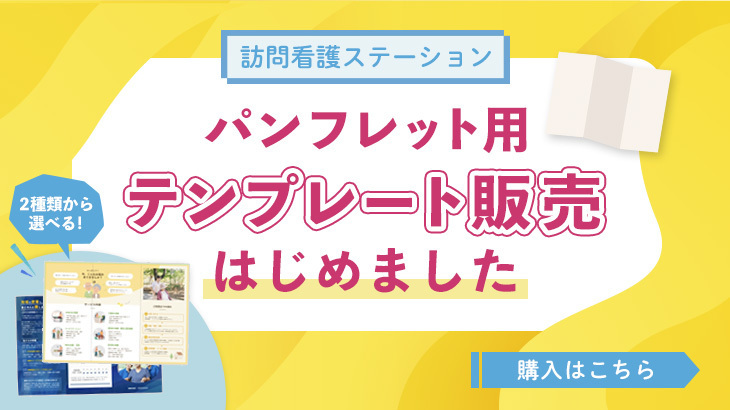
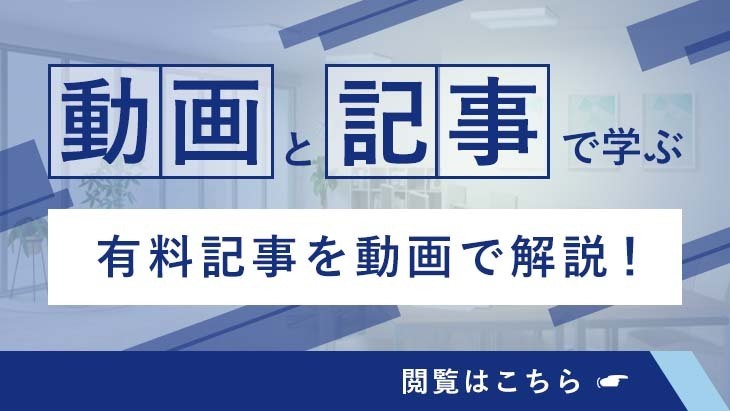
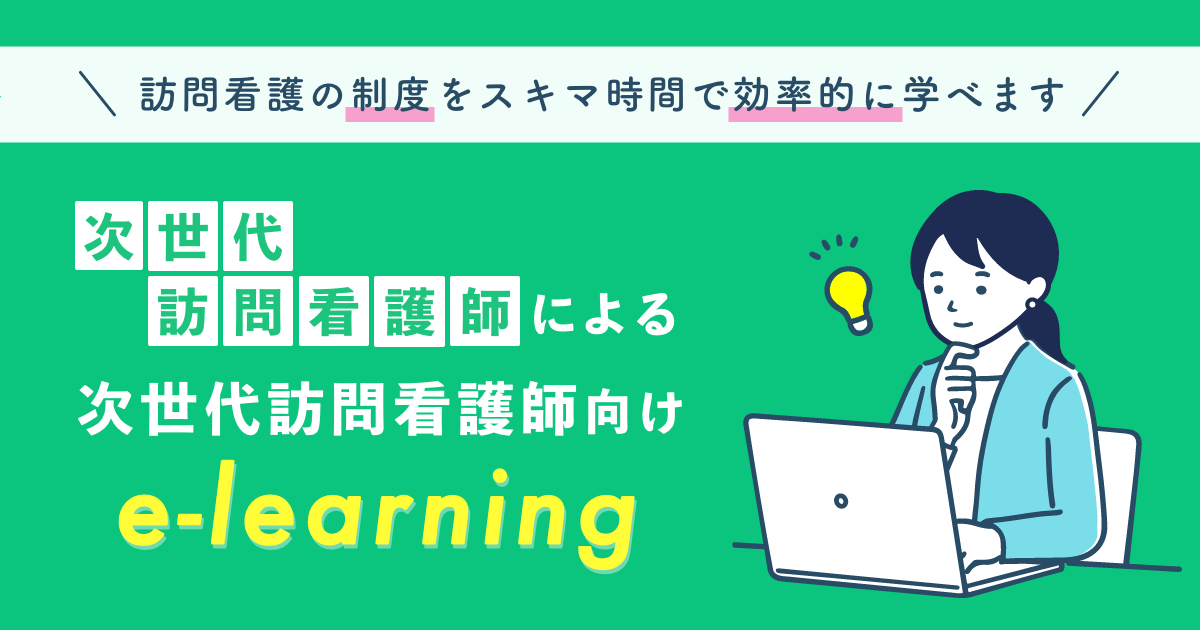
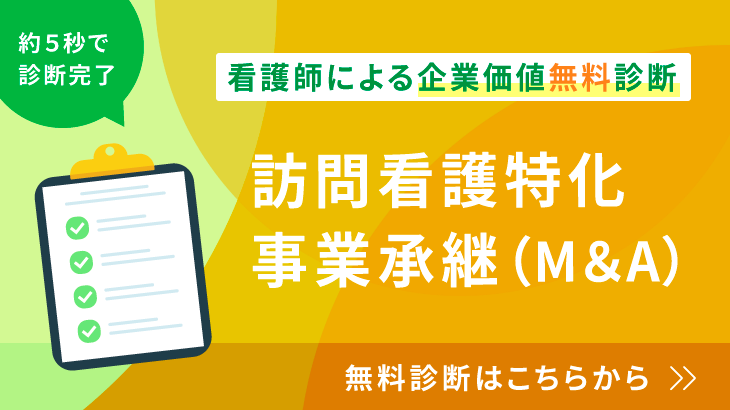
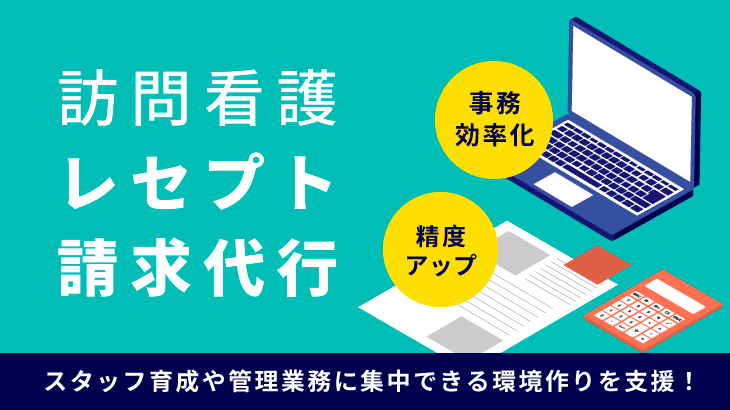

訪問看護師です。今度オンコール当番をすることになったけど、夜中起きられるか不安です。皆さんどうやって起きていますか?ちゃんと起きられるものでしょうか?