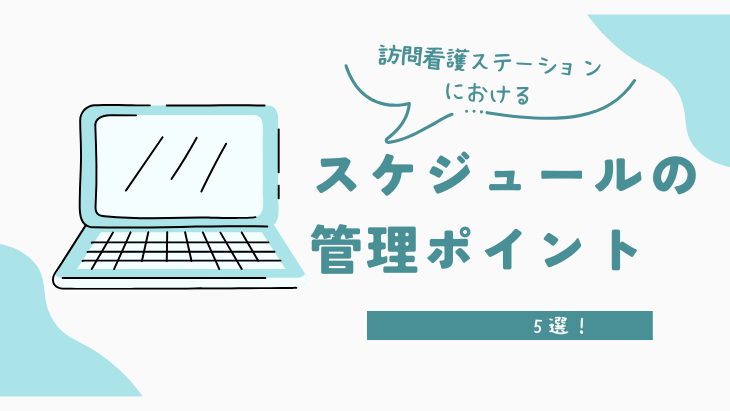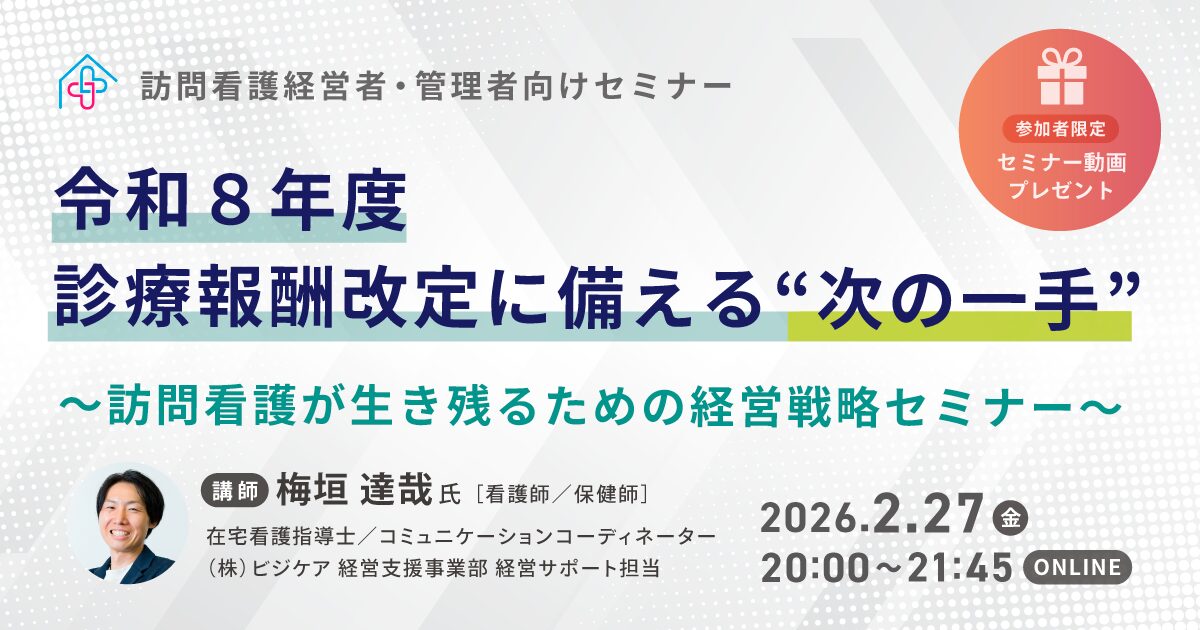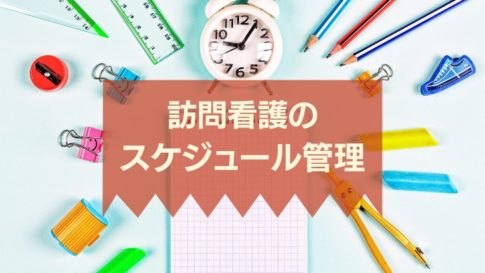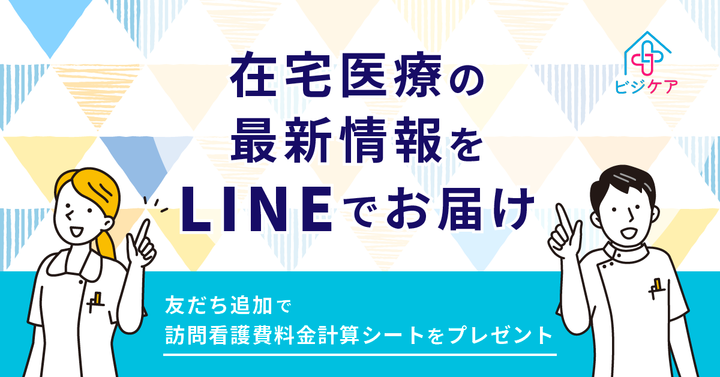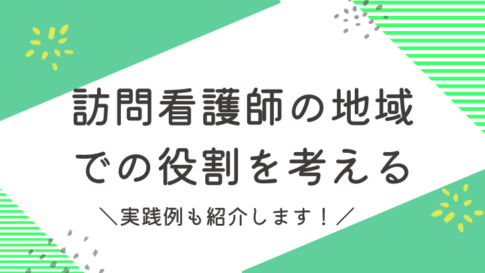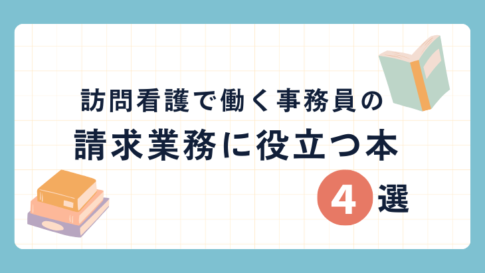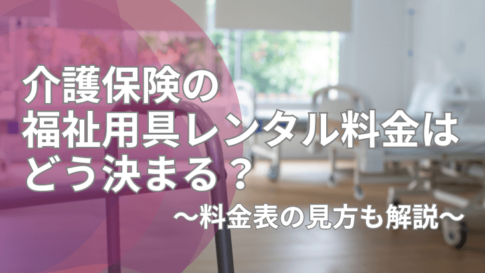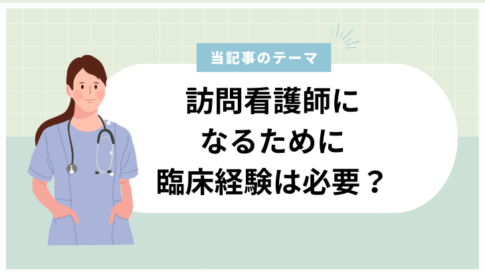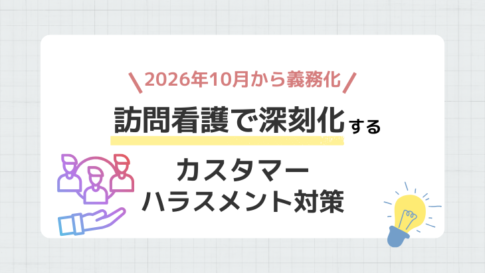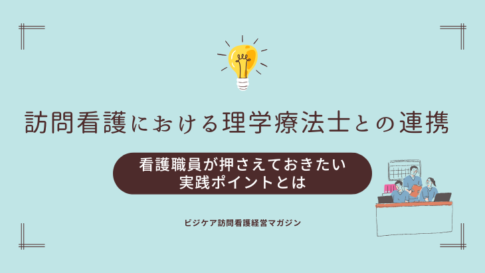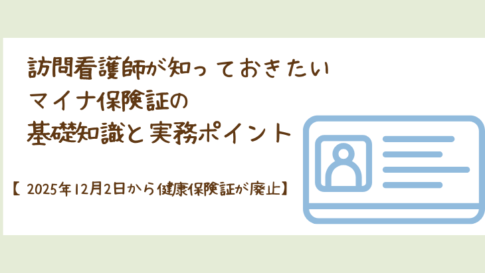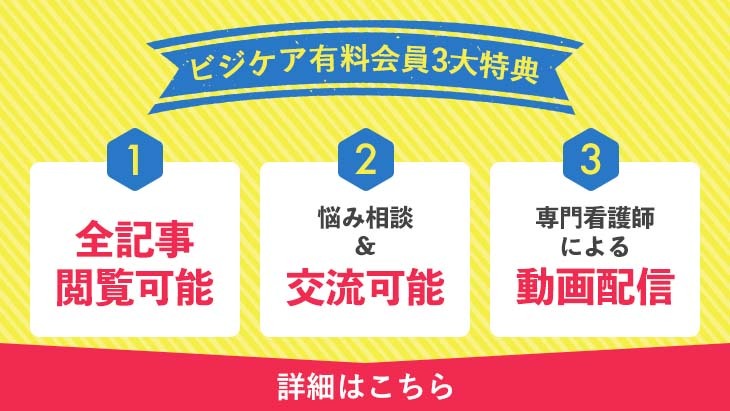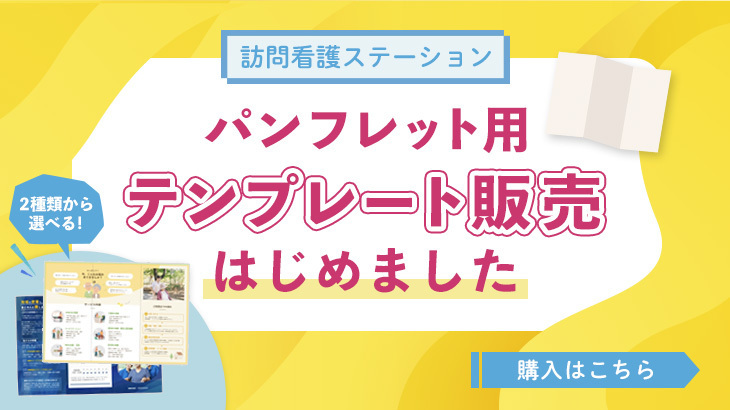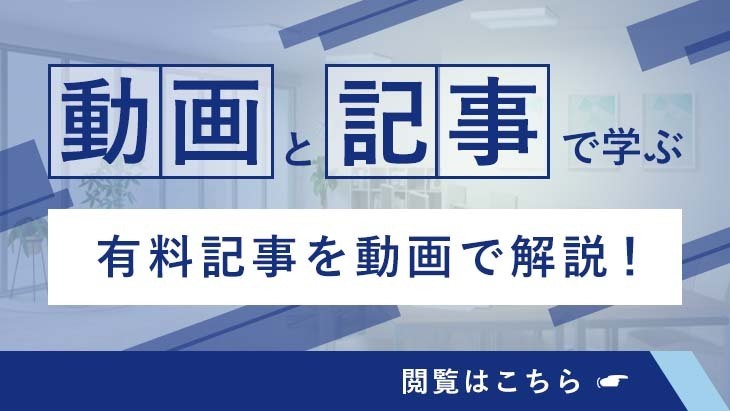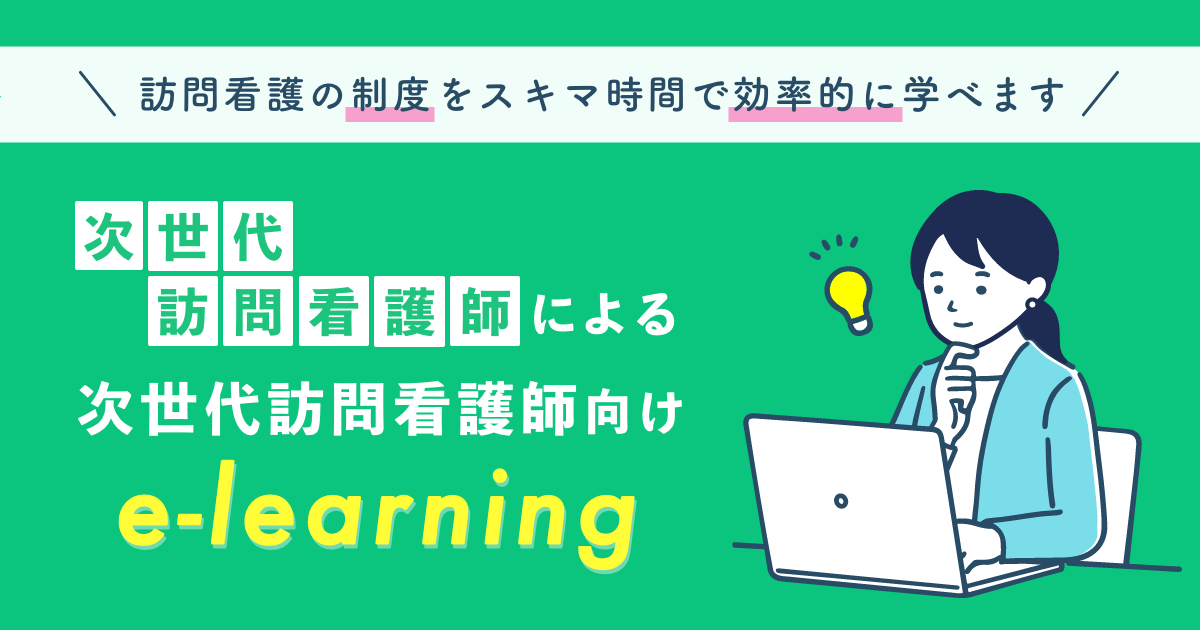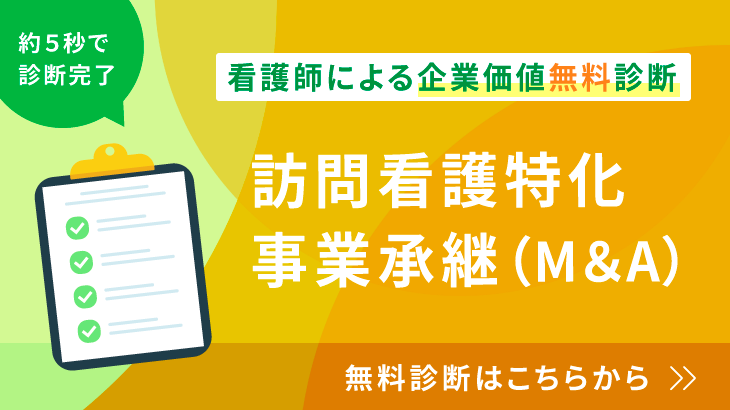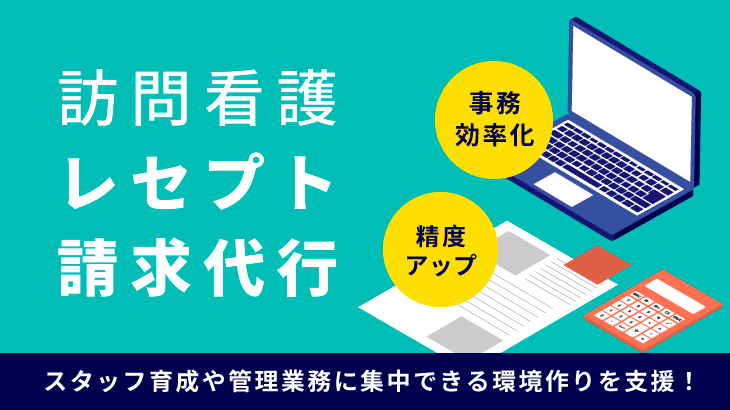訪問看護ステーションのスケジュール管理は、効率的な運営や収益の向上、スタッフの負担軽減において非常に重要です。
開設して間もない場合は、空きコマが多いので気にすることは少ないと思いますが、事業所であらかじめ方針を立てて、将来受けるべき訪問数を考慮し依頼を受けておくことが収益の視点からも大切です。
私の訪問看護の経験上、実はこのスケジュール管理が一番苦労をしています。
この記事はこういったことに悩んでいる訪問看護管理者が押さえておくべきポイントを整理しました。
目次
訪問看護のスケジュール管理の考え方

- 訪問看護師一人あたりの訪問件数の基準を設定する
- 訪問エリアを意識して、できるかぎり移動時間の短縮を図る
- 効率的なスケジュール調整をする
- 担当制に偏らない方針
- チームで調整力を高める
一つずつ解説します。
訪問看護師一人あたりの訪問件数の基準を設定する
安定した稼働率を維持できるようにするためには、事業所内で訪問看護師の1日の訪問件数は何件という概念を決めておく必要があります。
訪問看護ステーションの売上から考え、訪問看護師1人当たりの1日の訪問件数(例:5~6件)をあらかじめ決めておきます。
そして、午前・午後・夕方・移動時間は何分といった設定をする必要があります。
訪問エリアを意識して、できるかぎり移動時間の短縮を図る

訪問地域は、介護保険上、届出が必要です。
自事業所の届出をしている地域を移動時間の目安をもとに、訪問ルートを調整するためエリアを分けます。
事業所から移動時間の近いところをAエリア、次にBエリア、Cエリア、一番遠いところをDエリアなどとエリア分けを設定します。
効率的な移動ができるエリア分けとその視点が重要です。
移動時間は、地域によって様々ですが、山間部を除き15分以内が理想と考えます。
地域の渋滞などの交通事情にもよりますが、距離的には5キロ以内が経験上望ましいと思います。
開設当初、ここが空いているからと適当にスケジュールを組んでいくと6~7割くらいの訪問が埋まると、新規の受け入れができない、就業時間内に回れないといったことが起こります。
原因は、移動時間に対する調整をしていないことが考えられます。
例えば、A訪問看護師の月曜日の午前にAエリアの依頼があれば、次はAエリア内かAエリアから移動時間15分以内のBエリアまでといった感じに調整します。
遠いエリアの場合は、場合によって昼休憩は事業所に戻らずに、車で休憩していただく方法をとることもあります。
新規依頼がそのエリアの新規開拓につながっていくチャンスと捉えましょう。
移動時間をコントロールできれば、午前中に1時間訪問で3件、休憩後午後から3件といったように1日5~6件は訪問できるようになります。
効率的なスケジュール調整をする

できる限りの移動時間の短縮
エリアごとの視点で訪問スケジュール管理を行うことで、無駄な移動を避けます。
タイトすぎるスケジュールは運転に支障がでたり、焦ってしまうなど安全面でリスクを伴うため、余裕を持たせつつ効率化が必要です。
例えば、訪問看護ではいろいろと問題発生の可能性があるため、余裕をもって15分の移動時間を組んでおき、5分で移動できた場合は、前の利用者さんの記録をする時間にあてるなど、訪問看護師自身が柔軟に時間の工夫ができるようになります。
利用者宅への訪問時間の設定
利用者さんの中には、朝早いのは苦手、朝早くてもいいといった方がおられます。
必ずヒアリングしておき、早い時間の訪問が開始できるように調整します。
私の事業所は8時30分の始業時間のため、8時45分から訪問開始できるようにしています。
朝のミーティングや情報交換が必要という考え方もありますが、コロナ禍での訪問業務の見直しから、直行直帰といった考え方ができるようになりました。
朝のミーティングをしない、直行直帰をすることで、1件でも利用者さんを獲得でき、1件でも多く訪問することができます。
その代わり朝のミーティングや情報交換は、全体会議を月1回は設けることや情報の共有はツールを利用します。
実際のところ、朝のミーティングより情報ツールのほうが時間が短縮でき、何度も見返したりできるメリットがあることがわかりました。
また、一番遠いエリアの訪問で終了になる場合には、ステーションに戻ってくることがしんどくなってくることが考えられます。
その場合には、その終了になる利用者さん宅から近い勤務職員を選定し、直帰を提案しています。
実際私も、この直帰の方がいつもより早く帰宅でき、子育て中は大変ありがたかったです。
訪問看護師の情報交換の場がない、直行直帰が不安ということがないようにフォローし、1件でも多く訪問できる体制づくりが大切です。
担当制に偏らない方針

このようにスケジュール調整をすると、どのエリアの依頼があればどの訪問看護師に依頼するかは決まってきます。
また曜日や午前、午後指定などがあれば、その曜日の中から移動可能な利用者さんに調整をお願いすることになります。
その場合は、担当訪問職員の交代が生じることもあります。
利用者さんが特定の職員だけを希望することがないよう、多くの職員が関われる仕組みを構築します。
その際、契約時に「担当制をとっていない」旨を説明しておくということをしています。
中にはご理解がむずかしい利用者さんに対しても、多角的にアセスメントを行えること、いろいろな視点やアイデアがでてくる場合もあるといった、たくさんの職員が関わるメリットを伝えるようにしています。
新入職員の導入方法について
新入職員には、動線の良いルートを同行訪問で引き継ぎ、効率よく独立できる体制を整えます。
動線の良いルートのまま新入職員には同行してもらい、スケジュールが整ったまま引き渡すことが理想です。
しかし新入職員の力量などにもよるので、同行した職員と相談し、午前だけ、午後だけといったように引き継ぎをすることもあります。
チームで調整力を高める
訪問スケジュール調整は、新規の利用者さんだけでなく、常に既存の利用者さんにも調整する視点は必要です。
新規の利用者さんの場合は、ケアマネジャーからのケアプラン上、何曜日のこの時間という設定の依頼も多くあります。
新規の場合は、利用者さんやケアマネジャーの訪問時間のニーズを聞き入れるようにします。
その後、利用者さんとの信頼構築ができると、他のサービスの兼ね合いや1日の生活状況などを理解することができると交渉することも可能になります。
朝の訪問がむずかしいが、身体的な理由(夕方の方が動きが良いので入浴介助がスムーズなど)から夕方の訪問が最適であるなど、常に利用者さんや家族からの情報収集をしておきます。
あとあとスケジュール調整が必要になったとき、お願いできるという職員の交渉力が重要で、実際に訪問している訪問看護師から調整をする視点をもち提案してもらえるようにすることも重要になります。
訪問スケジュール調整は、管理者だけでなく訪問看護師自身も調整するということを意識しておくことが大切なことと言えます。
訪問看護のスケジュール管理の注意点
他にもスケジュール管理には以下の注意点があります。
- 地域事情に応じて移動時間を適切に見積もり、職員への負担が過剰にならないよう配慮する。
- 既存の利用者のスケジュール調整が必要になった場合は、ケアマネジャーに報告し必ず了承は得ておく。介護保険の利用者はケアプランにもとづいて訪問していることは忘れてはいけない。
- キャンセル時の対応策として振替の提案をする。
- スケジュールの空き枠は発生してしまうものなので、すること(営業や月初めに書類を届けるなど)を決めておき空き時間は有効活用する。
- 訪問看護は緊急対応が必要な場合も多く、移動や訪問中でもスムーズに情報を共有できる仕組み(ツールや連絡体制)を整備する。
- GoogleマップやZESTなどスケジュール管理ツールを活用して効率化を図る方法もある。
まとめ
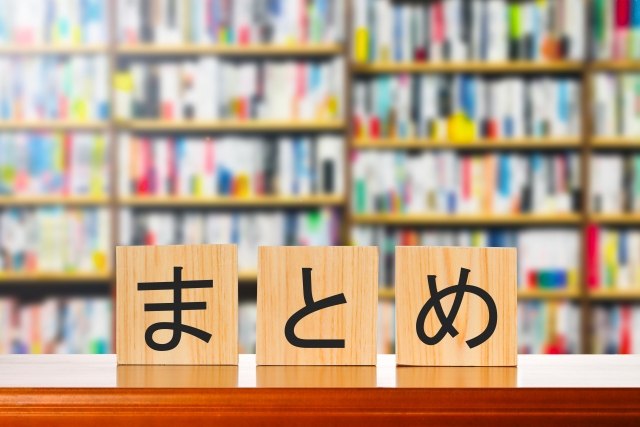
- スケジュール調整ができると訪問看護師一人当たりの訪問件数が増え、稼働率が向上する。
- 移動時間が短縮されれば、訪問看護師の身体的・精神的負担が軽減される。
- 空き枠が調整できれば、新規依頼を受けやすくなり、事業所の信頼度が向上する。
- 安定した運営につながる。
訪問看護スケジュール管理は、訪問看護師が利用者さんや家族とのコミュニケーションの中で、柔軟に見直しできるようにし、チームで調整力を高めます。
効率的なスケジュール管理は、訪問看護ステーションの運営を安定させるだけでなく、職員の働きやすさや利用者の満足度向上にもつながってきます。
この内容が、日々の業務改善にお役立ていただければ幸いです。