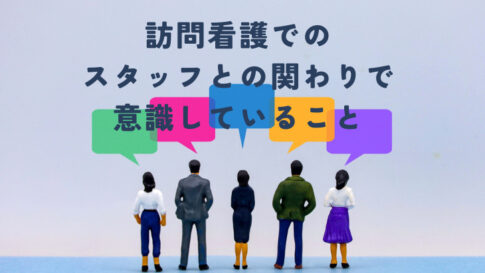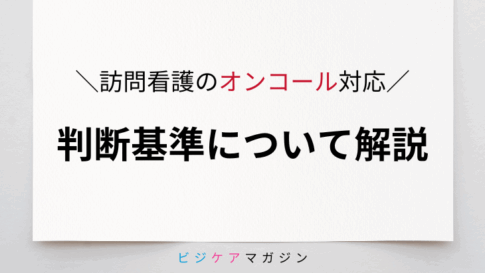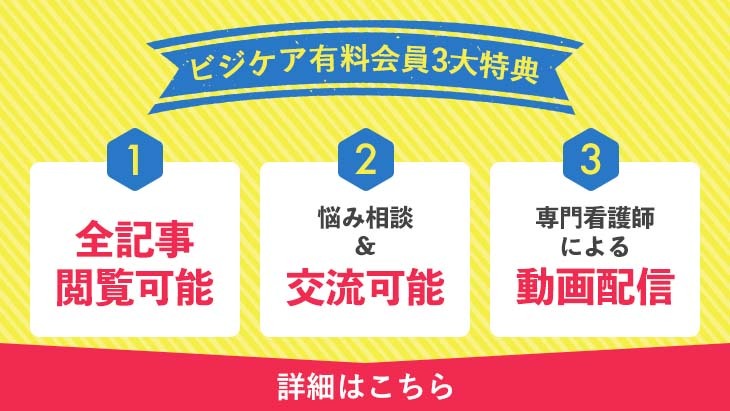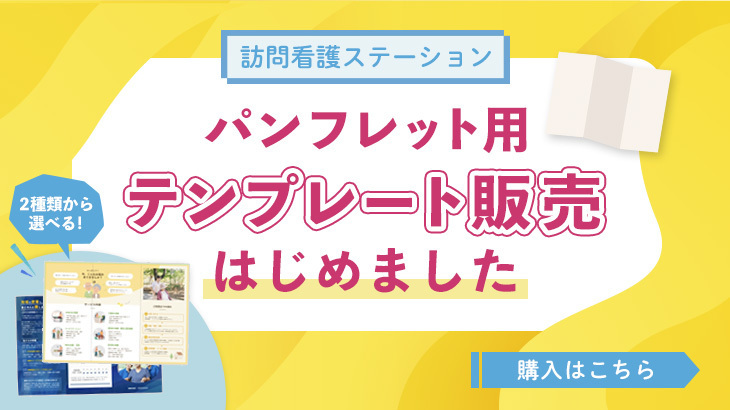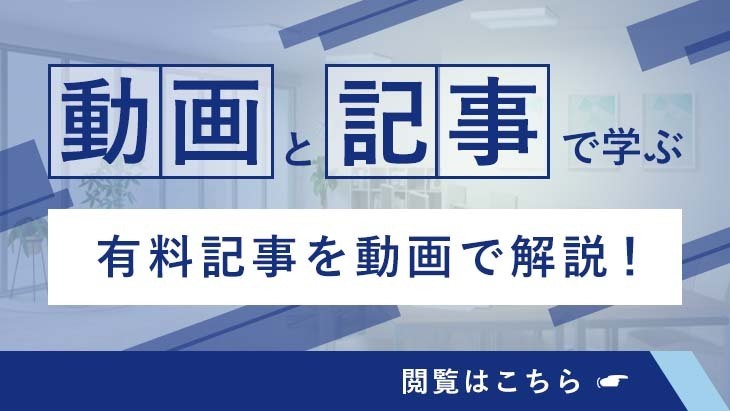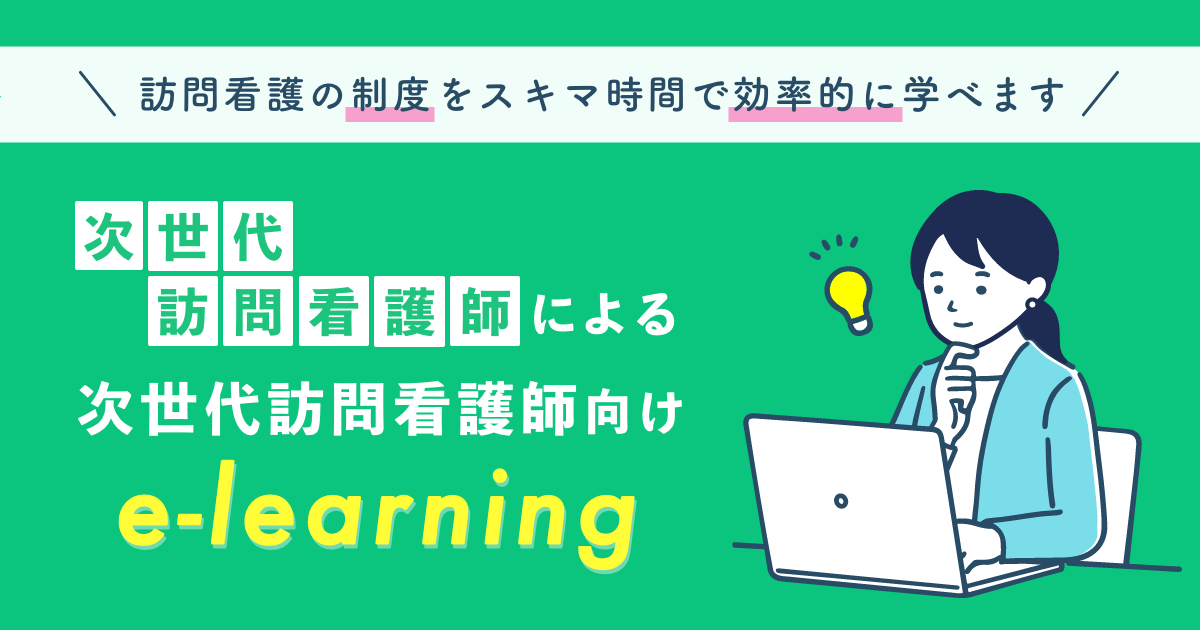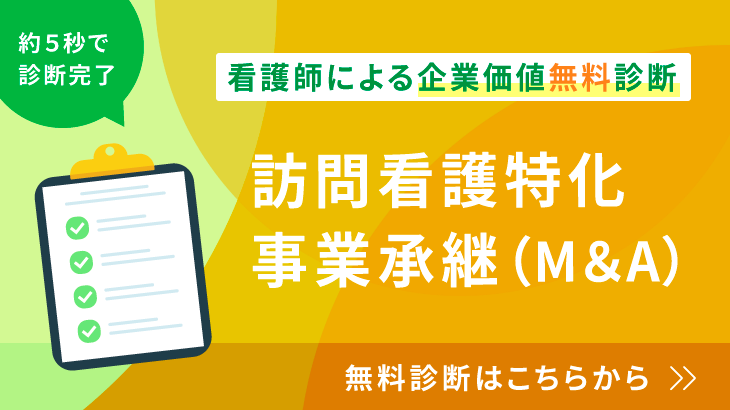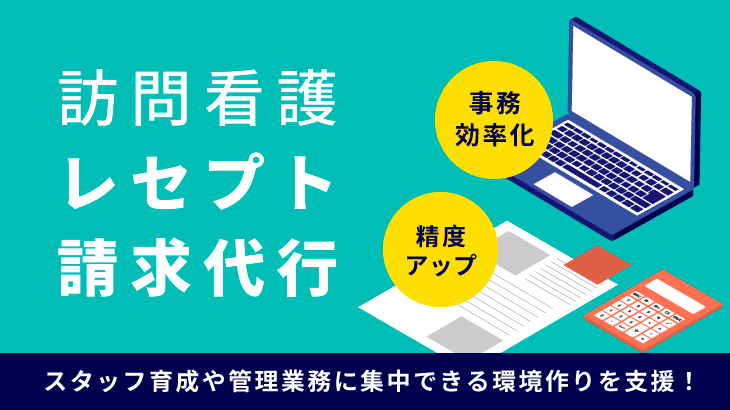このような悩みにお答えします。
訪問看護にリハビリ職として勤務したものの、「利用者さんの家族にすべき指導内容がわからない」という方もいるのではないでしょうか。
特にベッドでの生活が中心の利用者さんは、介助量の多さや皮膚トラブルのリスクなどがあり、家族の負担も大きいと考えられます。
そのため、安全で楽におこなえる介助方法の指導が重要です。
そこで本記事では、経験10年を超えるPTの視点から、リハビリ職がしておきたい家族指導のポイントをわかりやすく解説します。
本記事を参考にすれば家族指導のポイントが理解でき、家族が安全で楽に介助できるようになりますよ。
目次
リハビリ職がしておきたい家族指導5つ

利用者さんを介護している家族と話していると、「腰が痛い」「着替えさせるのが大変」といった相談をよくされます。
そのため、身体的負担が少しでも減るような家族指導の重要性を感じています。
今回は、ベッド上での生活が主の方に対してリハビリ職がしておきたい家族指導を5つ解説します。
主な内容は次の通りです。
- 背臥位から側臥位への体位交換
- 頭側への移動介助
- 褥瘡管理
- ポジショニング
- 腰痛対策
それぞれ見ていきましょう。
背臥位から側臥位への体位交換
ベッドで寝たきりの方の更衣介助やオムツ交換など、側臥位への介助が必要な場面は多いですよね。
実はあまり力を使わずに、スムーズに背臥位から側臥位へ誘導する方法があります。
この方法は下肢の重量と体のねじれを利用するため、大きな体格の方の介助でもあまり力を必要とせず、負担が少なくおこなえます。
つい力任せに介助してしまう家族には、上記のポイントを伝えてみましょう。
ベッド頭側への移動介助
オムツ交換やギャッジアップの後に、利用者さんがベッドの下の方にずれてしまうことがよくありますよね。
体格の大きな方を頭側に移動させるのは、大変負担がかかる介助です。
そこで、頭側へスムーズに移動できる介助方法を紹介します。
スライディングシートを使うと楽におこなえますが、もしなければゴミ袋で代用してみてください。
この方法は摩擦を減らした介助であるため、仙骨や背部の褥瘡がある方にも安全におこなえます。
ただし寝返り動作を繰り返すため、めまいが起こりやすい利用者さんには背臥位のまま頭側への移動介助をおこないましょう。
その際、スライディングシートやゴミ袋も使用し、摩擦へ配慮することが大切です。
褥瘡管理
自宅介護では、寝たきりの方に褥瘡ができてしまうことがあります。
病院では看護師や介護スタッフが専門知識を活かして予防やケアをしますが、在宅では家族がその役割を担うため、褥瘡予防に向けた指導が重要です。
リハビリ職としては、看護師と連携しながら家族にも褥瘡管理の重要性を伝え、在宅介護の負担を減らせるようにサポートしていきましょう。
以下で、褥瘡の発生や悪化を防ぐために重要な3つのポイントを解説します。
①体位変換をこまめにおこなう
褥瘡発生の要因として、同じ姿勢による持続的な圧迫が挙げられます。
医療者には常識でも家族にはあまり知られていないことが多いため、体位変換の必要性をしっかり伝えましょう。
また上述の「背臥位から側臥位への体位交換」を基本に、負担をできるだけ減らした介助方法を指導してください。
② 引きずらないように介助する
褥瘡は圧迫だけでなく、皮膚に加わる「ずれ力」でも発生・悪化します。
特に皮膚が弱い部分にずれ力がかかると、急速に悪化することがあります。
重度の介助が必要な方には、つい身体を引きずって介助してしまいがちです。
引きずらないように注意喚起をしてください。
体位変換時にはスライディングシートを活用する方法も伝えておきましょう。
③圧を抜きシワも直す
衣服やシーツのシワも褥瘡を悪化させる原因になります。
特に更衣や体位変換のあとは、シワができていないか確認します。
またギャッジアップ後は、背中や足がベッドに接している部分に手を入れて圧を抜くことを必ず伝えましょう。
ポジショニング
ポジショニングには以下の目的があります。
- 褥瘡部位の除圧:圧迫とずれを減らし、褥瘡の予防・悪化防止を図る
- 安楽な姿勢の保持:利用者さんがリラックスできる姿勢を保つ
適切なポジショニングをおこなえば、過度な筋緊張が抑えられ関節拘縮の予防にもつながります。
また、終末期の利用者さんには疼痛を軽減する効果も期待できますので、これらのポイントを家族にしっかりと伝えましょう。
ポジショニングの基本的な考え方は以下の通りです。
- 体のねじれを防ぐ:肩甲骨と骨盤が平行になるように整え、上半身と下半身のねじれをつくらないようにする
- 隙間を埋める:身体が安定するように、タオルやクッションを適切に配置する
家族への具体的な指導方法は以下のようにおこないましょう。
- 写真を使う:ポジショニング後の状態を写真に撮り、わかりやすいポジショニング表を作成する
- スマートフォンを活用する:スマートフォンを使う家族も増えているため、ポジショニング後の写真を保存してもらう
ポジショニングはわかりやすく指導することが重要です。
家族が実践しやすいように丁寧に説明しましょう。
腰痛対策
自宅介護をしていて、腰痛に悩む家族は少なくありません。
腰痛が起こりやすい原因や対策を家族に伝えることは、介護を続けるうえでとても大切です。
腰痛予防の3つのポイントを以下で解説します。
①中腰姿勢を避ける
中腰姿勢は楽に感じるため、ついとってしまいがちですが、実は腰への負担が非常に大きい姿勢です。
この姿勢を避けるために、以下を指導してください。
- 昇降式ベッドを活用する:ベッドの高さを調整し、中腰姿勢をとらなくても介助できることを説明する
- 正しい介助姿勢をとる:足を肩幅程度に広げ、膝を曲げて重心を低くする方法を指導する
②体を密着させる
重い物を持つ際に体から離すと腰への負担が増えるのと同様に、介助も相手との距離が遠いほど負担が大きくなります。
そのため、移乗介助の際は利用者さんと体を密着させておこなうことを伝えましょう。
③利用者さんの力を利用する
介護者が必要以上に力を入れてしまう場合があります。
特に力に自信のある男性介護者に多い傾向です。
しかしこのような介助方法は、利用者さんの残存機能の低下を招くだけでなく、介護者自身の腰痛の原因にもなります。
そのため介助の前には必ず声をかけ、できる部分は利用者さんにも協力してもらいながら介助をするように指導しましょう。
まとめ

今回は、リハビリ職がしておきたい家族指導のポイントを解説しました。
私たちが利用者さんに普段おこなっていることは、知識のない方にとって大変難しいものです。
家族指導は、難しいことを「誰でもできるようにわかりやすく伝えること」が大切です。
本記事を参考に、家族指導を積極的に実践してみてください。

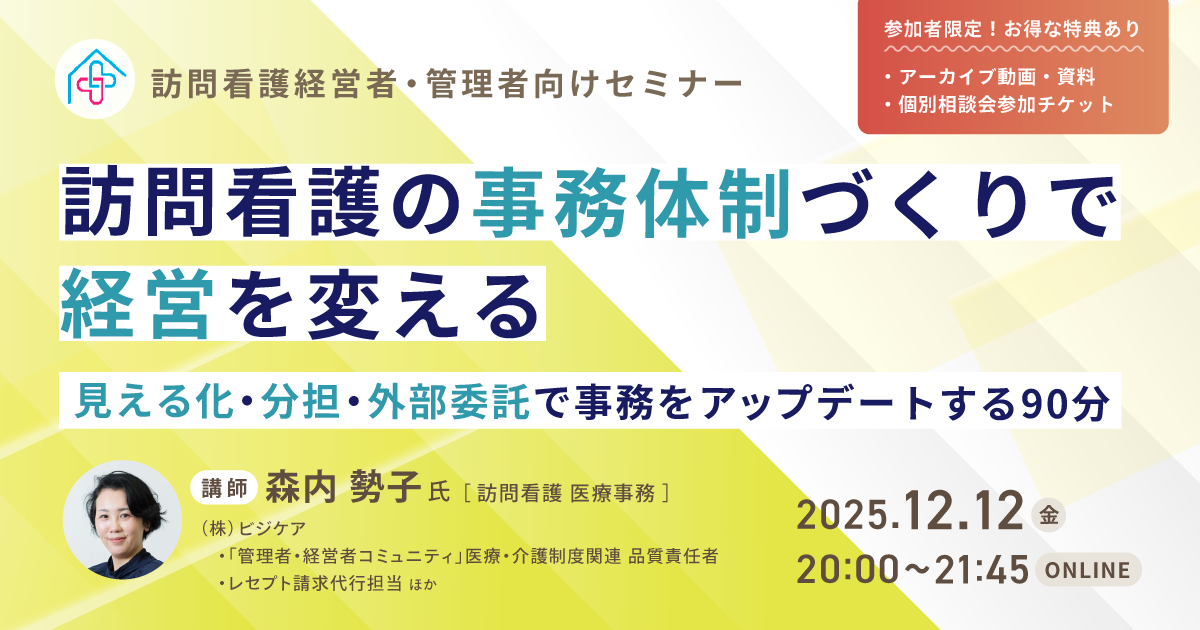

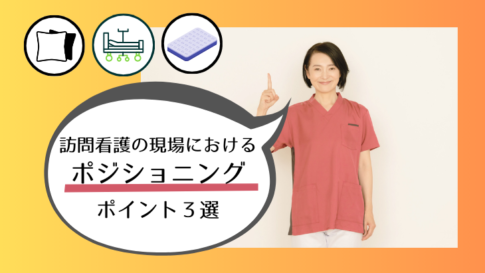
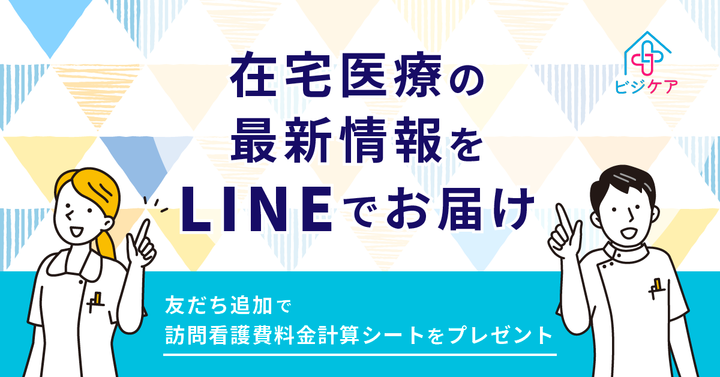

-150x150.png)