
訪問看護管理者さんで、このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、実際の書類作成の準備も交えて、運営指導の対策の最新情報をご紹介します。
管理者さんやマネージャーさんは、ぜひ参考にしてみてください!
目次
訪問看護|運営指導対策が不十分だと起こり得るリスク
以下に訪問看護ステーションで運営指導対策(運営指導への準備・体制づくり)が不十分な場合に起こり得る主なリスクを、整理してお伝えします。
1. 指摘事項が多くなり、改善指導や追加資料提出が必要になる
記録不備、契約書の漏れ、アセスメントの不足などがあると、場合によっては指導後に大量の修正や追加書類の作成が必要となり、通常の業務が圧迫されます。
2. 指定取消・報酬返還などの行政処分のリスク
不正請求や基準違反があったと判断されると、最悪の場合は指定取消・停止処分、過去分の返還命令が出る可能性があります。
たとえば以下が典型です:
人員基準(常勤換算2.5)未達
訪問実績の虚偽記載
必須項目の記録欠如
二重請求・誤請求の放置
3. 報酬請求の減算・返戻が増える
書類不備が多いと、審査機関から返戻が増え、結果として入金遅延や減算につながります。
4. 職員の負担増・離職リスクの上昇
指導直前に慌てて記録を修正したり、膨大な資料を準備したりすることで、スタッフの精神的負担が大きくなります。
特に管理者やリーダー看護師の離職につながりやすく、人員基準を満たせなくなる → さらに運営が危険に という悪循環を招きます。
5. 利用者・家族からの信頼失墜
指導で問題が表面化すると、地域包括支援センターやケアマネの耳に入り、「あの事業所は運営が不安定」という印象を持たれ、紹介が減ることがあります。
6. 事故・トラブル発生時の説明責任が果たせない
記録が整備されていないと、事故やクレームが起こったときに適切にケアを行っていたことを証明できないため、事業所側が不利になりやすくなります。
7. 管理者の評価・信頼が下がる
特に法人内で新規事業所を立ち上げる場合、運営指導で指摘が多いと管理者としての「管理能力に欠ける」と判断され、昇進・役職任命・事業を任せたい案件などに影響することがあります。
訪問看護の運営指導で特に指摘されやすい項目一覧
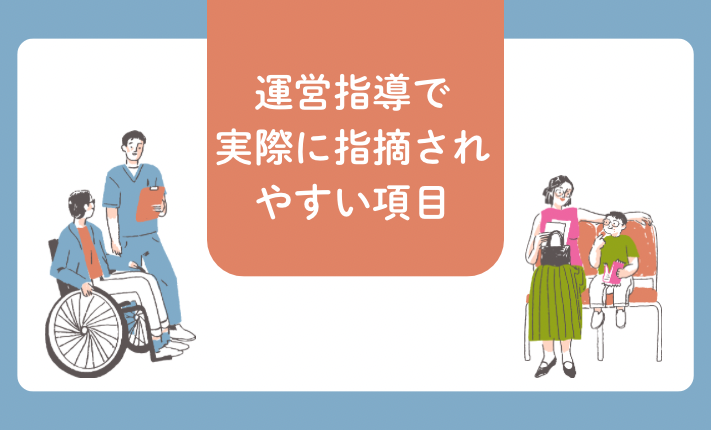
以下に、訪問看護ステーションの運営指導で “実際に指摘されやすい項目” を、できるだけ現場に即した形で詳しくまとめます。
(※自治体により多少異なりますが、全国的に共通して起こりやすいもの)
【A. 書類・記録に関する指摘】最も多い領域
1. 利用者ごとの契約書・重要事項説明の不備
- 署名・押印漏れ
- 日付が不明または前後関係が矛盾
- 保管が分散し、最新のものが確認できない
2. アセスメントの不足・形式的な記載
- ニーズが十分に描かれていない
- リスク要因(誤嚥・転倒・褥瘡など)の評価が曖昧
- 医師指示書の内容と看護のアセスメントが結びつかない
3. 訪問看護計画書の内容不備
- 目標が抽象的(例:”安定した在宅療養”など)
- 具体的な援助内容と頻度が書かれていない
- リスク管理の方針の記載が不足
4. 報告書・実施記録の不備
- 内容が明らかなコピー&ペーストになっている
- 看護記録なのに「事実」「評価」「今後の予定」がなど不足
- 医療と介護保険の境界が曖昧
【A : 目標が抽象的で、評価できない】 「安全に在宅生活ができること」など、曖昧な目標のみ。運営指導で「介入の妥当性や成果が判断できない」と指摘。 結果、計画の全面修正が必要になり業務が滞った。 【B : 必要な援助内容が計画書に書かれていない】 CVポート管理が必要な利用者だが、計画書に記載なし。 医療行為を行っているのに計画化されていないため、特別管理加算の請求が不適切と判断され返還が発生。 【A : 有効期限切れの指示書で訪問を続行】 更新依頼を忘れ、1か月指示書が切れたまま訪問していた。 指導で発覚し、指示書がない期間の訪問が全額返還。 【B : 主治医変更後の手続き漏れ】 利用者が入院後に主治医が変わったが、事業所は前医の指示書のままで継続訪問。 “無効な指示での訪問”として返還・行政指導の対象に。 リスク:個人情報保護違反・システム改善の強制 リスク:加算の取り消し 【A : ファイルはあるが実態が伴っていない】 事業所内に「虐待防止」「事故防止」「感染対策」「衛生管理」の指針をまとめたファイルは保管されているが、内容は開設時に作成したまま更新されていない。 スタッフは「見たことがない」「どこにあるかわからない」という状態で、周知した証拠も残っていない。 運営指導で「形式的であり実施体制が整っていない」と判断され、改善計画の提出を求められた。 【B : 研修を実施していても記録が残っていない】 実際には年に何度か感染対策や虐待防止について話し合っているが、毎回「口頭での説明のみ」で、研修記録や出席簿が残っていなかった。 運営指導で「研修を行ったことを証明できる記録がなく、義務である年1回以上の研修実施を確認できない」と指摘され、研修の再実施と記録作成の指示が入った。 ターミナルケア加算の請求根拠不足 ACP(意思決定支援)の記録不足 苦痛管理(疼痛/呼吸苦)に関する評価不足 訪問看護で書類の不備があると、返還・苦情・説明責任の欠如・加算否認・専門職としての評価低下などの重大なリスクにつながります。 特に以下は運営指導で必ずチェックされるため、日常的な整備が重要です。 訪問看護では、契約書や指示書、アセスメント、日々の記録などの書類が、利用者さまの安心と事業所の信頼を支える大切な土台になります。 もし書類に小さな抜けや曖昧さが残っていると、後から「ここが分かる記録があれば安心でしたね」といった指摘が入ったり、加算が認められないなど思わぬ影響が出ることがあります。 書類が丁寧に整っていると、看護の意図や判断が伝わりやすく、スタッフも安心してケアに集中できます。 結果として、利用者さま・ご家族・関係職種との信頼関係もより穏やかに築かれていきますね。 ビジケアには、組織のマネジメントなど「訪問看護経営の課題解決の支援」を行う訪問看護経営サポートというサービスがあります。 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 \詳細はコチラ!/ 工夫と仕組みづくりが笑顔で働ける職場づくりには大切なんですね。 まずは、今日できる小さな一歩から始めてみましょう 5. 医師の訪問看護指示書の管理不備
6. 情報管理・保存ルール違反
7. 24時間対応体制(オンコール)の記録不足(医療保険)
8. 指針(虐待防止・事故防止・衛生管理・感染対策)の未整備
B. ターミナルケアに関する指摘
まとめ

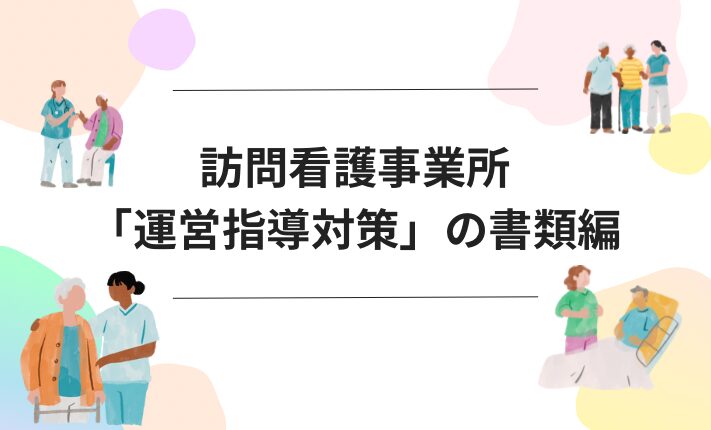

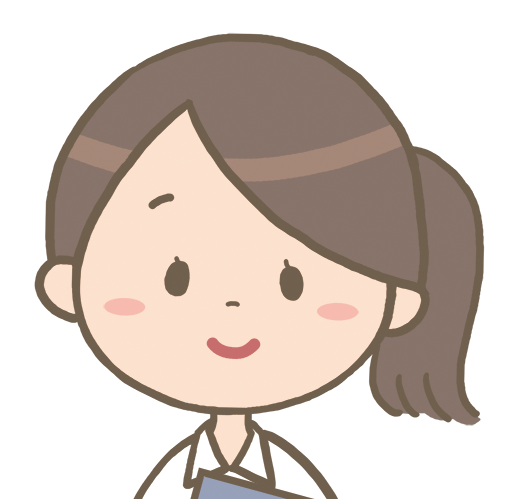
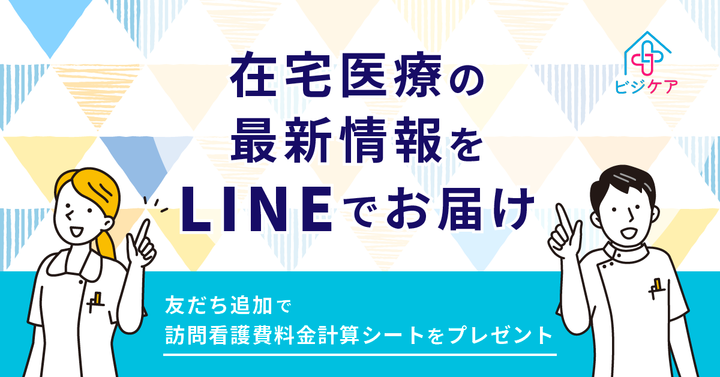
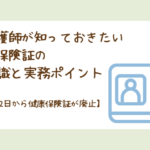


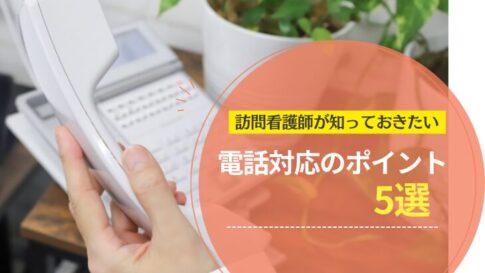
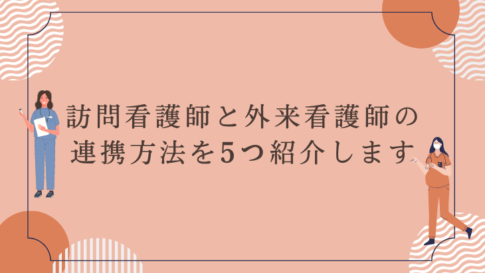

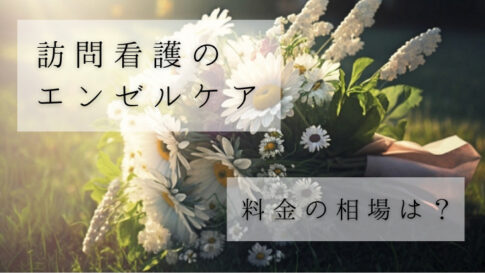
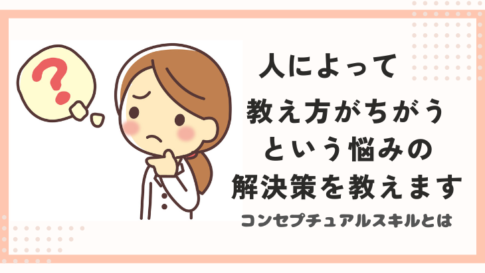

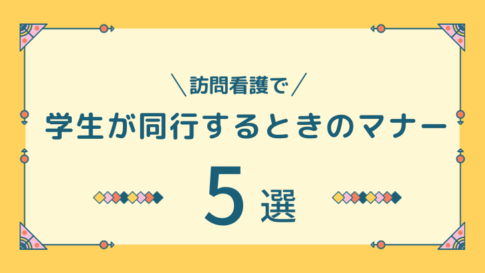

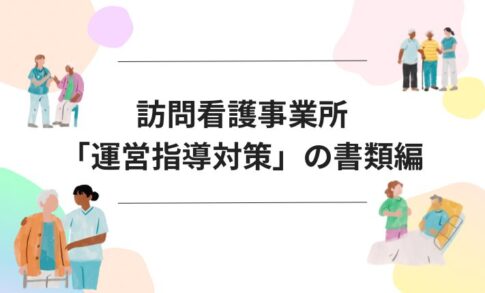
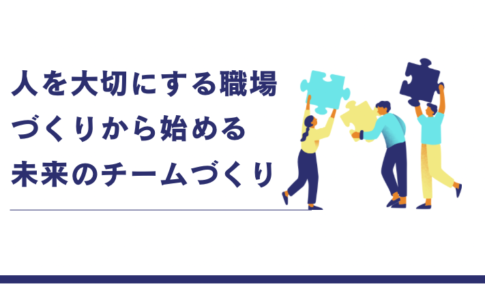
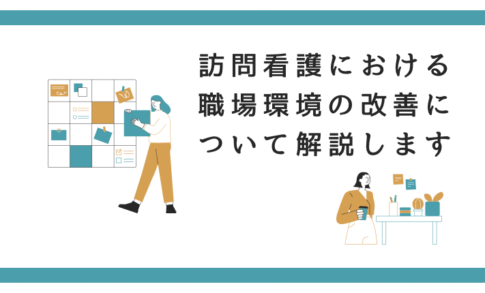
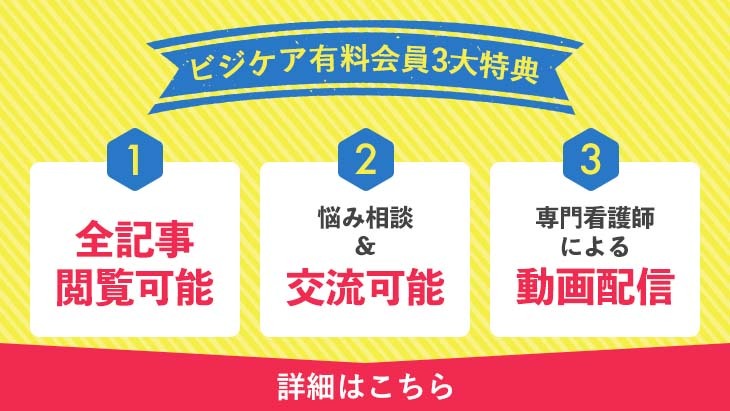

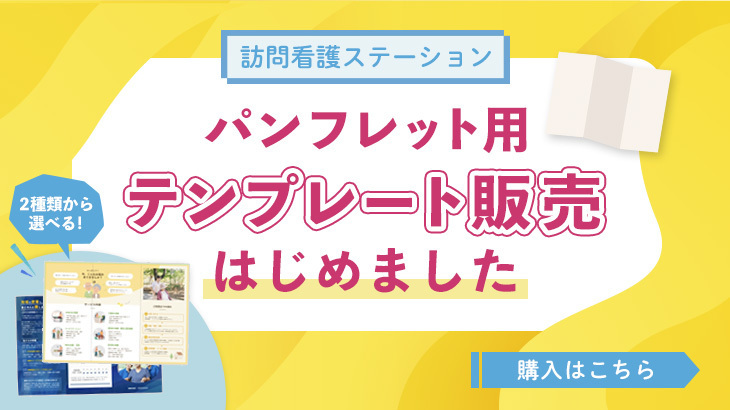
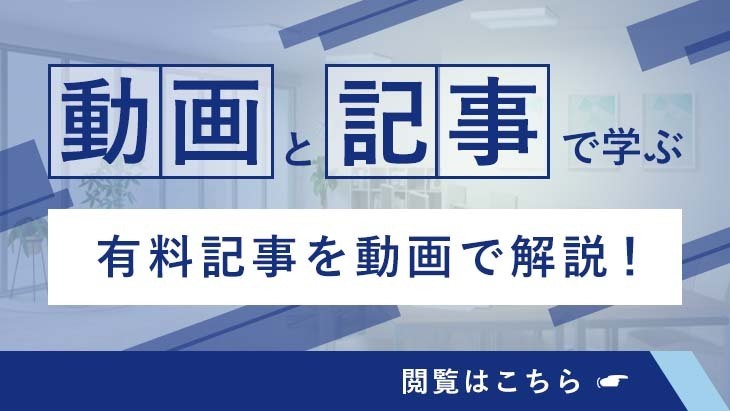
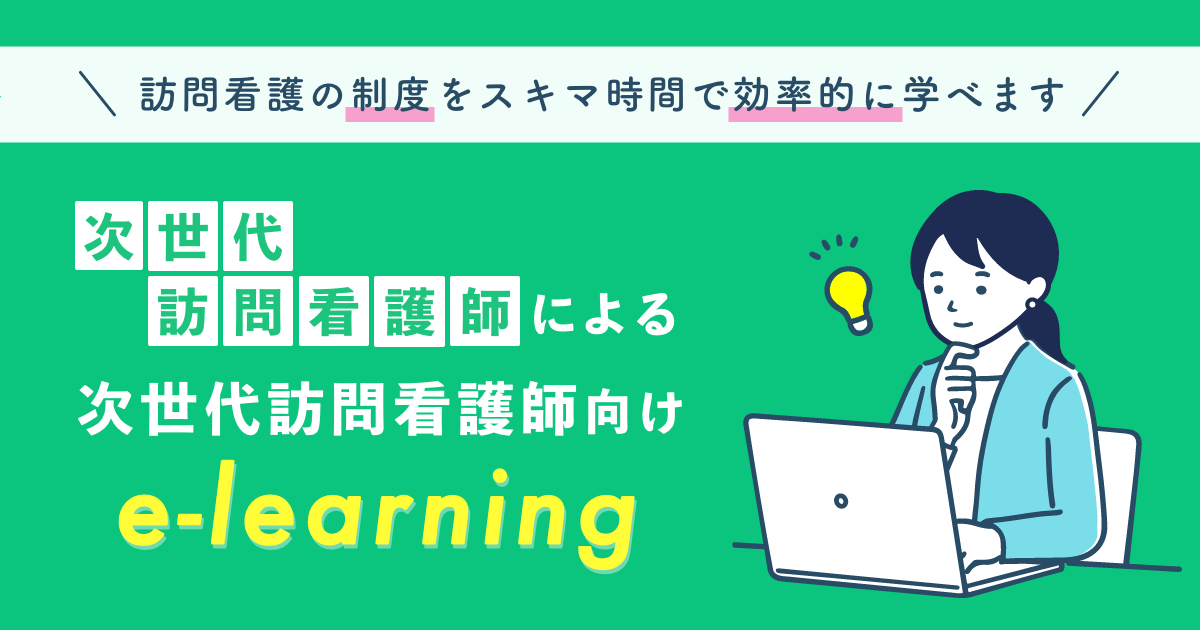
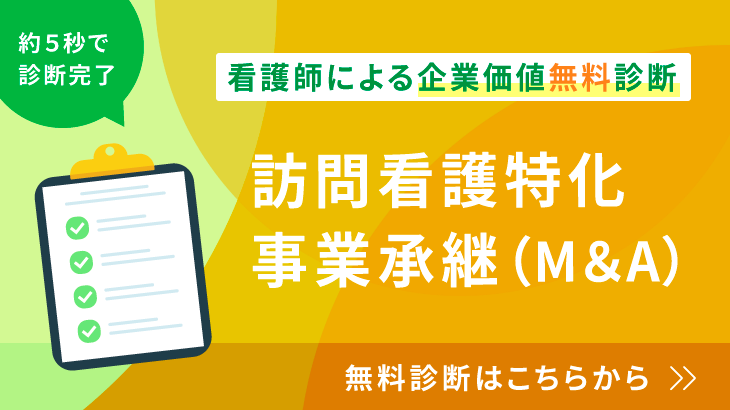
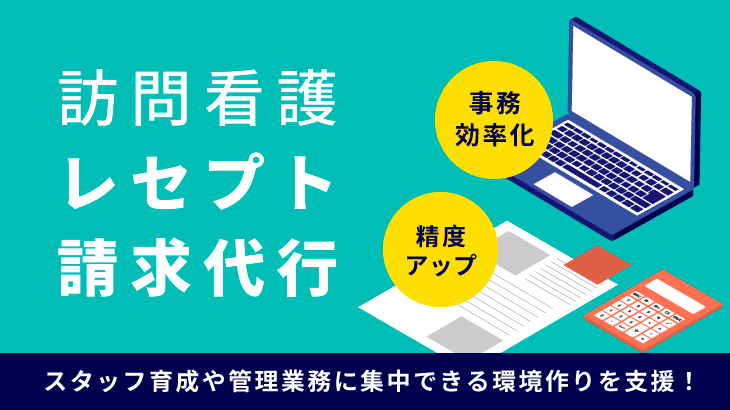

訪問看護ステーションでの「運営指導対策」には何があるかな?
揃えておきたい必要な書類は何があるのかな…。