
訪問看護管理者さんで、このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
在宅医療の需要が高まる中、訪問看護事業所では「採用しても続かない」「応募が少ない」といった声が多く聞かれます。
しかし近年、工夫と仕組みづくりによって“人が集まり、育ち、定着する”事業所も少しずつ増えてきました。
ここでは、行政の支援情報を踏まえながら、実際の成功事例も交えて、採用と定着を両立させるための最新戦略を紹介します。
最新情報を知りたい管理者さんやマネージャーさんは、ぜひ参考にしてみてください!
目次
社会の流れと支援制度の活用
人材不足と離職の連鎖
訪問看護は、高齢化と在宅療養支援の拡大により需要が急増しています。
厚生労働省や都道府県では、「人材を確保し、働きやすい職場をつくる」ための支援を強化中です。
例えば、愛知県では「職場環境改善支援事業」により、研修費やICT導入費の補助を受けられる制度があります。
こうした支援を活用して教育・ICT・福利厚生の整備を行うことは、人材確保に直結します。
名古屋市内のある訪問看護ステーションでは、ICT導入補助を活用し、クラウド型記録システムを導入。 訪問後すぐにスマートフォンで記録が完結するようになり、スタッフの帰宅時間が平均で1時間早まりました。 この“働きやすさ”が口コミで広がり、紹介による応募者が増加しています。 いま求められているのは、自社らしさを言葉と映像で発信することです。 「どんな想いで訪問しているのか」「どんなチームで働いているのか」をSNSやホームページで丁寧に伝えると、共感による応募が増えます。 あるステーションでは、スタッフが登場する短い動画をInstagramに定期投稿しています。 「1日の流れ」「イベントの様子」「利用者さんの笑顔や温かいやり取り」など、日常をそのまま見せることで、応募前から職場の雰囲気が伝わり、採用面接時のミスマッチが減少しました。 訪問看護の魅力は、勤務時間や働き方の自由度が高いこと。 子育て中の看護師、ブランクのある方、地域でゆっくり働きたいベテラン層など、ターゲットごとに伝え方を変えることが採用成功のカギです。 ある事業所では、「週3日・1日4時間からOK」「オンコールなし」の求人を出したところ、長年病棟を離れていた40代・50代の看護師が複数応募。 「少しずつ現場に戻れる安心感があった」との声が多く、結果的に常勤登用につながりました。 見学や現場体験の導入は、早期離職の防止に効果的です。 応募者が現場の雰囲気や訪問の流れを体感することで、「自分でもできる」「ここなら働けそう」と実感できます。 ある訪問看護ステーションでは、応募者の希望者に半日同行体験を実施。 実際の訪問やカンファレンスを見てもらうことで安心感を高め、体験後の内定承諾率が上がりました。 訪問看護では、移動や記録といった業務の負担が積み重なりがちです。 まずは業務の棚卸しを行い、誰がどこに時間を使っているかを可視化しましょう。 記録フォーマットの統一やICT活用によって業務を軽減することができます。 あるステーションでは、訪問ルートを地図アプリで自動最適化する仕組みを導入。 移動時間が1日あたり30分短縮され、スタッフのストレスが減少。「体力的に続けやすくなった」と好評です。 訪問看護の仕事は、ライフイベントとの両立が課題になりやすい職種です。 短時間勤務、時差出勤、オンコール免除など、柔軟な勤務制度を導入することが離職防止に効果的です。 ある事業所では、子育て中のスタッフのために「保育園のお迎えに間に合うよう16時まで勤務」や「日曜休み固定」など個別シフトを導入。 「制度で守られている安心感」がスタッフの定着に直結しました。 訪問看護は幅広い知識が求められるため、教育体制の有無が定着率を左右することがあります。 OJTやメンター制度を設け、困ったときに相談できる環境を整えることが大切です。 さらに、段階的なウェブ研修プログラムを整備し、スキルアップを実感できるようにします。 あるステーションでは、入職後6か月間は先輩が定期的に同行し、訪問後に「振り返りシート」を一緒に記入。 「安心して失敗できる環境」が育ち、若手の定着率が飛躍的に向上しました。 訪問看護は一人で訪問する場面が多く、孤立感を抱きやすいです。 そのため、「困ったときに相談できる雰囲気」を意識的に作ることが重要です。 あるステーションでは、月1回「お茶会ミーティング」を開催。 業務報告ではなく、雑談を中心としたお茶会形式にすることで、スタッフ同士のつながりが強まりました。 「気持ちを共有できる時間があることで、安心感もうまれ、また明日も頑張ろうと思える」と好評です。 ICT導入は、業務効率化だけでなく「安心して働ける仕組みづくり」にもつながります。 訪問スケジュールの共有、リアルタイム記録、緊急時の連絡システムなどを整えることで、スタッフの負担を減らし、チーム全体の安心感が増します。 あるステーションでは、スマートフォンで訪問内容を記録・送信できるシステムを導入。 管理者がリアルタイムで状況を把握できるようになり、新人ナースも安心して単独での訪問できるようになりました。 人材確保を事業所だけで解決するのは難しいため、地域全体での協力体制が求められています。 看護学校・病院・訪問看護ステーションが連携し、学生の実習や復職支援セミナーを共同開催するなどの取り組みが全国で少しずつ広がっています。 とあるエリアでは複数のステーションが協力して「訪問看護1DAY体験」を実施。 学生やブランクのある看護師が訪問現場を体験できるイベントを開催し、その参加者の数名がその後実際に応募しています。 訪問看護の魅力は、利用者とじっくり関われるやりがいと、働き方の自由さにあります。 その魅力を最大限に活かすためには、「人を採る」よりも「人を育て、守る」仕組みが欠かせません。 現場を支えるのは、人の手と心。 一人ひとりが安心して笑顔で働ける職場づくりこそが、結果的に利用者へのより良いケアにつながります。 これからの訪問看護は、「人を大切にする組織づくり」から未来を描いていく時代といえますね。 ビジケアには、組織のマネジメントなど「訪問看護経営の課題解決の支援」を行う訪問看護経営サポートというサービスがあります。 興味のある方はぜひチェックしてみてください。 \詳細はコチラ!/ 工夫と仕組みづくりが笑顔で働ける職場づくりには大切なんですね。 まずは、今日できる小さな一歩から始めてみましょう 採用を成功に導く3つのポイント
自社の魅力を伝える「ブランディング採用」
ライフステージに合わせた採用設計
見学・体験で職場理解を深める
定着を支える職場づくり
業務負担を「見える化」して整える
働き方の柔軟性を高める
教育とキャリアを支える仕組み
心理的安全性のあるチームづくり
ICTで働きやすさをサポート
地域で支え合う人材育成
今すぐできる5つのアクション
まとめ

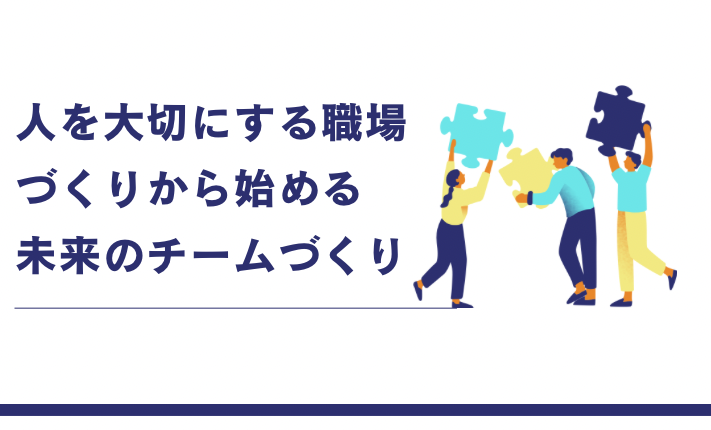
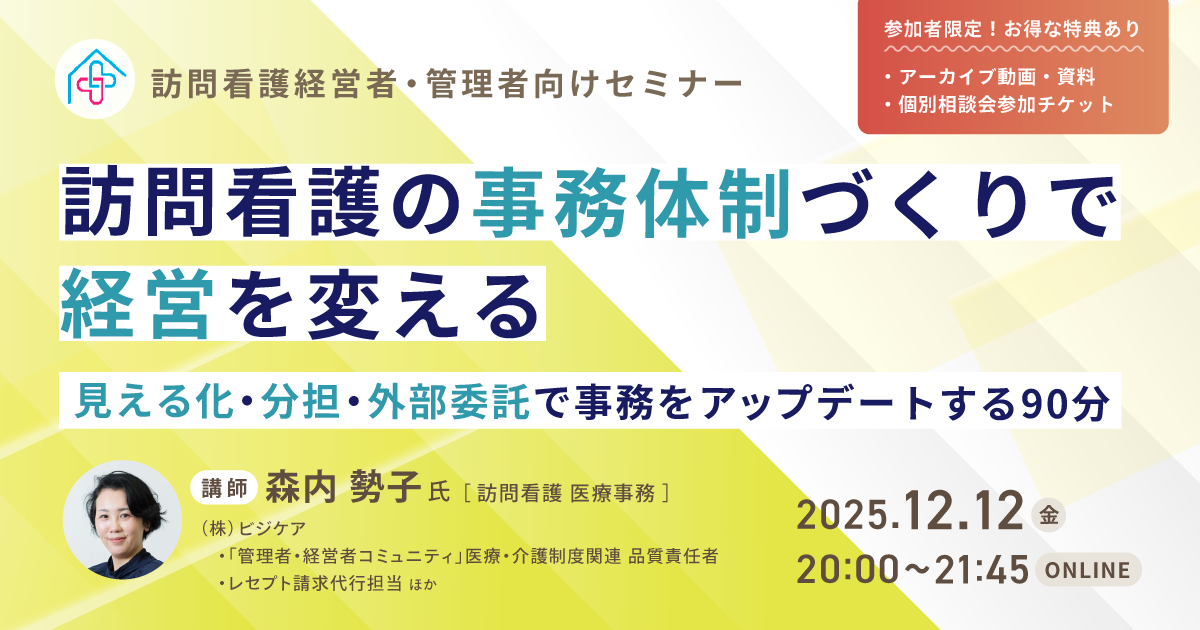
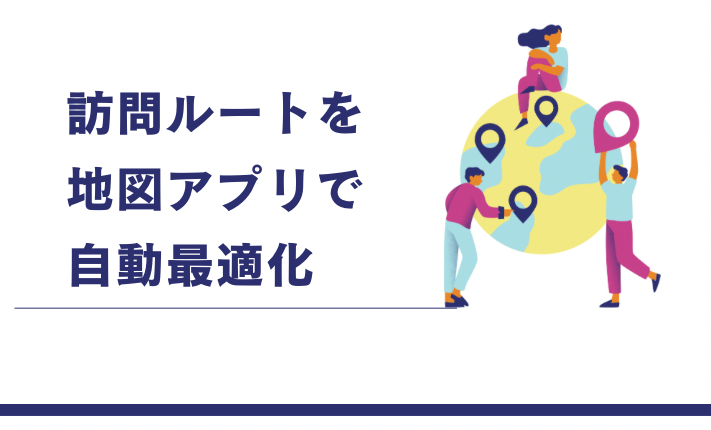
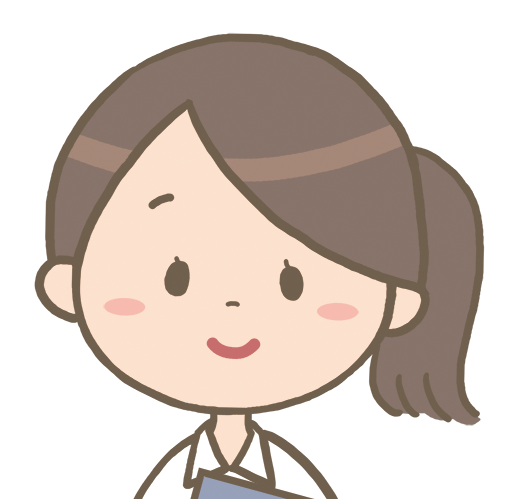
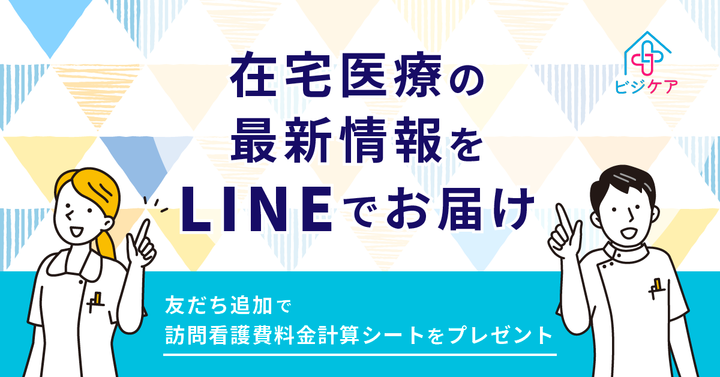
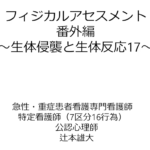

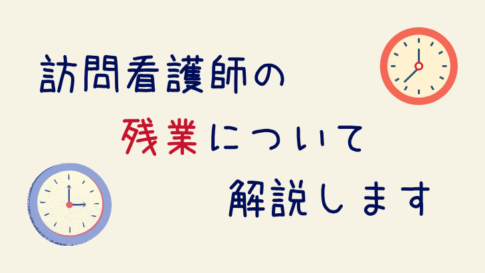




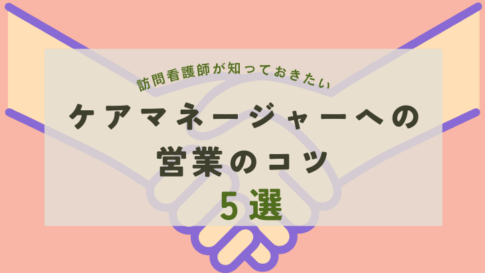

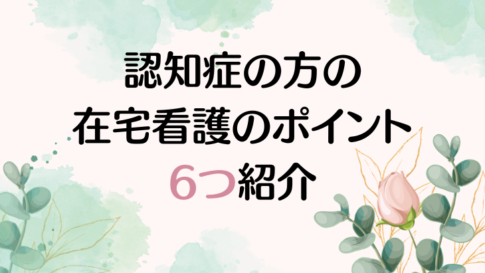
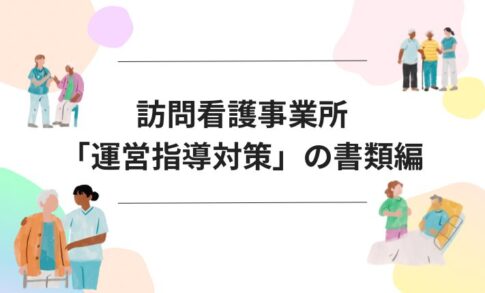
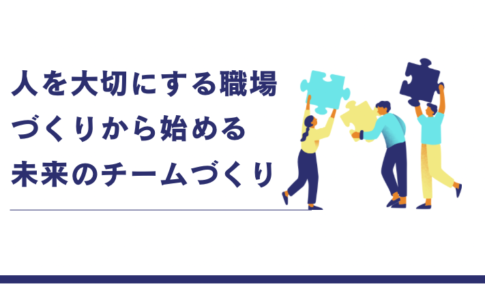
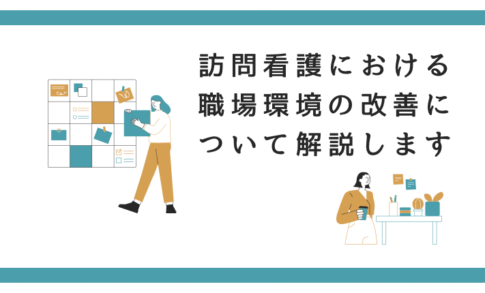

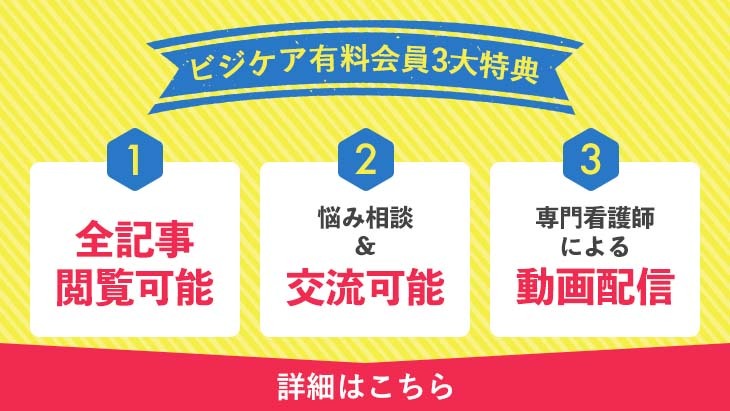

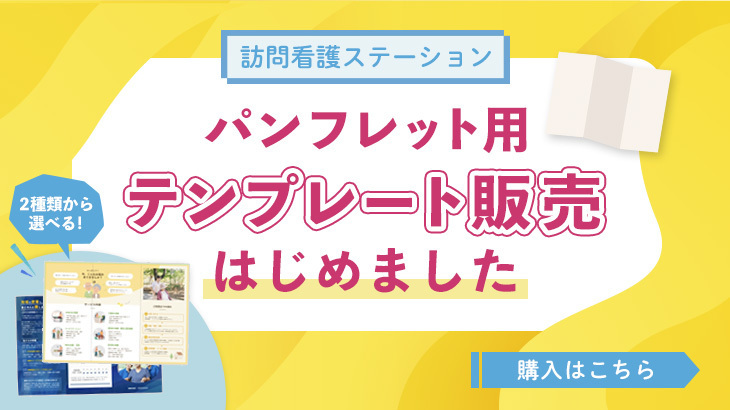
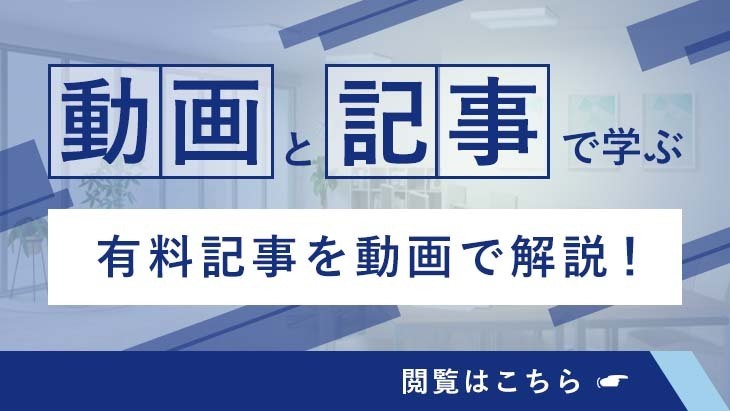
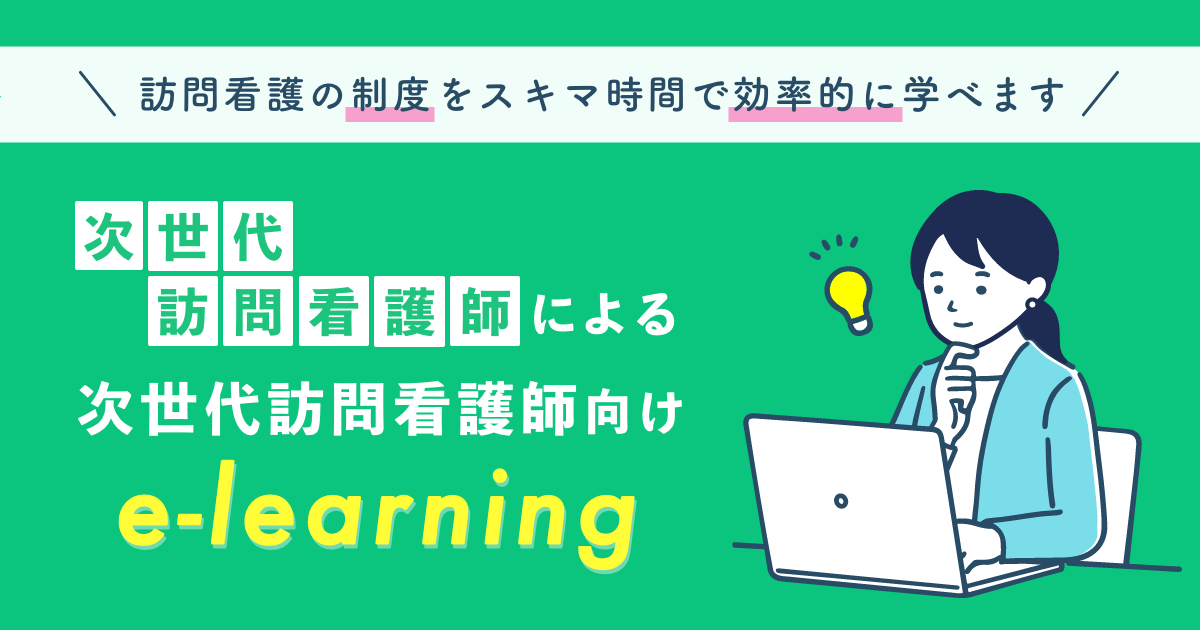
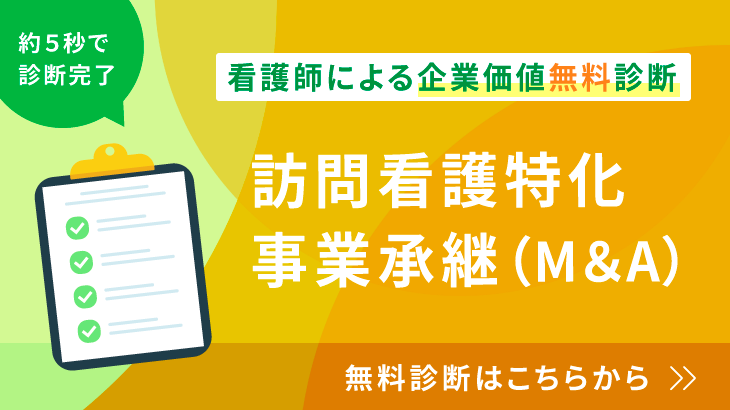
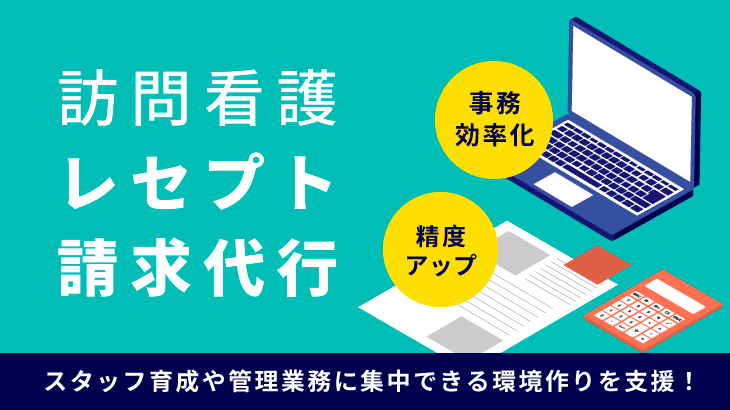

訪問看護ステーションでの「採用と定着戦略」には何があるかな?
よい解決策はあるのかな…。