訪問看護の現場では、利用者さんと家族が言い合いになっている場面に遭遇することがあります
「何度言ったら分かるの?」「そんなことしなくていい!」など、感情的なやりとりが始まると、看護師としてどう介入すべきか判断が難しくなります。
家庭内の問題である一方、言い合いが長引けばケアができず、利用者さんの安全にも支障が出ます。
本記事では、訪問看護における“プライマリ・ケア(初期対応)”として、利用者さんと家族の言い合いを仲裁する際のポイントや注意事項を具体的に解説します。
家庭内トラブルの介入に悩んでいる看護師の方に役立つ内容です。
目次
訪問看護が家庭内の言い合いに巻き込まれやすい理由

訪問看護では、家庭という閉ざされた環境でケアを行います。
家庭には長年積み重なった関係性や価値観があり、看護師はその場に“外部者”として入るため、言い合いや衝突が表面化しやすい状況に立ち会うことがあります。
1.介護負担が大きく家族が疲れている
介護疲れが溜まると、些細なことで言い合いに発展しやすくなります。
2.利用者さんの病気や認知症の影響
病気による行動変化、認知症による記憶障害や被害妄想は、家族との衝突を引き起こしやすい要因です。
3.価値観の違いや役割分担の不満
「誰がどこまで介護をやるのか」「方法はどうするのか」など、家族間の調整がうまくいかず言い合いが起こることがあります。
4.感情のぶつかり合い
長年の不満や感情が積み重なると、訪問看護の場で爆発してしまうこともあります。
家庭内の言い合いは、根深い原因が複数絡んでいるため、看護師は“第三者としての立場”を意識しながら対応することが必要です。
訪問看護で使える!言い合いを仲裁するためのポイント

1.まずは“中立の立場”で状況を見る
どちらかの味方をするような態度は避け、落ち着いた視点で状況を把握します。
「私はどちらの味方でもなく、安全にケアできるようお手伝いしますね」
と伝えることで、双方に安心感を与えられます。
2.声のトーンを下げ、場の空気を落ち着かせる
看護師が落ち着いた口調で話すだけで、感情的な場が少しずつ鎮まります。
「まずゆっくりお話を聞かせてくださいね」
と静かな声で介入することで、双方の注意をこちらに向けることができます。
3.“共通の目的”に話を戻す
言い合いがヒートアップしている時は、争点がズレていることがよくあります。
そこで
「お母さまの体調を良くするために、今日は◯◯のケアをしていきましょう」
「みなさんが安心して過ごせるように、まずは様子を見せてもらえますか?」
など、共通の目的に焦点を戻すと冷静さを取り戻しやすくなります。
4.“どちらの意見も理解できる”と伝え、感情を落ち着かせる
言い合いの場では、双方が「自分の気持ちをわかってほしい」と思っています。
そこで、
「お母さまの気持ちも、ご家族の気持ちもどちらもよく分かりますよ」
と伝えると、感情の高ぶりが和らぎやすくなります。
否定されていると感じると衝突が激しくなるため、まずは受容する姿勢が大切です。
5.一時的に会話を区切り、ケアを優先する方向へ誘導
言い合いが続くとケアが進まないため、
「ではまずバイタルサインだけ測らせてくださいね」
「処置を進めながら、お話しをまとめていきましょう」
と、ケアに移行する声かけで場を切り替えます。
看護師の行動がスイッチとなり、言い合いを一旦落ちつかせることができます。
6.必要に応じて“別室で話を聞く”
利用者さんが感情的になって疲弊している場合や、家族間の言い合いが激しい場合は、
「少し場所を変えてお話を伺いましょうか?」
と提案すると、感情のコントロールがしやすくなります。
同じ空間では刺激が続くため、物理的な距離を作ることは有効です。
7.家族の負担や本音を丁寧に聞き出す
家族の強い口調の背景には、
・介護負担
・不安
・怒り
・孤独
・罪悪感
など、複雑な感情が隠れていることがあります。
“否定せず聞き取る”ことで、家族も落ち着き、関係改善に向けた話がしやすくなります。
言い合いが起きた後のフォローも重要

1.利用者さんの気持ちを丁寧に受け止める
言い合いの後は疲労や落ち込みが出やすいため、
「先ほどは少し大変でしたね。お疲れはありませんか?」
と声をかけ、安心できる雰囲気を作ります。
2.家族にも“責めない言い方”でフォローする
家族の介護負担を否定せず、
「日頃からサポートされていて本当に大変ですよね」
と気持ちに寄り添います。多くの家族は“責められたくない”という気持ちがあります。
3.必要に応じてケアマネへ共有する
家庭内での衝突が続く場合、訪問看護だけで抱え込むのは危険です。ケアマネへ状況を報告し、サービス調整や介護負担軽減策を検討します。
4.他職種連携で負担を分散する
デイサービスの活用、ショートステイの提案、訪問介護との連携など、チームとして環境調整を行うことで、家庭内の緊張が和らぐ場合があります。
仲裁で“絶対にやってはいけないNG行動”

どちらかを責める
片方だけを否定すると関係性が崩れ、信頼を失います。
介入しすぎて家庭内問題に深入りする
看護師の介入領域を超えると、トラブルの原因になります。「医療的に必要な範囲」での対応が原則です。
感情的に反応する
看護師自身が感情的になると状況が悪化します。冷静でいることが最重要です。
すぐに結論を出そうとする
家庭内の言い合いは根深い問題が多く、その場だけで解決しようとすると逆にこじれることがあります。
まとめ|訪問看護の仲裁は“中立・冷静・目的の共有”がキーワード

訪問看護では、利用者さんと家族の言い合いに遭遇することは珍しくありません。
しかし、看護師が中立で冷静な立場を守りつつ、ケアという“共通の目的”に焦点を当てることで、その場を安全にコントロールできます。
訪問看護の場は家庭独自の文化や価値観に満ちており、トラブル対応は非常に繊細です。
今回紹介した“プライマリ・ケア”を意識して関わることで、信頼を損なわずに安全なケアが提供できるようになります。


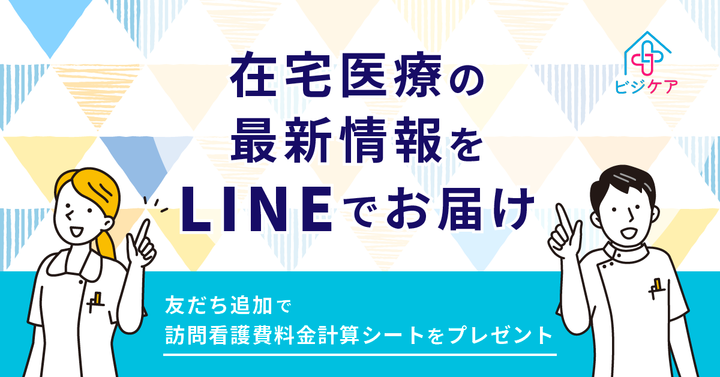



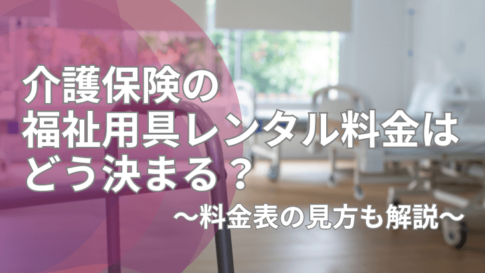
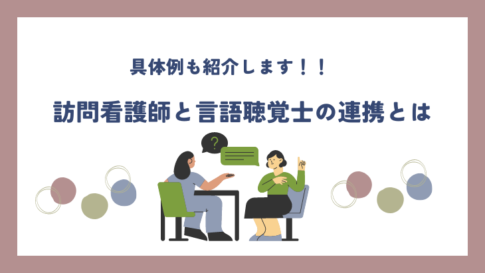



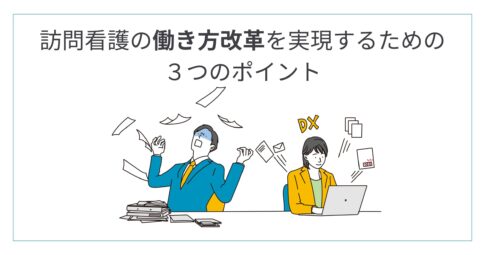
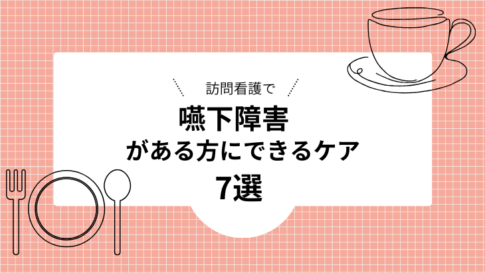
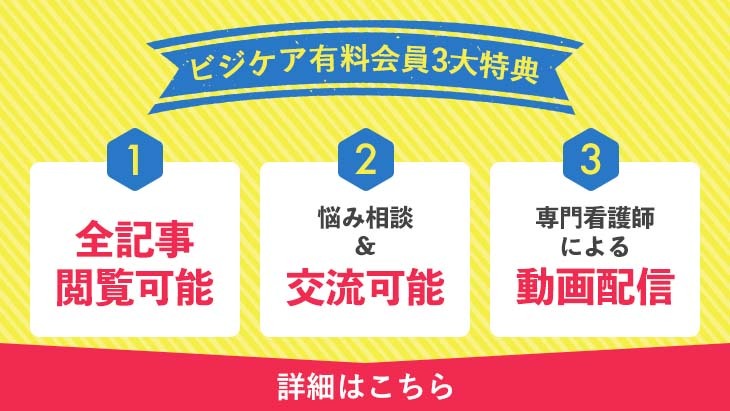

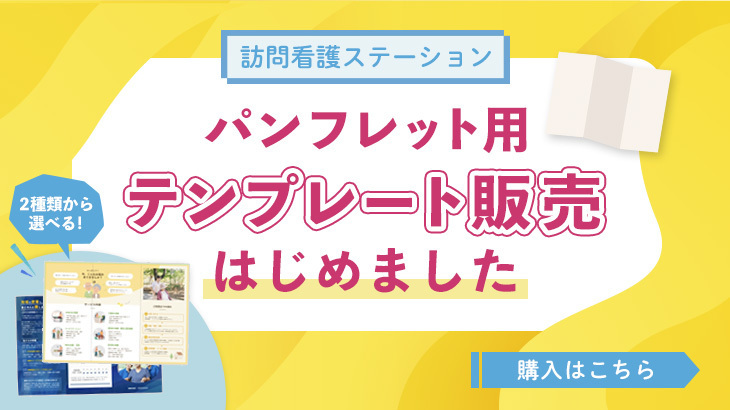
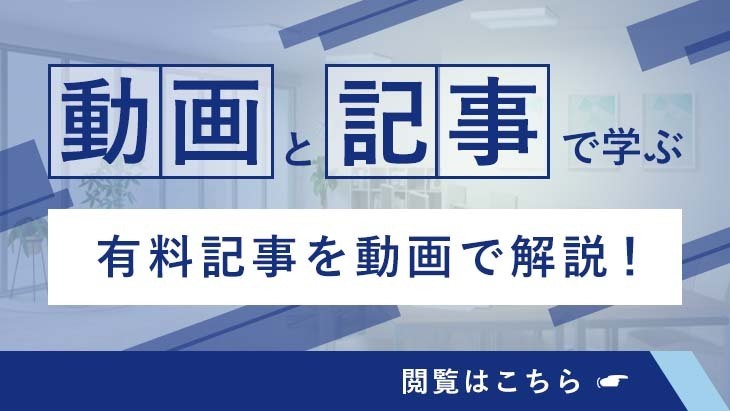
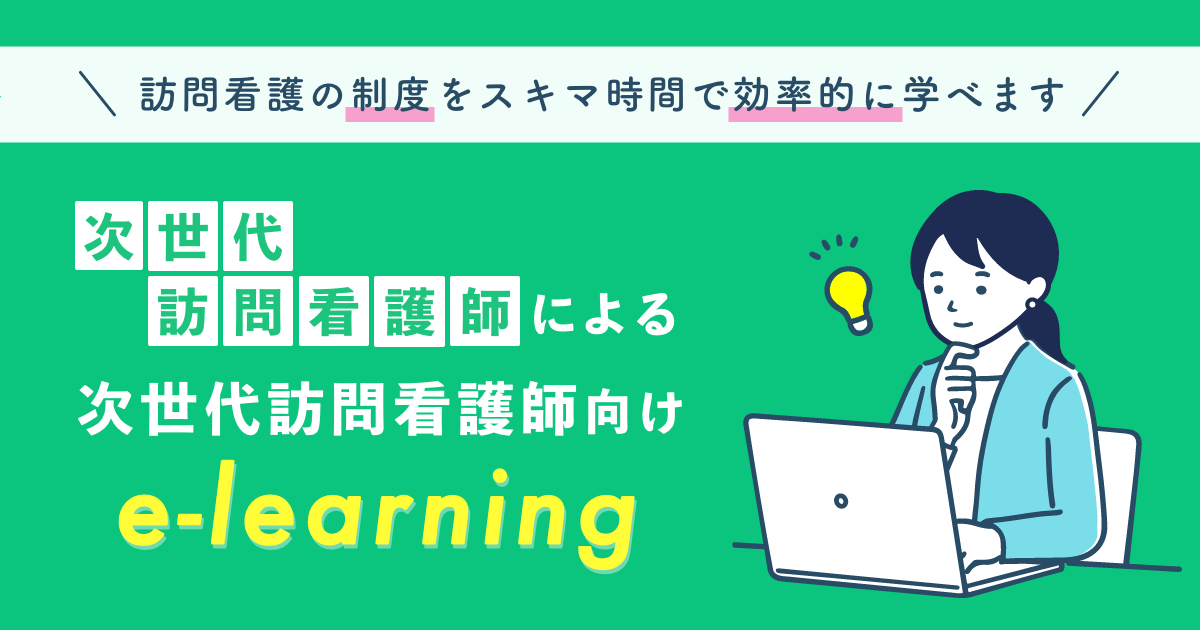
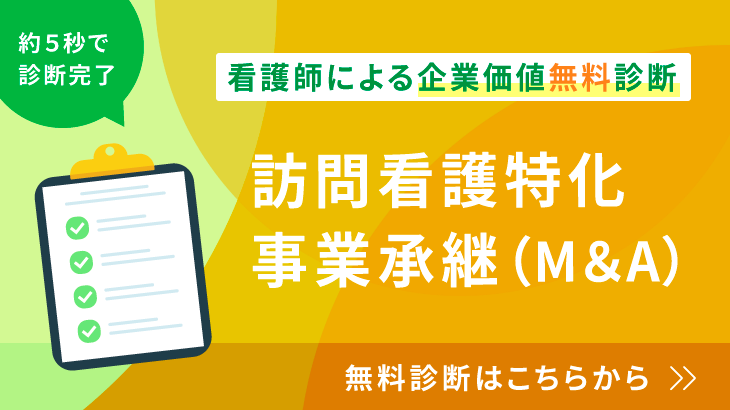
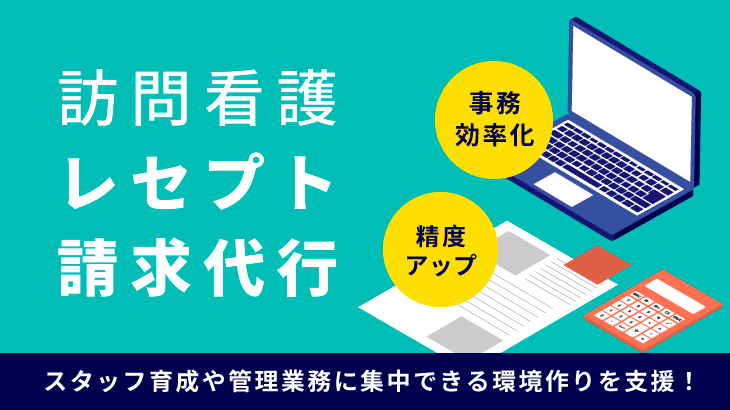

・声のトーンを下げ、落ち着かせる
・共通の目的へ話を戻す
・感情を受容し、否定しない
・ケアに移行するタイミングを作る
・家族・ケアマネへ連携する
・深入りしすぎない