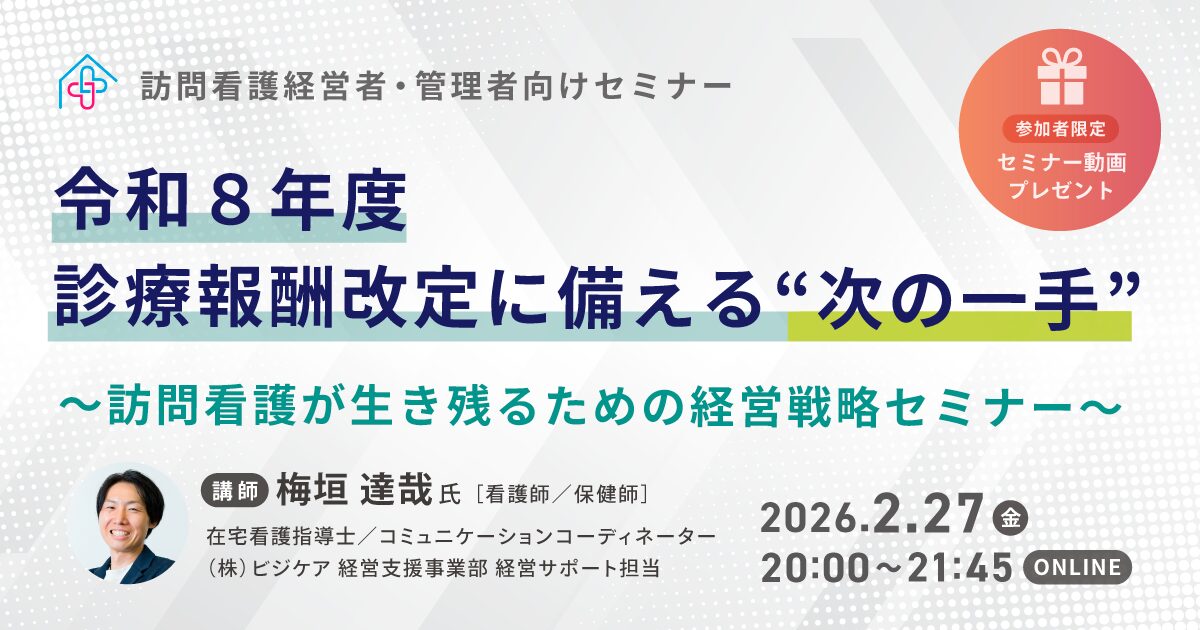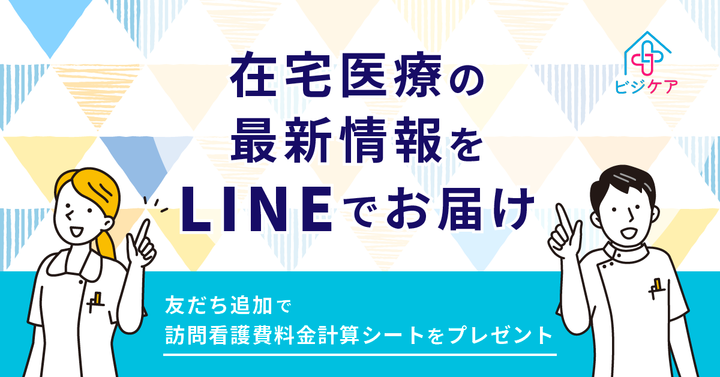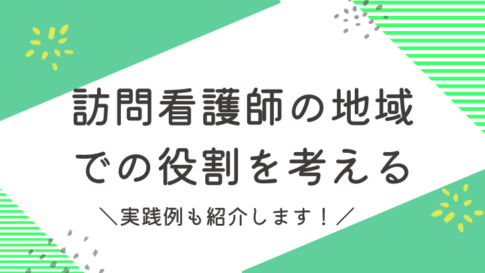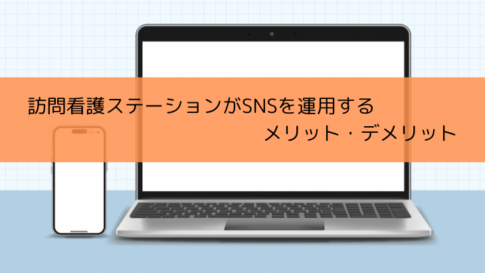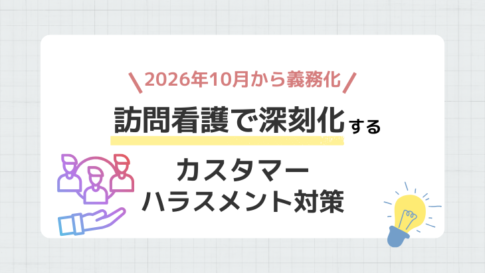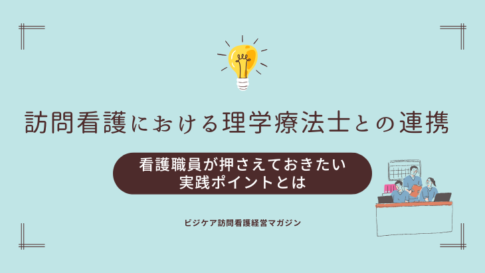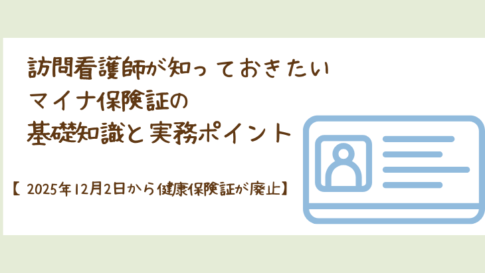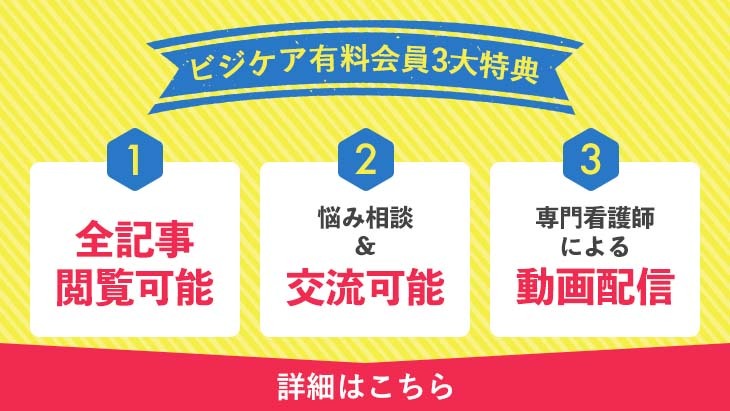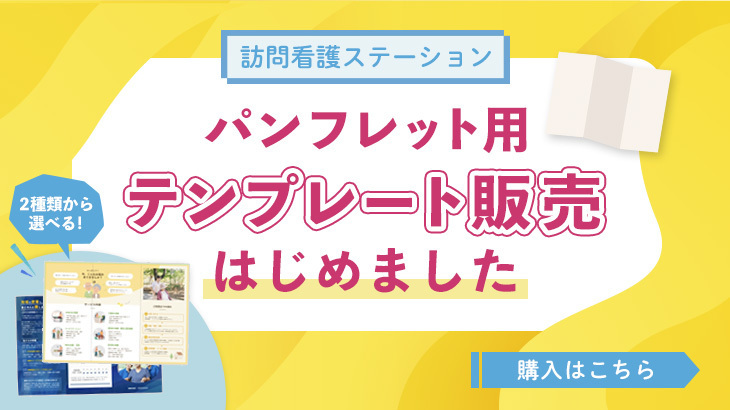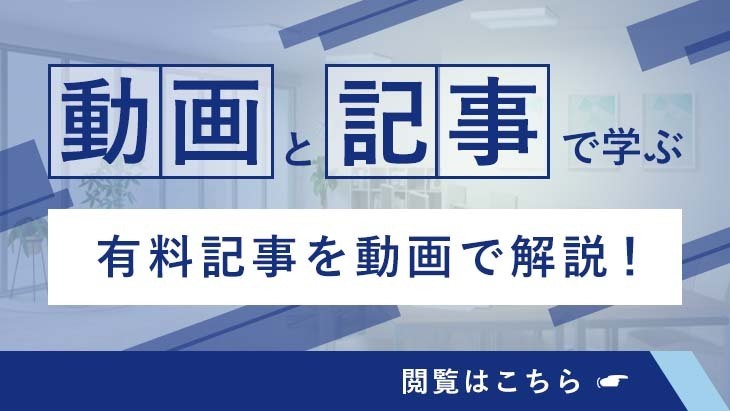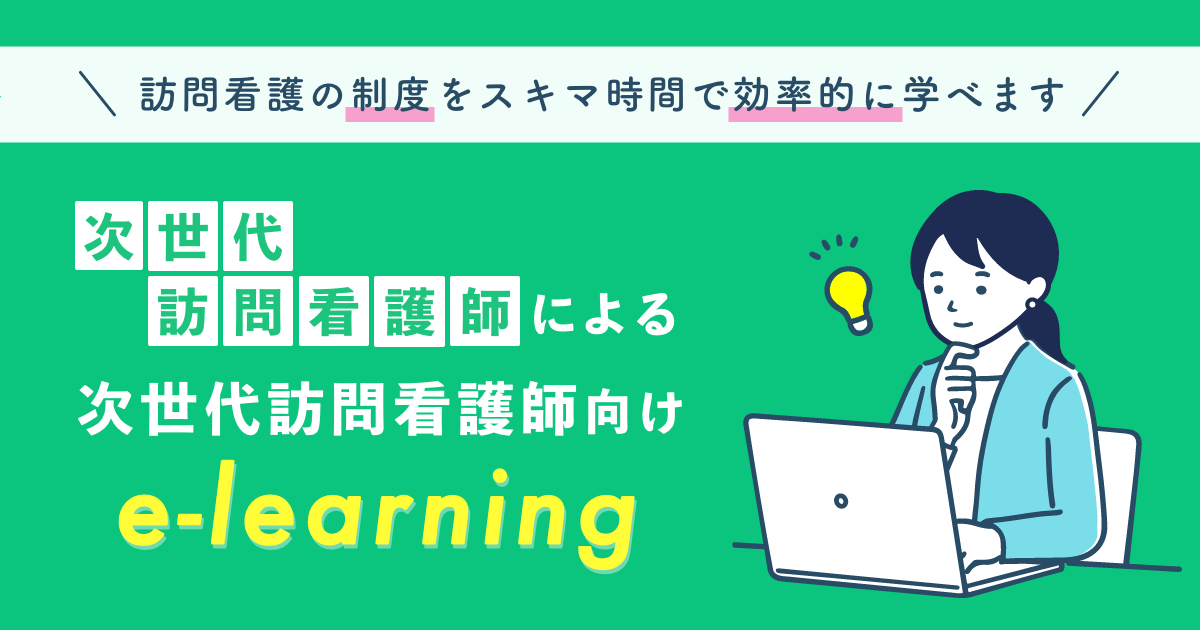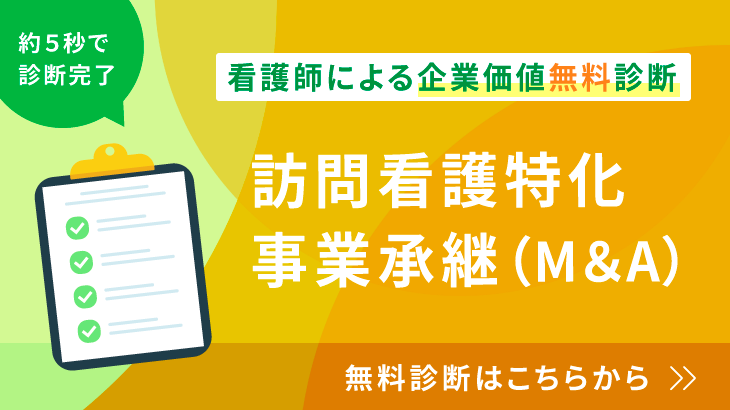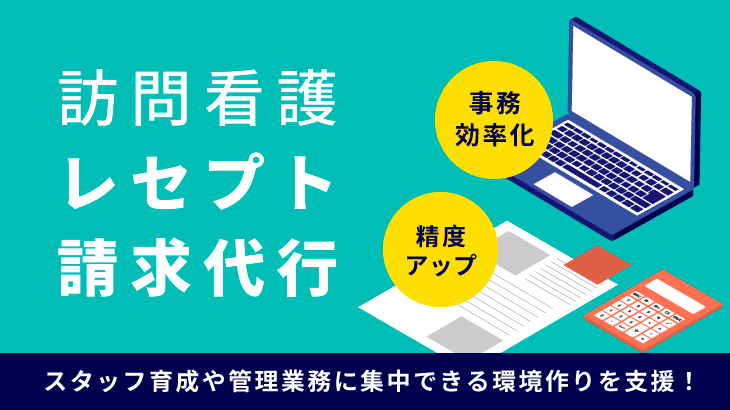訪問看護の現場では、スタッフ一人ひとりの判断と行動が利用者さんの暮らしに直結します。
個人の能力に頼り切る組織は、担当が欠けたときに脆弱になります。
この記事では「チームで回す」「主体的に動ける」訪問看護チームをつくるための考え方と具体的手法について解説します。
目次
訪問看護でなぜ今チームづくりが大事なのか?

近年の働き方や社会変化(VUCA時代、ITの進化、グローバル化、天災・疫病、情報習得の多様化)は、従来の「予定どおり進める」スタイルを変えました。
利用者さんや家族のニーズ、多職種連携、地域資源の活用など複雑性が増す中で、即時の判断と協働力が求められます。
また「お金だけでなく自分の力を社会に役立てたい」という価値観の広がりが、質重視・自己成長志向のスタッフを増やします。
チームづくりがうまくできれば、メンバーひとりひとりの承認欲求を満たし、仕事への意欲を向上させるとともに、業務上のミスを減らせます。
こうした変化がおきれば、チームが柔軟に学び合い、職場の生産性や定着率に差を生むことにつながっていきます。
チームづくりに原則「正解はない」
どの訪問看護事業所であってもチームの条件(メンバー構成、地域、勤続年数、職種構成、労働条件など)はすべて違います。
したがって「これが正解」という単一解はありません。
重要なのは自分たちの現実を丁寧に観察し、目的(より良いケア、効率化、職場の健康など)に合わせて仕組みを作り、柔軟に改善していくことです。
イノベーションが自然発生するチームの条件
イノベーションが自然発生するチームの条件とは以下のことがあります。
- 心理的安全性(失敗を共有できる雰囲気)
- 共通の目的意識(“なぜ”を共有)
- 分散型リーダーシップ(状況に応じて誰でもリーダーを取れる)
- 小さな実験(1か月単位のトライ&レビュー)
- 定期的な振り返りと成功の可視化(成功体験を積む)
一人のリーダーが頑張るだけでは限界があります。
判断に時間がかかる、モチベーションが続かない、といった理由でイノベーションは起きません。
チーム全体で判断・実行できる仕組みが必要です。
素早い行動にはOODAループで
OODAループとはもともとは戦闘機による戦闘の勝率を高めるために用いられた手法で、刻々と変化する不確実性の高い状況下での意思決定や行動に優れており、ビジネスシーンでも注目を集めています。
観察(Observe)→方向付け(Orient)→意思決定(Decide)→行動(Act)の4ステップ。
PDCAサイクルとは異なり、計画を立てるステップがないため、変化への即応性や柔軟性が高く、繰り返し回すことでより迅速で正確な意思決定ができるようになります。
- 観察:患者の状態・家の状況・地域資源・チームの稼働状況をリアルタイムで把握。共有ツールを活用。
- 方向付け:ケースごとの優先度やケア方針、リスクの整理。重要案件についての要旨説明や報告で視点を揃える。
- 意思決定:現場で判断できる権限を明確化(簡易な判断基準を用意)。
- 行動:決定を即実行し、結果を速やかにフィードバックして学習サイクルを回す。
このループを小さな単位で高速に回せるチームは変化に強く、イノベーションが自然発生しやすくなります。
訪問看護で「主体性」を育てる業務設計と空き時間の活用

主体性を引き出す業務とは「自己決定できる余地」と「学びの機会」がある仕事です。
訪問看護における業務設計の具体例は以下のとおりです。
- 空き時間の工夫:ケースノートの整備、地域資源リストの更新、訪問前のリスクチェック表作成、電話でのフォロー(実際の訪問以外での電話でのフォローアップ)、学習教材の短時間視聴、訪問前ミニカンファレンス。
- クロストレーニング:他職種間では、行動や言葉、現場の状況などを観察し、実際の業務やコミュニケーション、利用者への関わり方を理解する学習方法で互いの役割を理解し、代替可能性を高める。
- スキルバンク作り:得意・経験のあるスタッフをリスト化し、相談窓口を可視化する。
- チャレンジシート:教育プログラム導入による目標の可視化、各自の成長ゴールを書き、チームでフォローする(小さな目標→達成→共有)。
訪問看護|業務分担リストの実際
メンバーの能力を活かして目標を達成できる「チーム」を構築する取り組み(個人の成長に向けた成長循環づくりを支援する存在となる)には、今おこなっている業務分担をリスト化し、役割や権限(意思決定の範囲)を明確にする必要があります。
業務分担表とは、訪問看護事業所の業務における全体像を把握するための表です。
全体像は、訪問看護に携わるメンバーと担当する業務の全てを指します。
業務と担当メンバーの関係性が一目で理解できるため、業務内容の「見える化」に貢献する重要な表です。
また、業務分担表は、「なぜ今自分がこの役割を担っているのか」を把握できます。
チーム・事業所において、携わっている訪問看護業務の重要性と自身の状況を客観的に見られるため、たとえ与えられた仕事が簡単なものであっても、納得して業務に臨むことが期待できます。
| 役割 | 主な業務 | 権限(意思決定の範囲) | 担当・サブ担当(フォロー体制) |
| 訪問リーダー | 緊急対応・計画変更の判断・ルート調整 | ケア方針変更 | Aさん・Dさん |
| ケア調整担当 | ケア会議の調整・外部連携 | 連携先との調整 | Bさん・Aさん |
| ドキュメント係 | 訪問記録・同意書管理 | 文書の最終確認 | Cさん・Eさん |
| 教育担当 | 研修企画・新人導入 | 研修内容の決定 | Eさん・Bさん |
業務分担表は「作って終わり」ではなく「作ってからが本番」です。
「人を変える」より「変化に適応できるチーム」をつくる
チームづくりの実際が理解できても、自事業所で行うことになると職員の中には不安になる方がいらっしゃいます。
特に、経験とスキルを持っている方にとっては、理解しがたいところがあるかもしれません。
人は「変えられること」に抵抗します。
個人を変えるというより、環境を整え、変化を選びやすくすることが現実的です。
役割と権限を明確にすること、心理的安全性を高めること、経験の浅い職員には小さな成功体験を積ませること、これらが個人の自発性を引き出します。
- 業務分担リストを作成・共有(まずは仮版を作ってみる)
- 週に1回、15分から行動する(情報共有とOODAの短サイクル)
- 月1回のミニ実験を行うつもりで(改善案を1つ決めて1か月試す)
- スキルバンク(得意・経験のあるスタッフ)との同行訪問により学習の運用(月に1回程度)
- 振り返り(失敗含めた成功事例の共有)とセルフケア時間を確保(連休や有給の確保)
まとめ

チームづくりは「継続的な実験」であり、チームづくりに“完成”はありません。
目標を共有し、小さく試し、学びを蓄積していくプロセスが大切です。
訪問看護という現場では、チームの持つ柔軟さがそのまま利用者さんの安全や生活の質に結びつきます。
まずは、今日できる小さな一歩(業務分担リストの共有、15分の話し合い)から始めてみてください。
ビジケアには、組織のマネジメントなど「訪問看護経営の課題解決の支援」を行う訪問看護経営サポートというサービスがあります。
興味のある方はぜひチェックしてみてください。
\詳細はコチラ!/
訪問看護をおこなう中で誰もが不安や疑問に思ったりすることを解決できるような記事の作成を心がけています。
この記事がみなさんの日々の業務に役立ってもらえると幸いです。