
看護師リーダーや管理者さんで、このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
訪問看護は在宅療養を支える重要な社会インフラであり、利用者さんとその家族の生活の質を左右する存在でもあります。
しかし現場では、慢性的な人材不足、業務の属人化、情報共有の不十分さなどにより、チーム体制が脆弱になりやすいという課題を抱えています。
特に近年は、高齢化の進行や在宅医療ニーズの増加に伴い、訪問件数・業務内容ともに複雑化しており、従来の運営方法では限界を迎えつつあります。
こうした状況を改善するには、職場環境の改善に焦点を当てることが不可欠です。
当記事では、最新の課題を整理しながら、リーダー層の育成を含めた具体的な改善策を事例とともに紹介いたします。
最新情報を知りたい管理者さんや看護師リーダーさんは、ぜひ参考にしてみてください!

目次
1. 訪問看護における職場環境の現状と課題
(1) 人材不足と離職の連鎖
訪問看護師の求人数は、他業種と比べても高水準で推移しています。
少子高齢化の影響により在宅医療の需要が急速に拡大しているため、病院やクリニックよりも人材不足が深刻です。
介護職や保育士など福祉系の職種も人材不足ですが、訪問看護は医療知識と臨床経験が必須なため代替が効きにくく、安定して高い求人需要が続いているのが特徴であり、採用難が続いています。
入職後も、訪問業務の孤独感や緊急対応等の負担から離職につながるケースが多く見られます。
一人が退職すると残されたスタッフの負担が増し、さらなる離職を招く「負の連鎖」が生じやすい状況です。
(2) 属人化した業務体制
例えば、「感染対策のことはA看護師しかわからない」というような属人化が進むと、A看護師の休職や退職の際に業務が停滞します。
新人教育の仕組みが未整備な事業所では特に、チーム全体の脆弱性が顕著になっていきます。
(3) リーダー層の不在
プレイングマネージャー的に所長や管理者が現場と管理業務を兼務することが多く、中間リーダー層が育ちにくいという特徴があります。
結果として、所長の不在時に現場が混乱したり、スタッフの意見が吸い上げられないといった課題が発生します。
2. 脆弱なチーム体制を改善するための視点
(1) 情報共有の「仕組み化」
脆弱性を減らす第一歩は、情報の属人化を防ぎ、チーム全体で共有する文化を作ることです。
ICTの導入(電子カルテ、チャットツールなど)はもちろん、対面での短時間ミーティングも有効です。
重要なのは「誰が不在でも業務が滞らない状態」を整えることです。
ある訪問看護ステーションでは、出勤時の申し送りとともに、毎朝10分のオンラインカンファレンスを導入。 カンファレンスであがった重要な内容はチャットツールに残す事にしました。 訪問予定や注意点を共有することで、スタッフが安心して訪問できるようになり、結果として「このケースは誰でも対応可能」という体制が実現しました。 訪問看護は急な対応が発生しやすいため、スタッフのワークライフバランスを意識した体制づくりが欠かせません。 オンコールの負担を公平に分散させる、パートスタッフや非常勤スタッフをうまく活用するなどの工夫が必要です。 オンコール対応を1人で抱えていた事業所では、常勤看護師が疲弊していました。 そこで「一次対応(電話)」と「二次対応(出動)」を分け、一次対応は複数名でシェアする体制に変更。 これによりオンコールの心理的負担が軽減し、離職者が減少しました。 脆弱な体制を改善するには、中間リーダー層の育成が鍵を握ります。 主任・リーダーといった役割を設け、教育・フォロー・調整を担う人材を増やすことが求められます。 課題と対策 課題:リーダーに任命しても役割が曖昧で負担が増すだけになる。 対策:明確な職務記述書を用意し、権限と責任を段階的に付与する。 リーダー研修や外部セミナーに参加できるようにする。 ある中規模ステーションでは、訪看経験3年以上のスタッフを「リーダー」として任命しました。 リーダーには「新人同行の担当」「ケースカンファレンスの進行」を任せ、所長は運営や外部対応に集中できるように。 結果として管理職の負担が軽減し、スタッフのキャリア形成意欲も高まりました。 新人や中堅スタッフへの教育は、リーダー層育成にも直結します。 教育プログラムやマニュアルを整備することで、経験の差に関係なく均質なケアを提供できるようになります。 ある訪問看護ステーションでは「新入職社員育成シート」を導入しました。 訪問の同行回数や習得すべきスキルを可視化し、到達度をリーダーが確認できるようにしたところ、教育のバラつきが減り、スタッフ同士のフォロー体制が自然と生まれました。 新人も「どこまでできれば一人立ちなのか」が分かりやすく、不安軽減につながりました。 訪問業務は孤独感が強く、精神的な疲弊が起こりやすい仕事です。 定期的な振り返り面談や、外部カウンセリングの導入は離職防止に有効です。 ある事業所では、月1回の「お茶会ミーティング」を実施。 リラックスしながら、訪問で困ったことや感情的に負担を感じた出来事を共有する時間を設けました。 管理者が評価する場ではなく「安心して吐き出せる場」にしたことで、スタッフ同士の信頼感が増し、メンタル不調による離職が減少しました。 成果が見えにくい訪問看護では、スタッフのモチベーション維持のために定期的な評価とフィードバックが必要です。 利用者からの感謝の声を共有することも、現場の士気を高めます。 ある中規模ステーションでは「ありがとうボード」を設置。 利用者さんや家族から届いた感謝の言葉や、スタッフ同士の「助かった一言」を付箋で貼り出しました。 日々の小さな感謝が可視化されることで、スタッフが「自分の仕事は誰かの役に立っている」と実感でき、働きがいにつながりました。 書類作成や情報共有の負担を軽減することは、職場環境改善に直結します。 電子カルテやチャットツールを導入することで、訪問先でもリアルタイムに情報共有が可能になります。 ある事業所では、訪問直後にスマートフォンから記録を入力できる電子システムを導入。 従来は帰所後に1〜2時間かけて記録していた業務が短縮され、残業が月平均で8時間から2時間に減少しました。 時間的余裕が生まれたことで、スタッフが研修や自己学習に充てられるようになり、スキルアップとモチベーション向上につながりました。 脆弱な体制を改善するには、中間リーダー層の育成が鍵を握ります。 主任・リーダーといった役割を設け、教育・フォロー・調整を担う人材を増やすことが求められます。 あるステーションでは「リーダー候補ミーティング」を月1回実施。 所長と候補者がケース検討や運営課題を議論する場を設けました。 候補者は現場を見ながら経営的視点を学ぶことができ、所長は次世代の育成を実感できます。 半年後には2名が正式にサブリーダーに昇格し、管理職の業務負担が減少しました。 訪問看護はオンコールや緊急対応が避けられないため、シフトの柔軟性を高めることが重要です。 小規模事業所では、育児中スタッフのオンコール免除制度を導入。 その代わりに日勤業務や新人指導を多めに担当してもらう形に調整しました。 公平性を保ちながら柔軟に役割を分担することで、スタッフが安心して長く働ける環境が生まれました。 このように、教育・メンタルサポート・評価・ICT・リーダー育成・柔軟な働き方の6つの視点から事例を積み重ねることで、訪問看護の職場環境は着実に改善されます。 これからの訪問看護に求められるのは、人材不足を前提とした「しなやかなチーム作り」です。 すべてのスタッフが多能工的に動ける体制、リーダーが現場を支える仕組み、ICTを活用した効率化が鍵になります。 リーダー層を計画的に育てることは、単に人材の階層を増やすだけではありません。 スタッフが安心して働き続けられる「持続可能な職場環境」を作るための基盤となります。 訪問看護の職場環境改善は、単なる福利厚生や制度の話にとどまらず、利用者さんへの質の高いケアを継続するための必須条件です。 脆弱なチーム体制を改善するには、情報共有の仕組み化、働きやすい勤務体制、そしてリーダー層の育成が不可欠です。 現場に根差した小さな改善を積み重ねることで、看護師一人ひとりが安心して力を発揮できる環境が整い、その先に「地域に信頼される訪問看護ステーション」が育っていきます。 今回の事例と対応策を、明日からの現場に活かしていきましょう。 (2) 働きやすさを意識したシフト調整
(3) リーダー層の育成
3. 訪問看護の職場環境改善に向けた具体策
(1) 教育体制の整備
(2) メンタルサポートの導入
(3) 評価とフィードバックの仕組み
(4) ICTを活用した業務効率化
(5) リーダー層の育成
(6) ワークライフバランスへの配慮
4. これからの訪問看護 |チームの「しなやかさ」を育む
まとめ
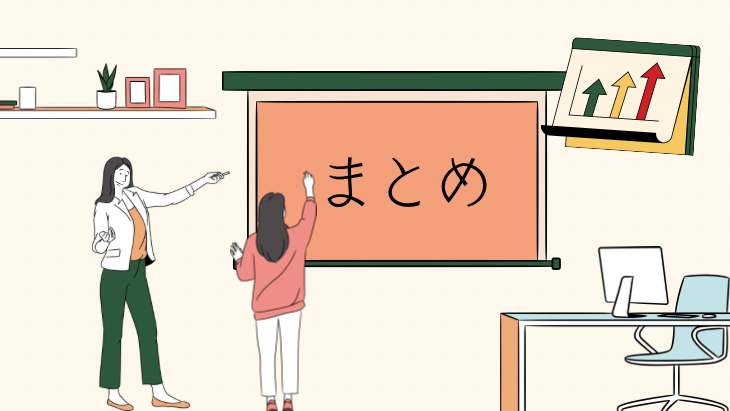
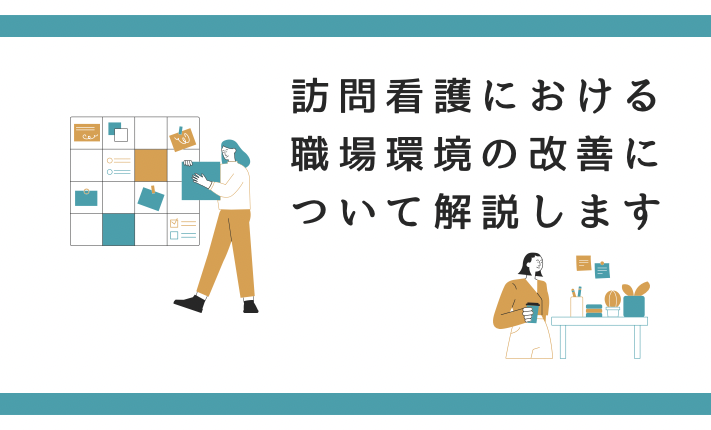
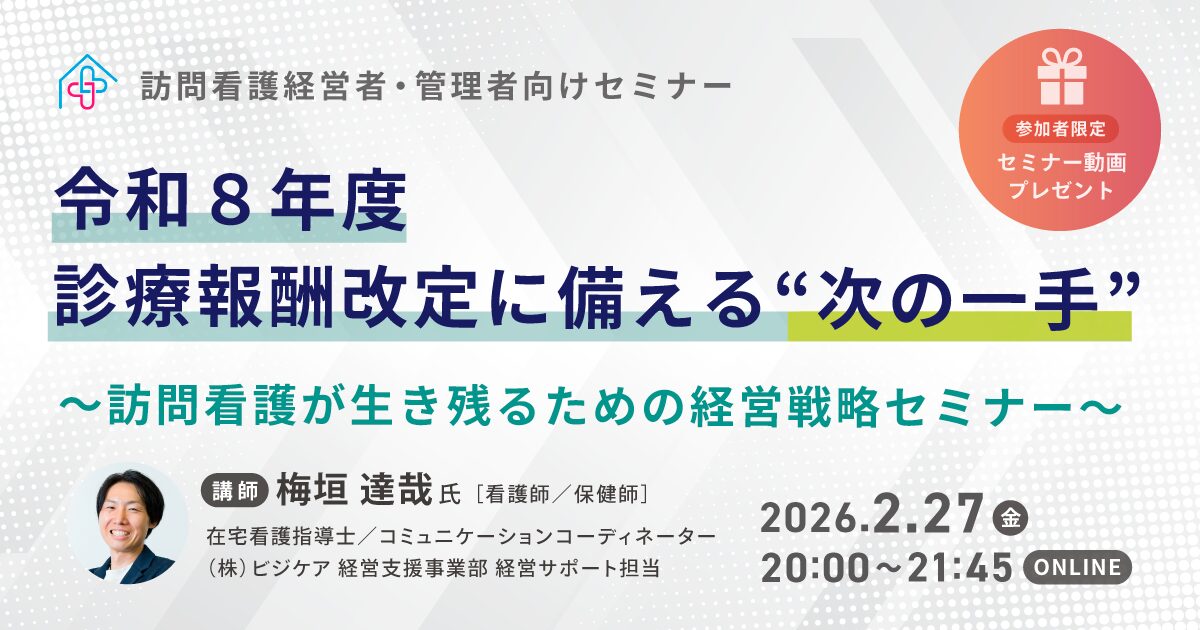
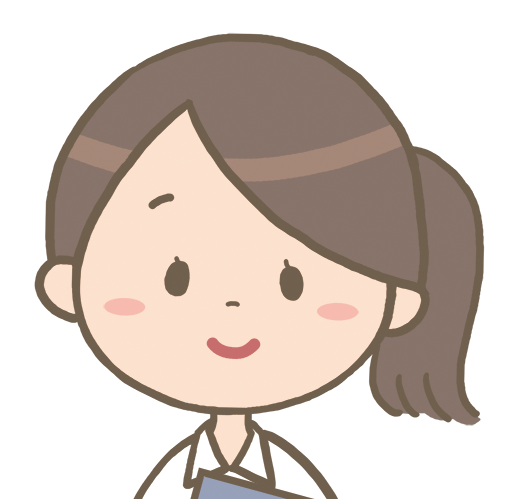
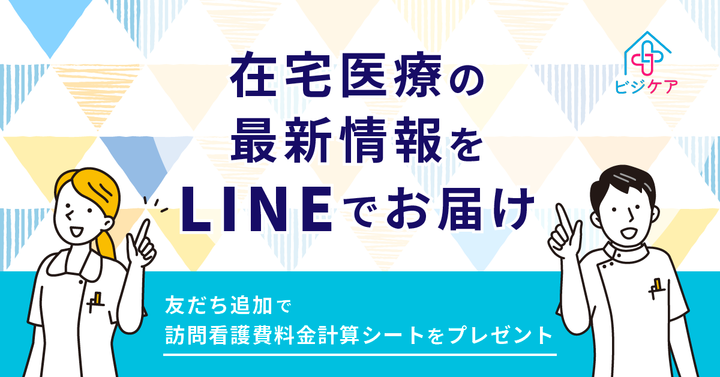


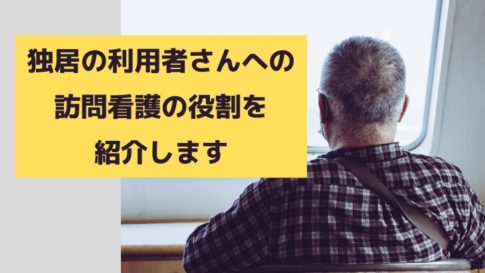
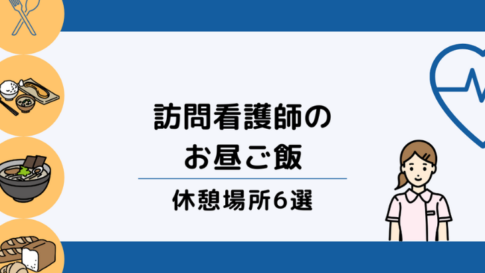




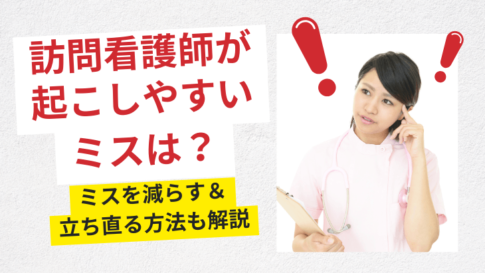


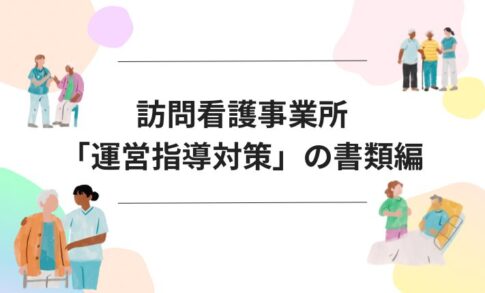
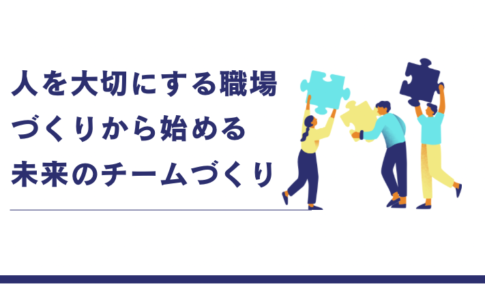
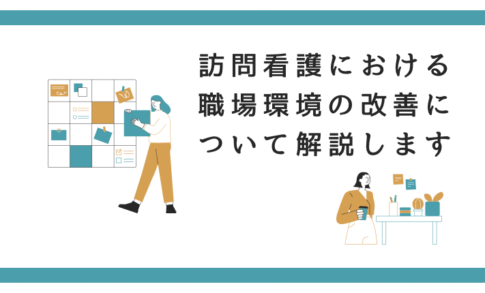
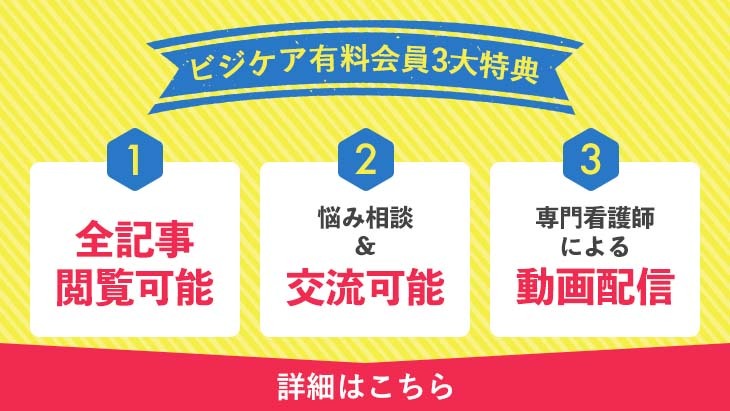

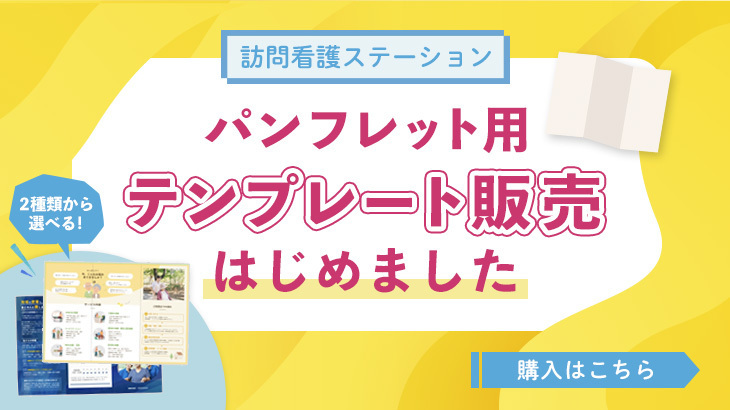
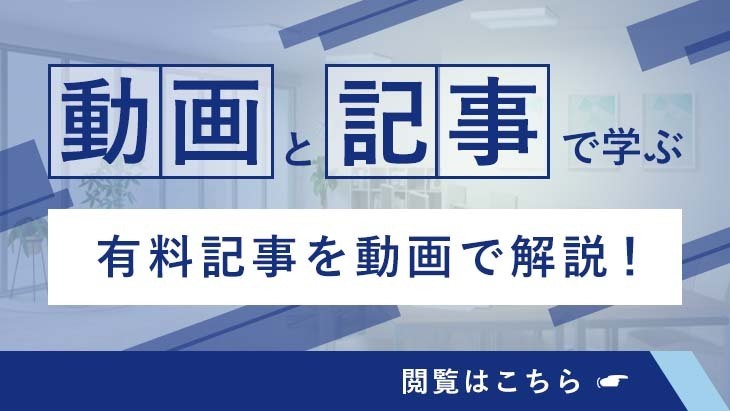
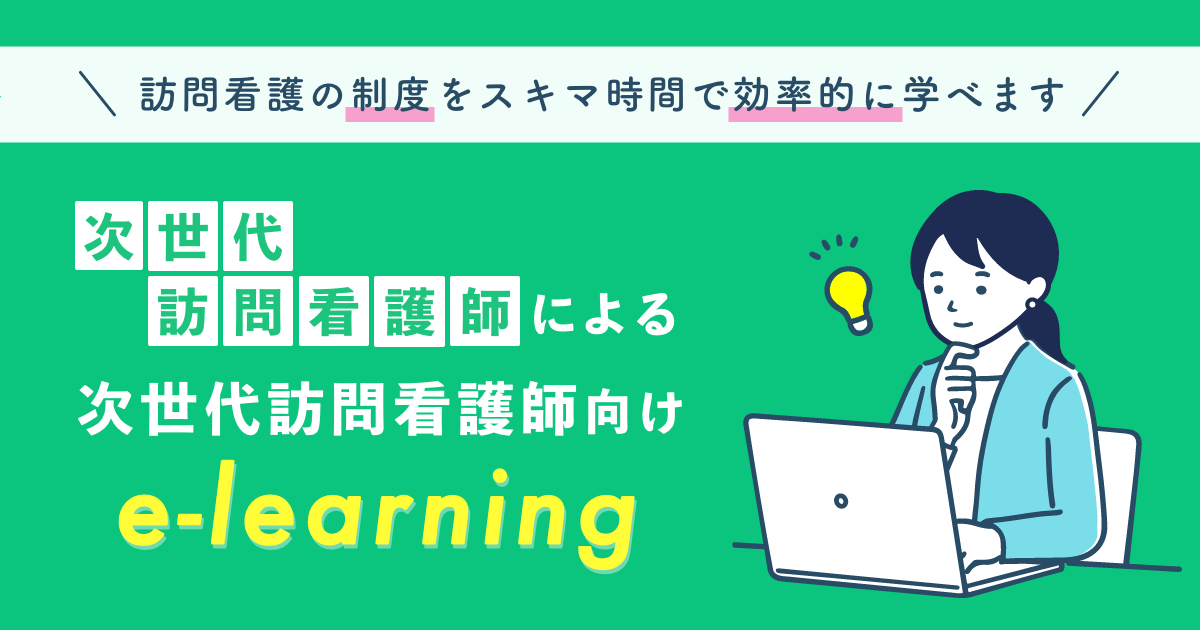
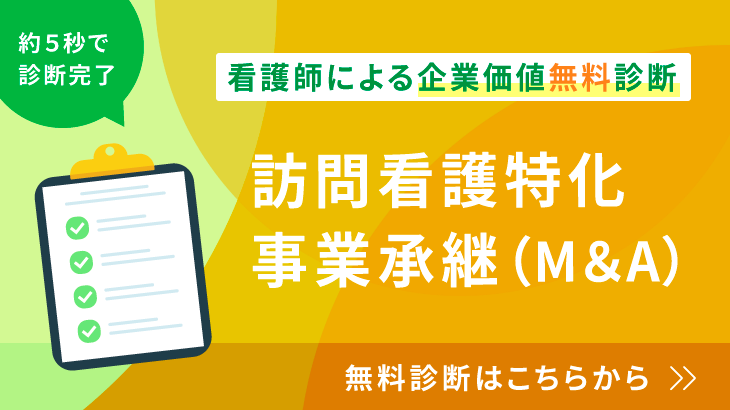
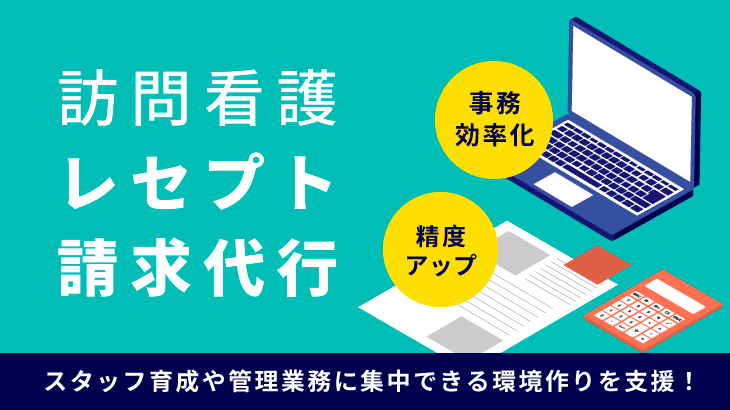

訪問看護ステーションでの職場環境の改善策はどんなことがあるのかな?
よい解決策はあるのかな…。