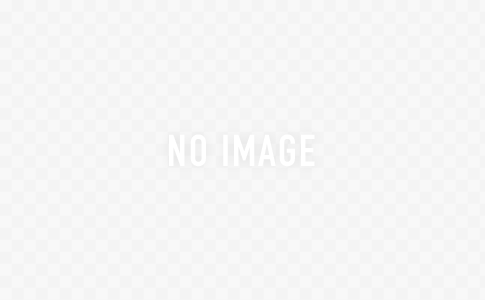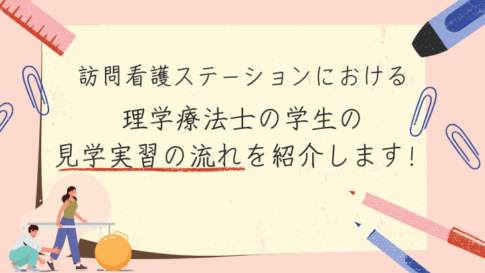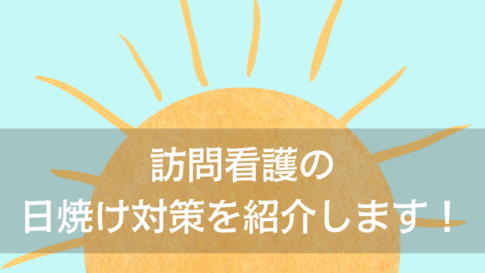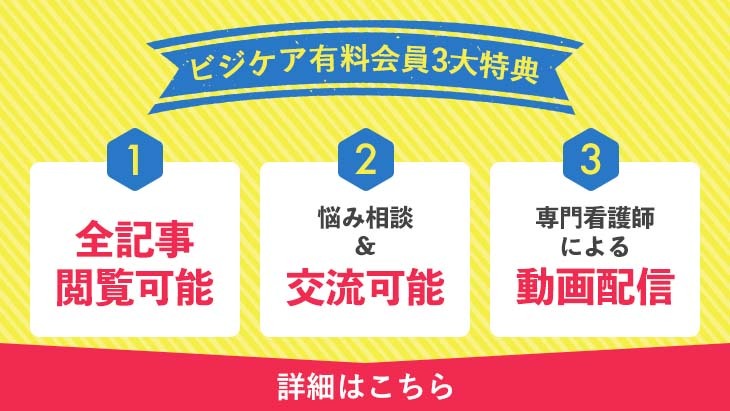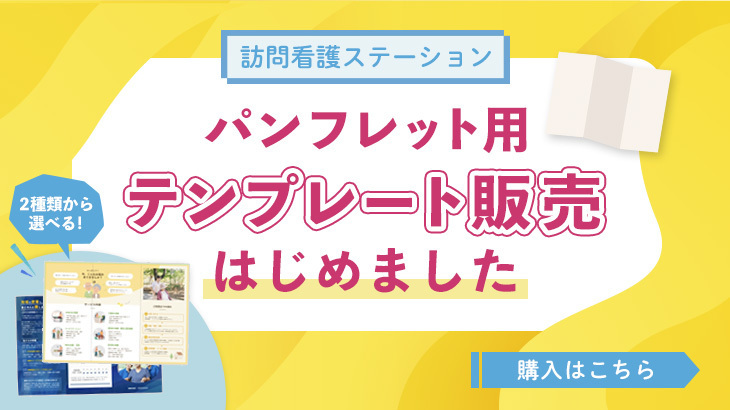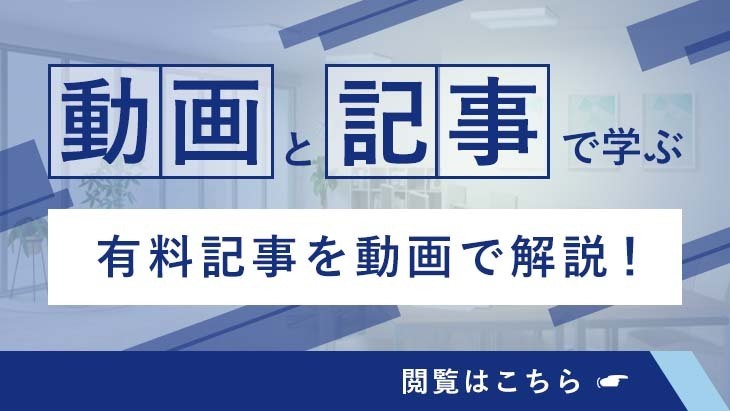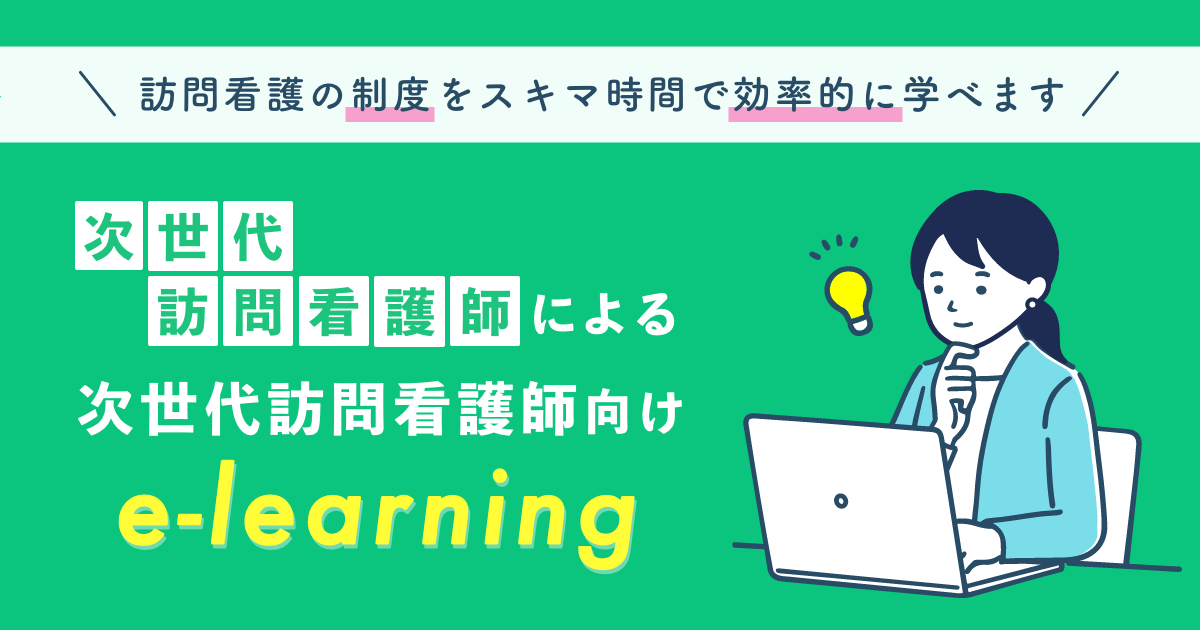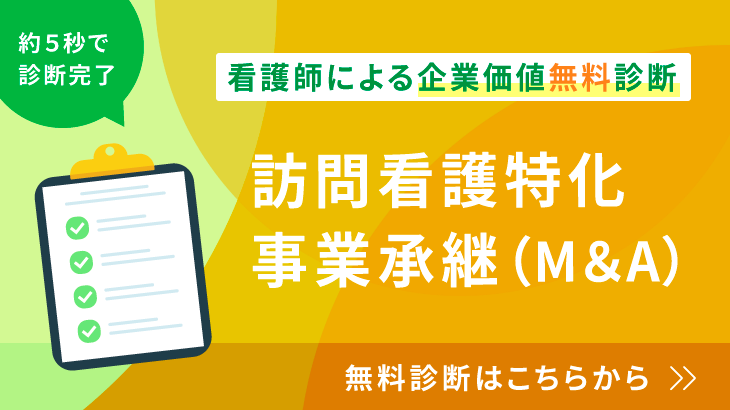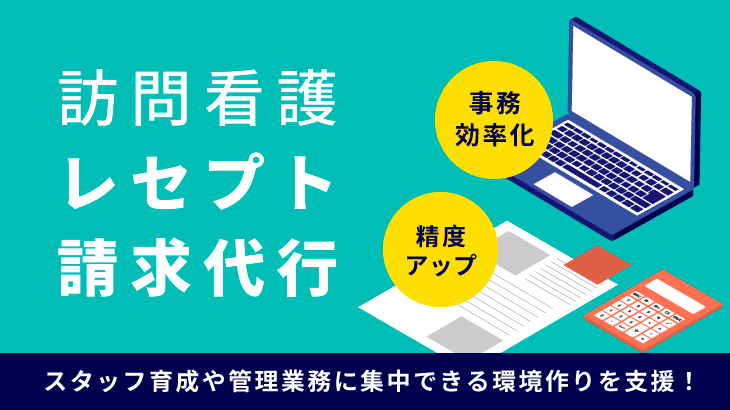昨今、高齢化や住み慣れた場所で最期を迎えたいと希望する方が増加し、訪問看護の需要が増えています。
訪問看護の現場では、医師の指示のもとでさまざまな医療行為が求められます。
しかし、「訪問看護師がどこまでの医療行為を実施できるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
医療行為の範囲は、法律や制度によって細かく定められており、適切に理解し対応することが必要です。
今回は、訪問看護における医療行為の範囲を制度上のルールを交えてわかりやすく解説します。
目次
訪問看護とは?

訪問看護とは、病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう、多職種と協働しながら看護師などが居宅を訪問して主治医の指示や連携により行う看護です。
訪問看護で行える医療行為は幅広く、訪問看護の需要に伴い医療処置の実施件数も年々増加しています。
また、要介護度が高くなるにつれて医療行為も多くなる傾向にあります。
医療行為の範囲について

訪問看護は、病状や状態によって「介護保険」「医療保険」どちらかを利用します。
訪問看護では、それぞれの保険制度を定めている「介護保険法」および「健康保険法」に関連する省令において、「主治の医師による指示を文書で受けなければならない」と定められています。
訪問看護指示書とは
訪問看護指示書とは、主治医が利用者さんに訪問看護の必要性があると認めた際に、訪問看護ステーションに対して交付する文書のことを言います。
訪問看護を利用者さんに提供するには、訪問看護指示書がなければ介入することができません。
訪問看護指示書の有効期限は最長6カ月ですが、利用者さんによって指示期間は違います。 その都度、訪問看護師は主治医と連携をとり、利用者さんの状態やニーズに合わせた指示内容の変更や指示書の更新を主治医に依頼する必要があります。 看護師の業務は、保健師助産師看護師法第5条により「療養上の世話」と「診療の補助」に大別されています。 「療養上の世話」については、原則として看護師が独立した業務として行えます。 「診療の補助」については、医師の指示を受けることを正当業務の要件としています。 医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為」と定義されています。 医行為には、医師(又は歯科医師)が常に自ら行わなければならないほど高度に危険な行為である「絶対的医行為」と、医師又は歯科医師の指示、指導監督の下に看護師が行う行為「相対的医行為」があります。 相対的医行為は、保健師助産師看護師法第5条による「診療の補助」にあたります。 訪問看護師は、主治医の発行した訪問看護指示書に基づいて以下の医療行為を行うことができます。 また、特定行為研修を受講した訪問看護師は医師が作成した手順書に基づき医療行為を行うことができます。 利用者さんの状態に変化があった場合は、すぐに主治医に報告して指示を仰ぎましょう。 医師の指示がなくても行える医療行為が厚生労働省の通知で「非医行為」として定義されています。 これらは、医行為にあたらないため、看護師でなくても行うことが可能です。 訪問看護における医療行為には、医師の指示が必要なものと、看護師の判断で行えるものという制度上のルールによって実施できる範囲が明確に定められています。 訪問看護師として制度を遵守することが、安全な訪問看護の提供につながります。 また、医療行為と非医療行為の境界を理解することで、介護士さんや家族の方との役割分担を適切に行うことも重要です。 訪問看護師として、最新の制度を理解し、適切な医療ケアを提供することで、利用者さんの在宅療養でのQOL向上にもつながります。 訪問看護師として制度を理解して、安心・安全な訪問看護を実践していきましょう。 訪問看護師が行える医療行為の範囲
訪問看護師が行える医療行為
訪問看護師が行えない医療行為
医師の指示が必要でない行為
まとめ


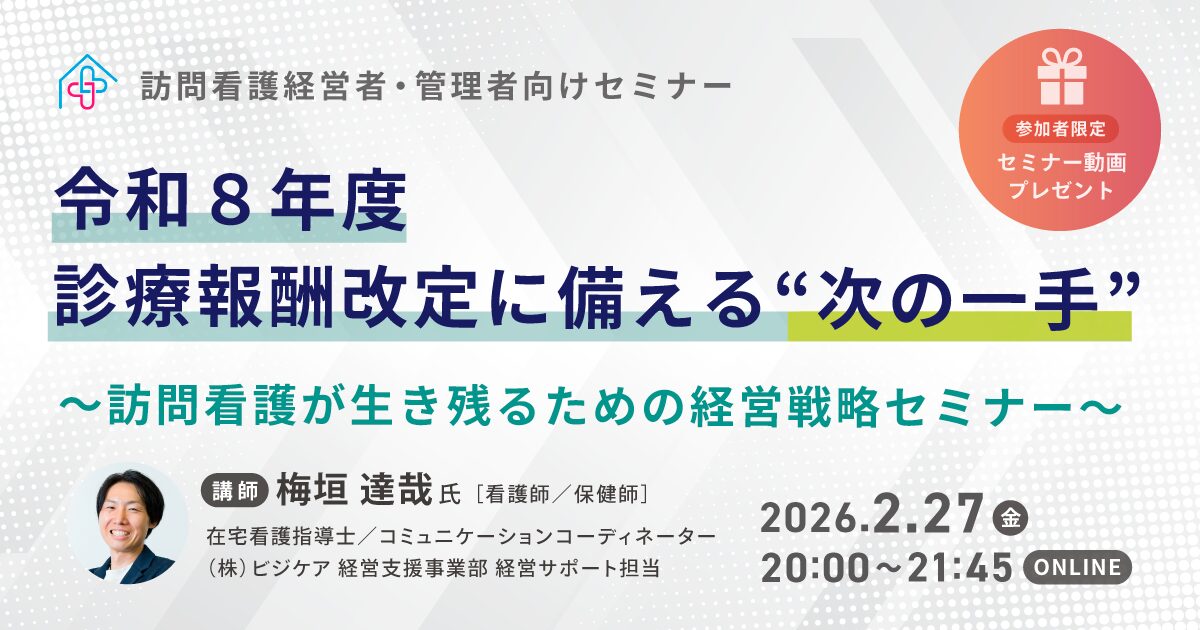

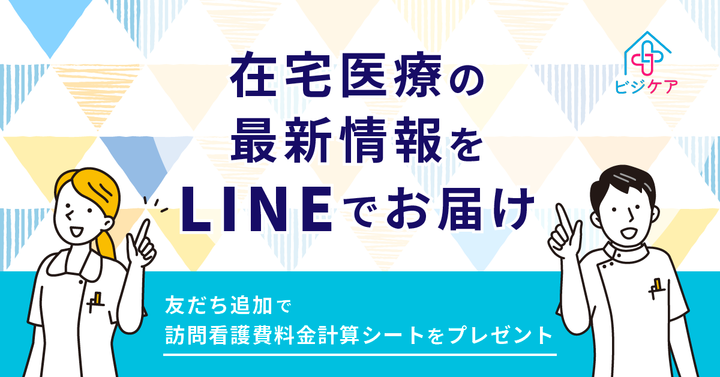

-150x150.png)
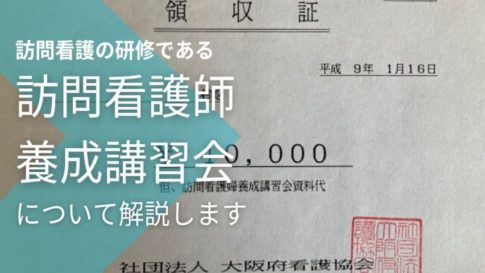
における-後輩指導のポイント3選-2-485x273.png)